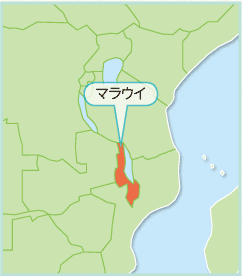コラム 5 みんなで手を取り合った開発を~COP10名誉大使MISIAさんへのインタビュー~
アフリカをはじめとする開発途上国の子どもたちの教育を支援されていますが、現地を訪問された際に印象深かったことなどをお聞かせください。
ケニアの首都ナイロビにあるキベラスラムの小学校を訪れたときのことです。読み書きができないため、毒薬を薬だと思って自分の子どもに飲ませてしまったお母さんや危険という文字が読めないばかりに、危ない場所に立ち入ってしまう子どもの話が印象に残りました。読み書きの能力は、安全に暮らすためだけではなく、世界へのアクセスを可能にするものだと感じています。また、学校は、子どもたちやその親たちが情報交換を行ったり、語り合うことで心の癒しを得たり、子どもたちが給食を食べられ、シェルターにもなる場所であることを知りました。これらの経験は、私がアフリカで子どもの教育支援を行うきっかけとなりました。「貧困とは何か?」と私はいつも心に問いかけながら、マラウイやマリ、2010年には南アフリカ共和国を訪れ、支援活動などを行っています。
国連事務総長よりCOP10 名誉大使に任命されましたが、生物多様性の保全には何が必要だと思われますか。
生物多様性とは、あらゆる命がつながり合い、支え合っている状態を意味しています。私たちの衣・食・住はもちろん、医薬品、多様な文化なども、その根源に豊かな生態系があってこそ成り立っているものです。国境、人種を超え世界中の人々が生物多様性について「知識」と「意識」を持つことが必要だと思います。以前、里山を訪れたときに案内していただいた方に、「自然界には、害虫という虫も、雑草という草もない。生き物には、すべて役割があり、まだまだ人間が自然のことを知らないだけ」といわれたことがあります。私たちは、自然を畏れ敬う気持ちをもう一度思い出す必要があると感じました。COP10での議論の結果が、私たちの命や暮らしを守る一助になってほしいと願っています。さらに、生物多様性は多岐にわたる問題なので、その保全には研究者やNGO、企業、国際機関など様々な立場の人が、協力し合い取り組むことが必要だと思います。
日本のODAをはじめとする開発協力に何を期待しますか。
「共に生きていること、共に生きていくこと」を意識した開発協力であることが大切だと思います。そして、本当にサポートを必要としている人々に、サポートが届くことが必要です。アフリカで、開発によって湖が汚染され、魚が獲れなくなるなどして、今までの生活を続けることが困難になったという話を聞いたことがあります。無秩序な開発は、より一層の貧困を生み出すということを知りました。私は、Love is Free Campaignという、マラウイに蚊帳を贈る支援活動を行っています。 2010 年の2月に第1回配布を行ったのですが、その後、現地コーディネーターに蚊帳の使用状況を調べてもらいました。次回の配布事業をより現地のニーズに合ったものにしていくためです。このように、支援する側の一方的な開発ではなく、現地の人々と共にみんなで手を取り合って開発が進められることを期待しています。

2008年マラウイにて(右がMISIAさん) (写真提供 : Child AFRICA)

マラウイでマラリア予防啓発を行う現地NGO代表と(左がMISIAさん) (写真提供 : Child AFRICA)