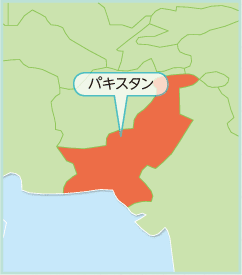コラム 4 水道はみんなの財産~パキスタンの水道改良事業~
日本では水は簡単に手に入り当たり前に飲めますが、多くの開発途上国では、遠くの井戸まで水を汲みに行ったり、冠婚葬祭時などの大量に水が必要なときは水売りから買うなど、水の確保は大きな負担となっています。日本は、水は生命の根幹であり、MDGs達成のために水の問題はきわめて重要と認識し、安全な水が得やすくなるように、開発途上国に対していろいろな支援を行っています。
パキスタンでは、日本のNGOである「日本地雷処理を支援する会」JMAS(ジェーマス)が、日本政府と連携し*1、2009年6月から首都イスラマバードに近いパンジャブ州マリー地区で、水道施設をつくる支援*2を行っています。パキスタンの水事情は深刻で、水道施設の不足のほか、水そのものが汚染されているといった問題もあり、1年間に約35万人が不衛生な水が原因で命を落としています。また、雨の降らない時期には汲み上げる水そのものが少なくなってしまうこともあり、遠くから水を汲みに来た女性や子どもは、水を運ぶ壺をいっぱいにするのに数時間を要したり、順番待ちのために徹夜をすることもあります。
JMASのパキスタン代表を務める筧(かけひ)さんは、「水は電気やガスと違い、生きていくために毎日必ず必要なものです。私たちの取組が良質な水の確保と日本とパキスタンの友好関係の増進に少しでも役立てばと思います」とこのプロジェクトへの抱負を語ります。
多くの住民から待ち望まれた水道ですが、いくつかの難しい場面にも出会いました。水汲み場となる水タンクの地主が土地代を求めたり、住民の期待が大きいためか、予算を超える数のタンクの設置を要望されたり、さらには、各家庭まで水道管を敷設することはできないかといった要望などもありました。筧さんは、住民に対し粘り強く予算の規模や「水道はみんなの財産」であることを説明し、意見をまとめていきました。
こうして、2010年4月のフェーズ1終了時には、大小4つのタンクを設置し、合計10kmに及ぶパイプを敷設しました。*3
水道施設の建設のほかに、筧さんは、住民に働きかけ、水道組合を設立しました。これは、JMASの国際協力に際しての考え方である自立支援に沿うもので、将来、住民自身で施設の維持管理ができるようにするためです。「住民が自分たちの財産として、自らの手で、良質な水と施設を末永く守ってほしいと思います」という筧さんは、水質検査の方法、タンクのクリーニング方法や水道パイプの接続方法などの技術を教えました。
このような筧さんたちの取組のおかげで、地元の人々の意識にも変化が現れ、水道施設を大切にしようという意識から、この地区に住む人々は水タンクの蛇口を保護するステンレス製の箱に「水を無駄にしないこと」と書くようになりました。
また、水道施設の建設は、今まで主に水汲みをしていた子どもや女性の生活に変化をもたらしました。重労働であった水汲みから解放され、女性は家事や育児の時間が持てるようになり、そして子どもたちは学校に通えることになった結果、勉強に集中することができるようになりました。
筧さんは、マリー地区の将来についてこう語ります。「この水道施設はJMASが日本人の支援を得て造った住民の皆さんの共有財産です。この施設をいつまでも大事に守って欲しいと思いますし、守っていただけると確信しています」。
*1 : 日本NGO連携無償資金協力
*2 : パンジャブ州マリー地区郊外水道改良事業(フェーズ1)
*3 : 2010年6月からはフェーズ2を開始

完成した水道施設の前で(左から3人目が筧さん)(写真提供 : 筧さん)

水汲み場での少年たち(写真提供 : 筧さん)