2. 南アジア地域
●約8億3,652万ドル(約27億3,485万ドル)
●二国間援助全体の約12.1%(約18.4%)
南アジア地域は、世界最大の民主主義国家であるインドをはじめ、高い経済成長を達成する国や大きな経済的潜在力を持つ国があり、国際社会における存在感を強めています。地理的には、アジアと中東を結ぶ海上交通路に位置し、日本にとって戦略的に重要であるほか、地球環境問題への対応という観点からも重要な地域です。また、インドやパキスタンにおける大量破壊兵器の問題やテロおよび過激主義に対する国際的取組における役割といった観点からも、日本を含む国際社会にとって関心の高い地域です。
一方、南アジア地域は、道路、鉄道、港湾など基礎インフラの欠如や人口の増大、初等教育における未就学率の高さ、水・衛生施設や保健医療制度の未整備、不十分な母子保健、感染症対策および法の支配の未確立など取り組むべき課題が依然多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、同地域に居住する15億人近い人口のうち5億人近くが貧困層といわれ、世界でも貧しい地域の一つです。ミレニアム開発目標(MDGs)達成を目指す上でもアフリカに次いで重要な地域となっています(注62)。
注62 : 2009年のMDGsレポートによれば、一日約1ドル以下で生活する人の割合は39%(2005年)で、これはサブ・サハラ・アフリカに次いで高い数字である。
< 日本の取組 >
日本は、南アジア地域の有する経済的潜在力を活かすとともに、拡大しつつある貧富の格差を緩和するため、社会経済インフラ整備の支援を重点的に行っています。特に同地域の中心的存在であるインドとは、基本的価値観を共有する「戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づいて、政治・安全保障、経済協力、学術交流など幅広い分野で協力を進めています。インドは日本の円借款の最大受取国であり、電力や運輸などの経済インフラの整備と共に、農村環境整備など貧困削減に向けた社会セクター開発も進めています。
パキスタンについては、2009年4月にパキスタン・フレンズ閣僚会合および支援国会合を東京で開催しました。支援国会合では、テロ対策と経済改革に取り組むパキスタンに対し、参加国・機関から総額50億ドルを超える支援が表明され、日本も最大10億ドルの支援を表明しました。
スリランカでは、2009年5月に25年以上にわたる政府軍とタミル・イーラム解放の虎(LTTE)との戦闘が終結しました。ラージャパクサ大統領は、民族融和のための政治解決を進め、国家開発に取り組むことを表明しました。日本は、スリランカの平和の定着の促進や社会経済開発を支援するため、地域・民族バランスにも配慮しつつ、支援を実施しています。
また、南アジア地域では、各国で援助協調に向けた取組が進んでいます。たとえば日本は、2005年に世界銀行、アジア開発銀行、英国国際開発省と対バングラデシュ共通援助戦略を策定し、援助政策の連携を進めています。また、バングラデシュ政府が策定した貧困削減戦略文書をより効果的に実施するため、主要な援助国・機関を中心に援助協調・連携を進めています。

バングラデシュにおける教育支援・心理ケア事業(写真提供 : (特活)国境なき子どもたち)
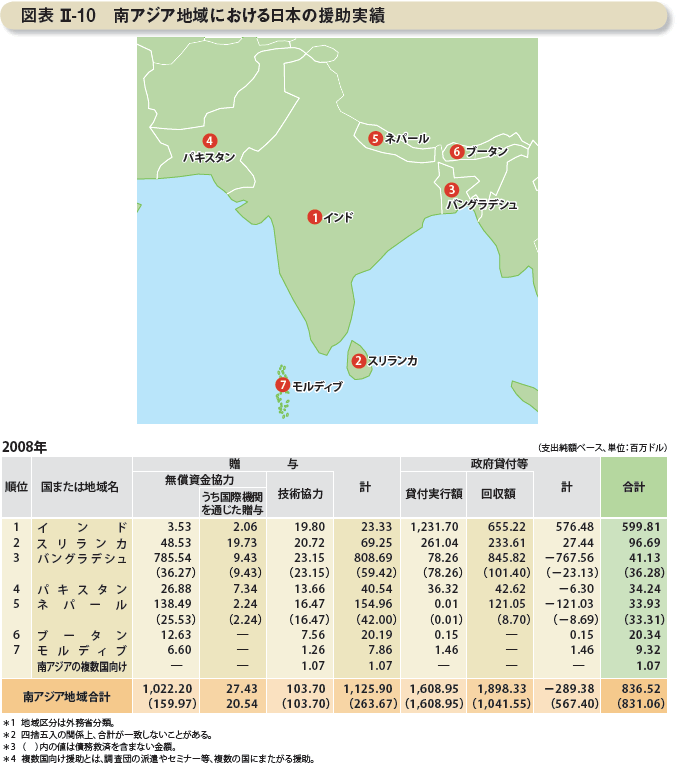
中小零細企業・省エネ支援計画(インド)
インドにおける環境改善は、同国の持続的な経済発展、さらには地球規模の気候変動対策という観点からも重要です。こうした状況を踏まえ、日本は、インドの中小零細企業に対し、300億円の円借款を通じて、省エネの取組に必要な中長期資金を供給しています。融資の実施者であるインド小企業開発銀行やその他仲介金融機関のネットワークを活用することで、インド全土における幅広い省エネ支援を行うとともに、これら金融機関の融資審査能力の強化も支援しています。
ダッカ市廃棄物管理能力強化プロジェクト(技術協力プロジェクト)およびダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画(無償資金協力)(バングラデシュ)
人口が1,200万人を超える首都ダッカでは、家庭ゴミなどの収集率が低く、多くのゴミが街にそのままになっています。また、収集に出されるゴミの量も増え続けており、衛生、環境上深刻な問題になっています。日本は、技術協力にて、住民参加によるゴミ収集活動の普及や、環境負荷の少ない処分場の整備、廃棄物対策を担うダッカ市役所の体制強化などを支援しています。その結果、市民による自発的な収集活動が進み、処分場の環境もかなり改善されました。また無償資金協力では、約100台の廃棄物収集車両を供与しました。二酸化炭素の排出量が少ない型の収集車を供与することで、温室効果ガス削減対策も同時に行っています。