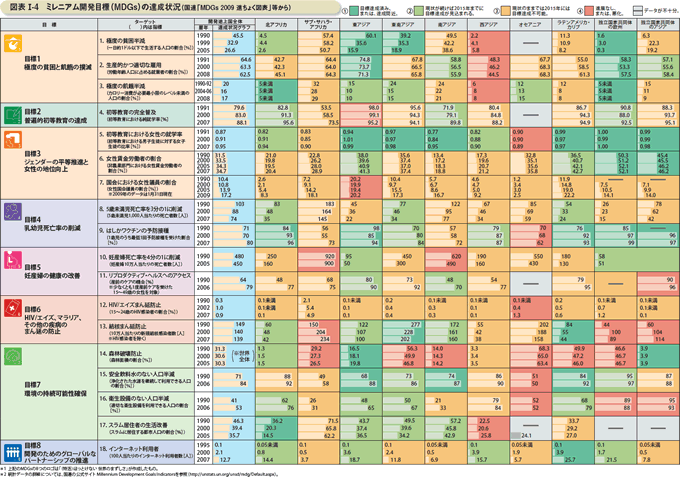2. その他の具体的環境協力
急速な経済成長や都市化が進んでいる開発途上国は、気候変動問題のみならず、大気汚染や水質汚濁などの様々な環境問題に直面しています。日本は、2002年に策定した「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ」(EcoISD)(注14)において、「我が国の経験と科学技術の活用」を基本方針の一つに掲げ、日本の公害問題での経験を活かすとともにすぐれた環境技術を適用し、都市部の公害対策および住民の生活環境改善などに取り組んできました。たとえば、ベトナムでは全国の水環境改善を目的として水質モニタリングや汚染源工場の取締り強化などのための技術協力とともに、円借款によりハノイ、ホーチミンなどで下水処理施設の整備を支援しています。また、住民や企業などの協力に基づくゴミの減量化、再利用、リサイクル(3R(注15))を実現するため、中国、ベトナム、フィジー、メキシコなどで技術協力を行っています。
また、地域住民の生活環境を考慮しつつ、日本の国立公園制度に模した自然保護区などの保全管理、持続可能な森林経営、砂漠化対策に対する支援などを実施し、開発途上国における自然環境を管理・保全し、生物多様性の保全を図っています。たとえば、メキシコでは、ユカタン州の保護区内のマングローブ生態系の保全や自然資源の持続可能な利用促進を行政機関と地域住民が一体となって実施する協力を行っています。
さらに、「国際生物多様性年」である2010年の10月に、愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されます。COP10では、2010年以降の世界目標(ポスト2010年目標)が設定される予定であり、日本は議長国として具体的な提案を行うことなどを通じてCOP10を成功に導くとともに、生物多様性に係る協力を一層推進していきます。
とりわけ、生物多様性を保全する上で森林生態系の保全は非常に重要です。日本は二国間ODAや国際機関・基金などへの拠出を通じて、開発途上国における持続可能な森林経営の促進、森林減少・劣化の抑制、違法伐採対策などを積極的に支援しています。たとえばインドネシアでは、2008年9月より、陸域観測技術衛星「だいち」の画像を活用した森林資源管理のための技術支援と人材育成を目的とする協力を実施しています。
また、日本は、地球環境の現況と変化を把握するために世界の国家地図作成機関が協働して土地被覆・植生などの地球全体の地図を整備する「地球地図プロジェクト」を推進しています。2009年には教育関係者や環境・防災NGOなどを対象とした地球地図セミナーや世界の国家地図作成機関の関係者および環境・防災の専門家を集めたワークショップを開催しました。
今後とも、日本は環境・気候変動分野で積極的に協力していきます。
注14 : EcoISD:Environmental Conservation Initiative for Sustainable Development
注15 : 3R:Reduce, Reuse, Recycle

地球地図による植生地図
図表I-4 ミレニアム開発目標(MDGs)の達成状況(国連「MDGs2009 進ちょく図表」等から)(クリックすると拡大されます。)