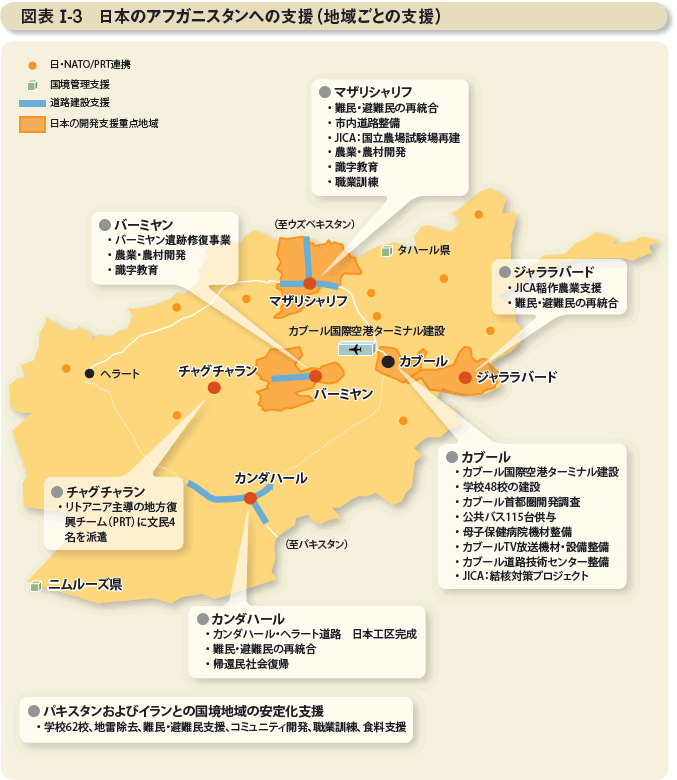2. 日本の対アフガニスタン支援
アフガニスタンにおける安定と繁栄の実現は世界全体の平和と安定につながるという考えに基づき、アフガニスタンを「テロと麻薬の温床」にしないとの決意の下、日本は一貫して支援を実施してきました。2002年には、「アフガニスタン復興支援国際会議(東京会議)」を主催し、45億ドル以上の国際社会からの支援を確保した上、最大5億ドルの支援を表明しました。2009年11月、日本は「テロの脅威に対処するための新戦略」を新たに発表し、アフガニスタンに対して早急に必要とされる約800億円の支援を行うとともに、これまでに約束をした総額約20億ドル程度の支援に替え、今後の同国の情勢に応じて、2009年からおおむね5年間で、最大約50億ドル程度までの規模の支援を決定しました。具体的には、警察支援などを通じた治安能力向上支援、元タリバーン末端兵士の社会への再統合のための職業訓練および雇用機会創出のための支援、同国の持続的・自立的発展のための農業・農村開発、エネルギー分野を含むインフラ整備、教育、保健医療などの基礎生活分野などを柱に、支援を実施していきます。また、パキスタン、中央アジアなどの周辺諸国との連携をも見据えた開発が必要であるとの観点から、アフガニスタンとその周辺諸国地域全体の安定と繁栄を促進するための地域開発支援も重視しています。政治プロセス・ガバナンスに対する支援については、国家の枠組みを形成する基本システムの回復を目的にしており、たとえば、2009年8月の大統領選挙に向けた環境整備などのため、約3億ドルを拠出しました。
2001年10月以降2009年末までの日本の支援総額は約18億ドルに上ります。このうち、治安の改善に対する支援については、2006年6月に旧国軍兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR(注5))が完了した後も、引き続き非合法武装集団の解体(DIAG(注6))において主導的な役割を担っています。また、警察支援や地雷対策など、平和の定着に不可欠な治安回復のための支援も行っており、2008年度には、アフガニスタンの全警察官約8万人(注7)の半年分の給与に相当する警察支援などを実施しました。
加えて、カブール国際空港ターミナルビルの建設やカンダハール・ヘラート道路整備などのインフラ整備に協力したほか、教育分野では550以上の学校の建設と修復や1万人の教師育成など、保健分野では延べ4,000万人に対するワクチン供与や50のクリニック建設、さらには、稲作支援や農村開発のため、全土で約2,000のコミュニティに根ざしたプロジェクトの実施など様々な分野で大きな貢献をしています。
現在のアフガニスタンは、緊急人道支援を要する段階から復旧・復興支援の段階を経て、本格的な開発支援を必要とする段階へ徐々に移行しつつあり、アフガニスタン国家開発戦略(ANDS(注8))に沿った開発が国際社会の支援の下、着実に進められています。
さらに、アフガニスタンの地方支援拡大のため、地方復興チーム(PRT(注9))と連携しつつ、初等教育、職業訓練、保健医療、衛生の分野での活動を実施するNGOなどに対し、草の根・人間の安全保障無償資金協力を行う枠組みを構築し、2009年10月までに12のPRTと連携し、58件の事業を実施しています。2009年5月には、ゴール県のチャグチャランPRT(リトアニア主導)に対し、PRTへの日本人文民派遣を初めて実施し、復興のための地域のニーズをきめ細かく調査する活動などを行い、地方に対する支援を強化しています。
2008年8月には、日本のNGOに所属する邦人職員が殺害されるなど、アフガニスタンでは、依然として厳しい治安状況が続いています。このような状況においても、日本は国際社会における重要な役割を果たすべく、援助関係者の安全確保に向け最大限配慮しながら、同国に対する様々な支援活動を行っています。
注5 : DDR:Disarmament, Demobilization and Reintegration
注6 : DIAG:Disbandment of Illegal Armed Groups
注7 : 人数は当時の定員数。
注8 : ANDS:Afghanistan National Development Strategy
注9 : PRT:Provincial Reconstruction Team:PRTとは、北大西洋条約機構(NATO)の軍人及び文民復興支援要員から構成される組織で、アフガニスタン各地において治安改善と復興支援を同時に推進することによって復興開発支援の成果を上げ、アフガニスタン政府の影響力の地方拡大を支援している。

ポリオ・ワクチン接種キャンペーンにカルザイ大統領と同席した岡田克也外務大臣

学校を視察する岡田克也外務大臣(写真提供 : 時事通信社)