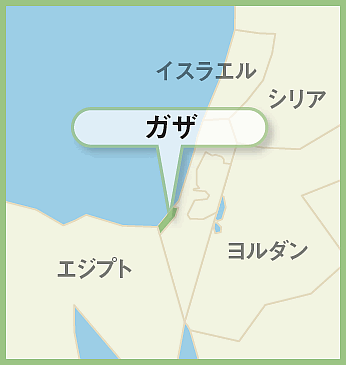コラム 16 あたたかい毛布を避難民へ~日本のパレスチナ支援 国連パレスチナ難民救済事業機関 羽隅温子さん~
2008年12月27日、ガザ地区は再び戦禍に巻き込まれ、多くの死傷者が出ました。国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)も、その事務所や学校、医療センターが攻撃を受け、戦闘中は人道支援活動にも大きな影響が出ました。停戦後、日本政府はガザ地区への物資の緊急支援を表明し、29,000枚の毛布、20,000枚のスリーピングマットおよび8,000枚のビニール・シートを送りました。*1今回、UNRWA職員としてこの支援で活躍された羽隅さんは、フランス留学中にコソボからのアルバニア系難民と交流し、難民問題に興味を持つようになり、国連コソボ行政ミッション(UNMIK)勤務などを経て、2007年9月よりUNRWAガザ事務所で、パレスチナ難民への人道支援に従事しています。羽隅さんに当時のガザ地区への支援の様子などについて寄稿していただきました。
*1 : 国際平和協力法に基づく物資協力
戦闘中、私はガザ地区勤務の他の同僚と共に、一時的にエルサレムに配置されました。UNRWAによるガザ地区内での緊急支援活動を外から支援するために、人員が必要だったからです。
私のエルサレムでの主な仕事の一つは、ドナーへの対応でした。UNRWA向けに支援を表明してくれたドナーと緊密に連絡を取り、ガザ地区内で活動する同僚からの情報をもとに、ガザが何をいつまでにどれくらい必要とし、支援物資をどこに輸送してもらうか、という情報を発信し続けました。各国政府、NGO、一般企業や個人から提供された人道支援物資は続々と到着し、これらをいかに迅速かつスムースにガザ地区内に輸送するかが大きな課題となりました。戦闘という非常事態だけでなく、イスラエルによる継続的な封鎖が、ガザへの支援物資の搬入を阻んでいたからです。
ガザ地区への物資輸送は、陸路でのみ可能です。戦闘当時、イスラエルへ通じる4つの物資用検問所のうち、開いていたのはケレム・シャロームのみで、最大の物資搬出入口であるカルニ検問所は閉鎖されたままでした。このケレム・シャローム検問所を通じて、一日およそトラック100台分ほどの援助物資の搬入が許可されていました。そのうち、UNRWAが与えられた枠は約60台分。当時ガザ地区では、何万人もの避難民が発生していました。UNRWAは戦闘中に、UNRWAが運営する学校の校舎や他の施設を住民のための緊急避難シェルターとして開放していましたが、その数は最も多いときで50箇所。受け入れた避難家族は8,000を超え、避難民の数は5万人に迫る勢いでした。住民が緊急に支援物資を必要としている状況下で、トラック60台分という枠は十分ではありません。しかも戦闘状況によって、検問所は不定期に閉鎖され、開いているときでも、セキュリティ・チェックその他諸事情によりトラック60台分の貨物がその数字通りに搬入されることはまずありませんでした。
こうした中、2009年2月上旬に日本政府からの支援物資の第一陣のマットレスがガザに到着しました。届いたマットレスは、2月8日に配布されました。配布した場所は、ガザ地区北部のイズベド・アベド・ラッボで、今回の軍事行動で最も被害が大きかった地区の一つです。およそ2000人以上の人々が家を失い、現場は住居の瓦礫の山と化していました。すぐ近くにある工場地帯も破壊され、その被害は現在もそのままの状態が続いています。
現場に並ぶ人々の険しい表情から、今回の戦闘がいかに彼らの生活を破壊し、苦難を強いているかが伺え、安易に声をかけるのがためらわれました。
マットレスや毛布は、日本以外からの支援もありましたが、現場では日本からの物はとくに好評でした。防水シート仕様で、かつ折り畳みが可能なマットレスは、持ち運びには大変便利である、と現場からの声です。毛布も、緊急支援用に生産されたものであることが一目瞭然で、ベージュ色に全て統一されたものは見た目にも暖かそうで質の良さが伺えました。日本政府はこれまで多大な援助をガザ地区で実施してきており、その寛大な支援を人々は記憶しています。この点も、日本からの援助をとくに好意的に受ける結果につながっていたのではないでしょうか。

UNRWAの同僚と(右から2番目が羽隅さん)(写真提供 : 羽隅さん)

イズベド・アベド・ラッボでの支援物資配布の様子(写真提供 : UNRWA)