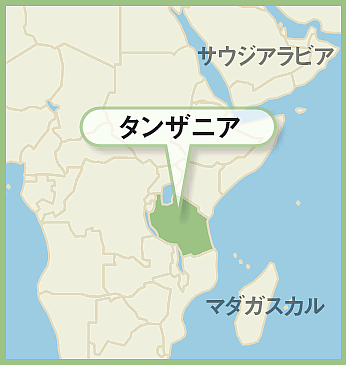コラム 11 タンザニアで親しまれる「日本」~キリマンジャロの麓から広がる稲作支援~
タンザニア北部、キリマンジャロの麓のモシ市の市場では、Japani(スワヒリ語で「日本」の意)という名の米が売られています。日本は、タンザニアの人々に親しまれているこの米の商品化に大きな貢献をしています。
日本は、1970年代からキリマンジャロ州でのかんがい稲作開発に協力してきました。1987年に完成したローアモシかんがい地区(水田面積1,100ha)では、もみの収穫量を1ヘクタール当たり約2トンから6トンに伸ばすなどの成果をあげています。1990年代半ばからは、キリマンジャロ農業技術者訓練センター(KATC)を拠点に、タンザニアや近隣諸国の農業普及員や主要農家約2,000人に、あぜ作り、水田の地ならし、田植え、早めの除草、水管理といった基本的なかんがい稲作技術を指導してきました。そして、2007年から、KATCを含む4つの国内農業研修所と稲研究プログラムを対象に、「かんがい農業技術普及支援体制強化計画(通称:タンライス)」に協力しています。
「タンライス」計画では、1年目にタンザニアの中部、西部、南部農業研修所の職員や主要農家に、かんがい稲作技術の普及方法を教え、2年目には、男女平等の視点も含めた農家の暮らしの改善、かんがい施設を維持するための組織の運営方法、それぞれの水田での稲作技術の指導を行います。こうした協力を2012年までに40か所のかんがい地区で行う予定です。
現在この「タンライス」計画に派遣されている富高元徳(とみたかもとのり)専門家は、これまでも2度(1986~91年、1994~99年)、タンザニアに派遣された経験があります。1987年、農民のムランバさんは乾期の稲作展示のために水田を提供し、他の村人と共に富高さんの指導を受けました。その後、この村や近隣の水回りのよい農地では、年に2回稲が栽培されるようになりました。ムランバさんは、初めて生産した乾期の米を販売したお金で牛を購入しました。ムランバさんは、その牛の写真を当時の研修資料と共に今でも大事に保存しています。2008年に富高さんが再びキリマンジャロ州ムサ・ムウィジャンガ村を訪問した際、約10年ぶりにムランバさんと再会しました。ムランバさんから「あの牛はもういないが、その孫にKumbuka Japani(スワヒリ語で日本の思い出)と名付けた。」と聞き、稲作指導を始めたころを懐かしく思い出したそうです。
富高さんは、「たまに訪れるモシの市場でJapani米を見るたびに、タンザニアの稲作は、多くの課題や問題に直面しながらも、着実に発展しつつあることが分かります。」と言います。「タンライス」計画では、ネリカ米*1を含む新たな米の品種の可能性が具体化されるよう、稲研究プログラムも支援しています。こうしたタンザニアでの稲作支援の成果は、日本が2008年5月の第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)で発表したサハラ以南のアフリカのコメ生産を向こう10年間で倍増するという取組に大きく貢献するものと期待されています。
*1 : NERICA:New Rice for Africa(収穫量の多いアジア稲と病気等に強いアフリカ稲を交配した米)

研修農場での富高さん(右端)(写真提供 : 富高さん)

Kumbuka Japaniとムランバさん(写真提供 : 富高さん)