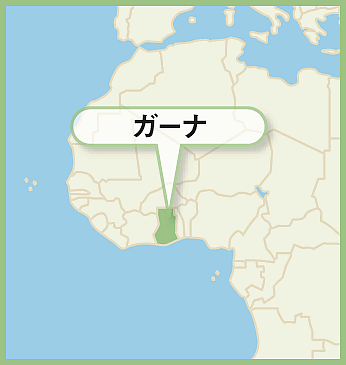コラム 4 いつも安全な水を~ガーナ帰国研修員の活躍~
「自分はエンジニアなので、横浜の海沿いに立つ高層ビルにはとても驚きました。是非、また日本を訪れてみたいですね。」横浜市での研修生活について尋ねると、オセイ・エーガンさんは笑顔でこう答えてくれました。エーガンさんは、2009年1月に横浜市水道局で実施された「都市上水道技術者養成」研修を受講し、その後ガーナに帰国して活躍する元研修員の1人です。
今回の研修は2008年5月に横浜で開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)が端緒となり、国際協力機構(JICA)と横浜市の協力によるアフリカ諸国への技術支援の一環として実施されました。8か国から計13名(ガーナからはエーガンさんをはじめとして計4名)の研修員が、浄水処理技術、配水管理、料金徴収の方法などについて横浜市の事例などを通じて学びました。現在、エーガンさんは給水事業を行うガーナ・ウォーター社(Ghana Water Company Ltd.)において、水道関連の機材の導入やメンテナンスなどを行うセクションリーダーとして、研修で得た知識を生かしながら指導にあたっています。
エーガンさんによると、首都アクラを中心としたガーナの都市部では水道インフラが十分に整備されておらず、一般家庭に水を届けるまでに水道管の破損や盗水などによって約半分が失われてしまい、得られる収入が半減してしまっているとのことです。また、アフリカ諸国特有の問題として、乾季になると貯水湖の水量が著しく減少し、緑藻が発生してしまうために水質も悪化してしまうそうです。その水質の改善のためにさらに多くの薬剤を投入する必要があり、コストも高くなってしまいます。
「日本の方々は聞いていた通りに勤勉で、そして親切でした。」と日本人の印象を語るエーガンさんですが、研修当初は言葉も通じない環境でとても苦労したそうです。「横浜市の職員の方が通訳をして下さるなど本当にいろいろと助けていただきました。休日も神社に連れて行って下さったおかげで、多くの日本の文化にも触れることができました。でも緑茶は思っていたより苦かったですね。」とエーガンさんは滞在中の思い出を振り返りながら語ってくれました。また、「水」に対する両国民の意識の違いについても、「ガーナでは水源のとなりにゴミを捨ててしまう人が多くいますが、日本では周辺住民が木を植えるなど、水源の保護に熱心なことにとても感動しました。」と、エーガンさんは同僚にもこの話をよく聞かせているそうです。
国連のミレニアム開発目標(MDGs)の中に、「安全な飲料水および基本的な衛生施設を継続的に利用できない人の割合を2015年までに半減する」と掲げられているように、安全な水へのアクセスはアフリカ諸国のみならず深刻な問題といえます。ガーナにおいても、安全な水にアクセスできず溜め池などの水を飲料水として使ってしまうために感染症などに罹る人々が依然として多くいます。将来的な安全かつ安定した給水システムの確立のために、研修で得た知識と技術を生かしつつエーガンさんのような帰国研修員の方たちの更なる活躍が期待されます。

横浜水道記念館を視察する研修員(写真提供 : JICA)

漏水探知機による調査実習(写真提供 : JICA)