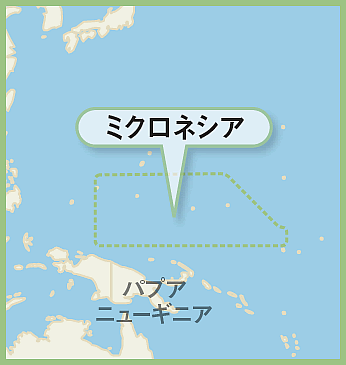コラム 3 安心して使えるトイレを~ミクロネシアの衛生改善プロジェクト~
太平洋に浮かぶ小さな島々から成るミクロネシア連邦は、1914年から1945年までの31年間、当時の日本の南洋庁による国際連盟委任統治下にあったという歴史があります。
「たくさんの日本語が現地語となって日常で使われています。たとえば今や世界の合言葉になっている“モッタイナイ”などです。また水洗式トイレは“トイレ”ですが、昔ながらのトイレは“ベンジョ”と呼ばれています。」と青年海外協力隊員の丹羽健治(にわけんじ)さんは言います。丹羽さんは2007年から2009年までポンペイ州環境保護局に派遣されていました。自然保護、環境意識の向上などの環境プログラムの企画立案および実施、環境教育教材の作成などの活動を通じて、現地の仲間達と共に試行錯誤しながらポンペイ州の環境問題に取り組みました。
その中の取組の一つにトイレの改善があります。ミクロネシアの一般的なトイレは、地面に縦穴を掘り、トタンの屋根と囲いがあるだけで、その衛生状態は必ずしも良いものではありませんでした。
2007年の「国連ミレニアム開発目標報告書」によると、ミクロネシアの人口の75%は衛生的なトイレを利用していません。このような状況は人々に病気をまん延させ、子どもたちの健康を日々脅かしています。世界では毎日約4,500人の子どもたちがコレラ、腸チフス、下痢などの汚水に関連した病気で死亡しており、トイレや下水処理などの衛生分野における世界規模の取組が求められています。2008年には国連で日本が提出した「国際衛生年」の決議案が採択されました。日本は地球規模の課題である水と衛生問題の解決に向け積極的な協力を行っています。
このような動きを受け、ミクロネシアでは日本大使館の呼びかけに応じて、丹羽さんとポンペイ州環境保護局が現地の衛生分野のニーズを汲み取り、草の根・人間の安全保障無償資金協力との連携によるプロジェクト「ポンペイ州学校衛生設備改善計画」が始まりました。調査を始めてみるとトイレの問題は子どもたちの健康だけではなく、現地の人々の生活に欠かすことの出来ない地下水の汚染による周辺の生態系などの環境にも大きな影響をもたらしていました。多くの学校のトイレ設備は生徒数に対して絶対数が不足している上、男女共用でした。衛生面は劣悪で、トイレを使いたがらない子どもたちも多く、さらには順番待ちでのけんかも度々ありました。このような状態で、特に女子生徒には使いにくいものとなっていました。このため、特に学校生活には欠かすことのできない基本的インフラ整備としてトイレ・プロジェクトを企画しました。企画の過程では、コミュニティや教育関係者、生徒を対象に、インタビューや話し合いの場を設け、住民、特に女性のニーズに応えられるように努めました。トイレが完成した今、ある女子生徒は「以前は男子と一緒だから入りにくかったけど今は安心して使える。」と言います。
こうした草の根の取組が、島嶼(とうしょ)国を脅かす水と衛生問題、住民たちのジェンダーに関する意識の改善につながることが期待されています。

現場での打ち合わせ

ポンペイ州環境保護局のスタッフと(左端が丹羽さん)