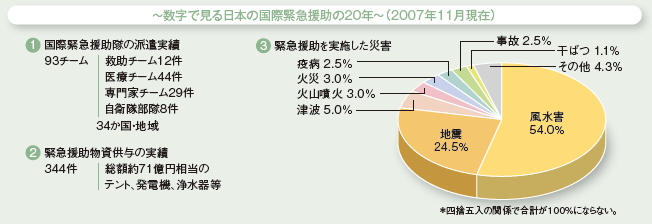 |
国際緊急援助隊(JDR(注))は、1987年9月に「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」(以下、派遣法)が施行されて以来、2007年で20周年を迎えます。国際緊急援助隊は被災地で救助活動、医療活動および災害応急対策や災害復旧のための活動を行っており、時には埃まみれになり、額に汗を流して日本独自のきめ細かな被災者支援を実施しています。同法の施行以来、日本は海外における大規模災害に対し、国際緊急援助隊93チーム(2007年11月現在)を派遣しました。
ひとたび大規模な災害が発生すれば、被災国では多くの住民が死傷し、水、食料、電気といったライフラインに大きな影響を与える等、独力ではどうにもならない状況に陥ることが多くあります。国際緊急援助隊には一人でも多くの被災者に迅速に救いの手を差し伸べることが求められています。発災後72時間を経過すると生存者救出の可能性が著しく低下するといわれているため、日本は被災国政府からの要請があれば、救助チームは24時間以内、医療チームは48時間以内に現地に向かえる体制を整えています。また、地震や台風などの自然災害の多い日本は、これまで災害救助に対する豊富な知識や技術を蓄積しています。
このような迅速性と知見を有する日本の国際緊急援助隊は、これまでにも海外の多くの被災者の悲しみを和らげ、希望の光を与えてきました。例えば、2003年5月に発生したアルジェリア大地震に派遣された救助チームは、被災者がいれば、どんな形であれ救出するとの信念の下、疲労に襲われながらも不眠不休で活動を行いました。発災後50時間以上が経過し、活動を中止する海外チームもある中、ある隊員が倒壊したホテルの瓦礫の下からかすかな声が聞こえてくることに気付きました。ともすれば見逃してしまいそうなほどかすかな声でしたが、生存者の可能性を信じ念入りに付近を捜索したところ、瓦礫に埋まっている男性を発見しました。現場近くで活動していたトルコ・チームと協力し、生存者を励ましながら丁寧に作業を進めた結果、男性の救出に成功しました。その瞬間、両国の隊員のみならず、ホテル関係者や多くの住民から大きな歓声と拍手が沸き起こりました。一つ一つ丁寧かつ慎重に取り組む日本ならではの緻密な行動が功を奏し、生存者の救出につながりました。
また、2001年1月のエルサルバドル地震に派遣された医療チームでは、災害による外傷を手当てするだけではなく、訪れる患者の苦労話を真摯に聞いたり、限られた薬品や資機材の中でできる限り患者を助けようとするなど日本人ならではの丁寧な対応を行いました。患者の中には決して裕福な生活を送っているとは思えない子どもたちも大勢いましたが、ある日、一人の子どもが隊員に飴を差し出しました。彼らにとって飴は非常に貴重なものですが、それは子どもながらに日本の医療チームに感謝の気持ちを伝えようとしての行動でした。それから約1年後、追跡調査のため現地を訪れた調査員は、地元病院の院長から医療チームの懇切丁寧な診療が患者の信頼と好評を得たとして、撤収した後も患者から「日本のドクターはいないのか」と何度も聞かれたと話していました。
1995年1月、日本は阪神・淡路大震災を経験しました。その際、77の国・地域・国際機関から援助の申し出があり、その中には経済的に必ずしも豊かとはいえない国が含まれていたことは意外と知られていません。「国」と「国」との関係も突き詰めれば「人」と「人」との関係と何ら変わるものではありません。大規模災害が発生し、被災国が本当に困っているときにこそ、国の規模や経済力などを超えた人道的見地から救いの手を差し伸べること、これこそが真に求められています。派遣法施行から早20年。国際緊急援助隊は、これまでも、そしてこれからも初心を忘れず被災者救済のため世界各国で活動を続けていきます。
注 : JDR : Japan Disaster Relief Team
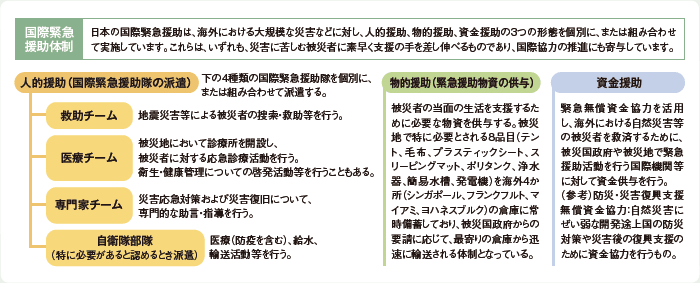 |
●浅井康文先生 札幌医科大学附属病院高度救命救急センター教授(スマトラ沖大地震・インド洋津波・2004年12月派遣)
私の国際緊急援助隊医療チームでの経験の中で、2004年12月のスマトラ沖大地震・インド洋津波の経験は衝撃的でした。医療チーム副団長としてインドネシアのバンダ・アチェに赴きましたが、歩道には多数の遺体袋に包まれた死体が置かれている等壊滅的な被災地の状況は目を覆うばかりであり、また、独立運動が盛んな地域で安全確保に神経を遣う活動でした。診療活動は、外傷等に対する診療だけではなく、被災者の心のケアや遠隔地への巡回診療にまで及び、極度の緊張が続き休む間もありませんでした。医療チームの中心は私も含め医療関係者のボランティアですが、こうした海外での緊急医療活動を行うことができるのも、職場や家族の理解を含む国内での強い支援の賜です。ひるがえって、医療チーム参加者は、日本では災害医療派遣チーム(DMAT(注))の中核としても活躍しており、海外で培った経験が国内での被災者支援にもいかされています。
 |
●佐藤邦彦さん 警視庁警備部災害対策課機動救助係 警視庁警部補(パキスタン等大地震災害・2005年10月派遣)
「娘が埋もれているんだ。助けてほしい」原形をとどめないほど崩壊したパキスタン北部の村落で、スコップを手にした父親から悲痛な訴えを受けました。その土砂の下に間違いないという父親の言葉を頼りに、私は小隊員を指揮して捜索活動を実施しましたが、残念ながら冷たくなった体での収容となってしまいました。しかし、父親から「日本の援助隊に心から感謝する」との涙ながらの謝辞をいただいたことは生涯忘れることはないでしょう。緊急援助隊員という形で国際貢献に従事させていただき、警察官としても世のため人のために奉仕するという精神は国の内外を問わないものであると実感しました。 今、私は首都東京の災害対策を担当する部署にいますが、これらのパキスタン派遣で得た経験を語り継ぎながら、若い救助隊員の育成に当たっています。
 |
●阿部聡さん 東京消防庁 牛込消防署 消防司令補(派遣当時は、第八消防方面本部消防救助機動部隊 隊長)
(スマトラ沖大地震・インド洋津波・2004年12月派遣、パキスタン等大地震災害・2005年10月派遣)
スマトラ沖大地震およびパキスタン等大地震の災害に、当時、消防救助機動部隊の救急救命士として国際緊急援助活動を行いました。派遣されたタイ国では、日本人で亡くなった方が多く、同じ飛行機に遺族の方も搭乗し、重い空気の中、成田空港を飛び立ったのを思い出します。現地の活動は、高温多湿の中、過酷な活動を強いられましたが、皆が一丸となって救助活動に取り組みました。津波の恐ろしさをまざまざと実感しました。また、パキスタン等大地震では、現地の山奥で野営をしながら、情報収集や探索活動を行いました。機動部隊での訓練は、座屈したビルを想定し、倒壊した建物の狭い入口からの救助活動を行っていますが、それが今回の活動に大いに役立ちました。また、医師と消防隊の連携訓練も、救助活動と並行しての救急活動等にいかされました。派遣によって現地の人々の力になれたことは、私の励みになっています。
 |
●一宮剛さん 海上保安庁 羽田特殊救難基地 第五特殊救難隊 隊長(パキスタン等大地震災害・2005年10月派遣)
派遣中、私は隊員兼通訳として住民からの生存者情報の収集に当たりました。その中で、ある若者から「家族が埋まっている。そこから臭いがしている。助けてほしい」と言われました。しかし「我々は一刻も早く多くの生存者を助けたい。本当に申し訳ないが、生存者を優先させてくれ」と必死に伝えました。若者が必死の形相でしたので、探してあげたかったのですが、そういう申し出が多数あったので、何とか説得して分かってもらいました。若者は、「頑張ってくれ!」と声をかけてくれましたが、その涙をこらえた表情は、今も忘れることができません。その後、日本チームは瓦礫の中から3名を救出しましたが、残念ながら既に亡くなられていました。この悔しさを心に持ち、今後大災害が起きた際には、一刻も早く現地に駆けつけ、一人でも多くの生存者を助けたいと思います。
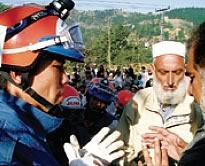 |
注 : DMAT : Disaster Medical Assistance Team