近年、ミレニアム開発目標(MDGs)等の国際的な開発目標が共有され、関係国の援助協調の下に様々な取組が進められていますが、これらの目標を達成するためには援助の額を増加するとともに、質の向上も不可欠となっています。その中で、援助の質の改善を目指し、援助が最大限に効果を上げるために必要な措置について、援助国と被援助国双方の取組事項をとりまとめたものがパリ宣言です。パリ宣言は、2005年3月にパリで開催された第2回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラムで採択されました。なお、同宣言には現在、111か国(援助国および被援助国を含む)、26国際機関、14民間団体が参加し、良い援助を実施するための規範として広く認知され、OECD-DAC(経済協力開発機構の開発援助委員会)を中心に実施が促進されています。
パリ宣言には、以下の項目が記載されています。
(1) 援助効果向上の5原則
<1>自助努力(Ownership)
被援助国は、開発戦略の策定と実施についてリーダーシップを発揮し、援助国・機関等はそれを支援する。
<2>制度、政策への協調(Alignment)
援助国・機関等による支援は、被援助国の開発戦略に沿って、可能な限り被援助国の財政・調達等の制度と手続きを利用して行う。
<3>援助の調和化(Harmonization)
援助国・機関等は、可能な限り援助の計画、実施、評価、報告等に関する制度・手続きを共通化する。
<4>開発成果管理
被援助国の開発計画、予算措置、評価等の援助実施・管理に関連する制度を強化し、相互の連関性を強めることにより、開発の成果を高める。
<5>相互説明責任
援助国・機関等と被援助国は、援助資金や手続き、開発成果等に関して透明性を高め、相互に説明責任を果たす。
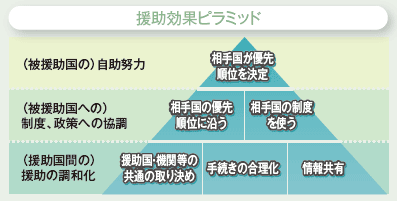 |
(2) 56の取組事項
5原則を具体的に実施し、援助の効果を向上するために援助国・機関等と被援助国のそれぞれが取り組むべき具体的な行動について、56の取組事項がとりまとめられています。
(3) 12のモニタリング指標
被援助国の国家計画に沿ってプログラム化された援助の割合、被援助国の公共財政管理・調達システムを利用した援助の割合、アンタイド率、複数の援助国・機関等が共同実施する調査・分析作業の割合等、12の指標を設定し、モニタリングを行うこととされています。
(1)パリ・ハイレベル・フォーラムでパリ宣言に参加するとともに、独自に「援助効果向上に関する我が国の行動計画」を発表しました。その後、毎年、同行動計画の進ちょくをOECD-DACに報告しています。
(2)援助国として、アジアを中心にパリ宣言の普及・実施促進に貢献しています。2006年10月には、英国国際開発省、アジア開発銀行、世界銀行と共催で援助効果向上に関するアジア地域フォーラムを開催しました。アジアにおける調和化や被援助国の制度政策への協調に関する取組の好事例に関して情報共有が行われるとともに、援助の効果を向上するため、自助努力の重要性、被援助国の能力強化のための技術協力の質の向上等が話し合われました。
(3)2008年には、ガーナにおいて第3回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラムが開催される予定です。日本は、主要援助国として同会合の運営委員会に入っており、これまでの日本の援助の経験、成功事例を援助効果向上の議論に反映するため、会合の実施準備において主導的な役割を果たしています。特に、新興援助国の援助効果向上、能力開発、社会・経済基盤(インフラ)整備分野における援助効果向上の3つの議題を重視しています。
(1)パリ宣言では、1996年に日本の主導で提唱した、OECD-DACの新開発戦略からの流れをくむ自助努力の原則や成果重視の考え方が5原則に取り入れられるなど、基本的な考え方には日本の援助理念が反映されています。
(2)日本の限られた政府開発援助予算を有効活用し、援助の成果を向上していくためには、日本と被援助国が共同で援助効果向上のための努力を行う必要があり、そのためにはパリ宣言は有効な枠組みの一つです。