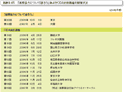日本の外交において大きな役割を担う開発途上国への開発援助を進めていくに際して国民からの理解と支持を得ることは不可欠であり、そのために政府としても国際協力に関する情報の一層の公開に取り組んでいます。
国際協力に関する情報提供および日本の協力案件に接する機会を提供するための具体的な施策としては、この白書や外交青書をはじめとする政府刊行物の発行以外にも、以下のような取組があります。
● ホームページ・メールマガジン・新聞
関連のホームページにおいて情報公開の充実化を図っており、外務省、JICA、JBIC、国際協力プラザなどのホームページでは、国際協力に関する多くの情報をタイムリーに掲載するとともに、各ホームページ(注23)とも国際協力について分かりやすく紹介しています。
外務省は、ホームページに加え、メールマガジンも発行しています。2007年3月22日現在で第111号まで発行され、この中では、経済協力にかかわる時宜を得た話題や情報を提供しているほか、在外にある日本大使館の館員や、青年海外協力隊員、シニア海外ボランティアなどが、実際の援助の現場で体験した話や援助にまつわるエピソードなどを紹介しています。なお、メールマガジンはホームページを通じて随時登録を受け付けており、2007年3月末現在で約1万4,100名の方が登録されています。
また、国際協力に関する最新情報を掲載する「国際協力新聞」を毎月発行し、全国の教育機関、図書館等に配布しています。
● 市民との対話
「国際協力について語ろう」は、国際協力に関する市民対話の一環として、政府開発援助(ODA)改革を巡る動きなどを一般市民に紹介するとともに、国民の生の声を直接聴取することを目的に、日本全国各地で開催されています。2007年2月までに33回開催され、有識者や外務省の省員と一般市民との間で忌たんのない意見交換を行っています。
また、より機動的な市民対話の一環として2005年10月からは、外務省経済協力局(当時)(注24)の職員が中学、高校、大学、大学院、地方自治体(国際交流協会)、NGOなどに赴いて、国際協力について説明をする「ODA出前講座」を開始し、2007年3月までに19回開催されました。
図表II-45 「国際協力について語ろう」およびODA出前講座の開催状況
● ODA民間モニターの派遣
ODA民間モニター事業は、国際協力に関心を有する一般国民が実際の援助の現場に赴き日本の政府開発援助案件を直接視察することにより、国際協力の意義・重要性について正しく理解するとともに、意見や感想などを提言するものです。この事業は、1999年度から開始され、2007年度までに704名がアジア、アフリカ、中南米など28か国の開発途上国のプロジェクトなど479件を視察しました。参加者からは、政府開発援助が開発途上国の発展・安定に役立っていることや援助の必要性について理解を深めたなどといった報告がなされています(注25)。また、モニターへの参加をきっかけとして、国際協力に関心を深め、青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして国際協力に参加することとなった方もいます。これからも、こうした事業を通じて、国際協力に対する国民の理解が一層進んでいくことを期待しています。
● 国内広報テレビ番組
開発途上国の現状、援助の必要性、プロジェクトに参画・利益を受けている住民および日本人の姿を映像にし、日本の国際協力が開発途上国においてどのように評価され、また役立っているかをより多くの一般国民に紹介し、国際協力に対する関心を高め、理解を深めてもらうため、シリーズもののレギュラー番組を1997年度から制作・放映してきています。2006年度は、テレビ東京で毎週1回4分間の番組「関口知宏の地球サポーター」を、ラオス、イラク、タンザニア、エルサルバドル、モンゴル、パキスタン、トルコについて放映し、平均視聴率は5.3%に上りました。また、国民の方々の全国放送への強い希望から、BSで総集編を放送しました。そして2007年度も引き続き、「関口知宏の地球サポーター」を放映しています。
● グローバルフェスタJAPAN
1990年から日本国内最大の国際協力イベントとして「国際協力フェスティバル」を毎年「国際協力の日」(10月6日)(注26)にあわせて開催してきましたが、若い世代や国際協力になじみの薄い層にも広く参加してもらうため、2005年に名前を「グローバルフェスタJAPAN」に変更しました。外務省、JICA、JBICおよび国際協力NGOセンター(JANIC)が共催し、東京・日比谷公園で土・日の2日間にわたって行われるグローバルフェスタJAPANには、政府、NGO、国際機関、各国大使館など200を超える団体が出展します。会場では来場者に国際協力をより身近なものに感じてもらい、政府開発援助(ODA)を含む国際協力の現状や必要性、政府とNGOの協力などについて理解が進むよう、各出展団体のテントでの紹介のほか、ダンスや音楽、クイズ大会、チャリティーラン、各種ワークショップなど、楽しく親しみやすいイベントが多数行われました。
グローバルフェスタJAPANでは、毎年、統一テーマを設定しています。2006年は『「食」から考える・地球しあわせ計画』をテーマとし、途上国の食糧事情、日本の食糧支援、各国の食文化、食の安全性など、身近な関心事である「食」を通して、国際協力、途上国への理解促進を図りました。2007年10月6日・7日に行われた「グローバルフェスタJAPAN2007」は、私たちの生活の中心である家族、家庭から、私たちの周りの地域、環境、世界とのきずなやつながりを考えてもらい、国際協力や途上国への理解促進を図ることを目指して「家族と地球」をテーマにして行われ、2日間で約8万人の来場者がありました。また、初めての試みとして民間企業の協賛を得て、企業のブース展示やアトラクションを通じ、日本の国際協力が政府、国際機関、NGOのみならず、幅広く民間企業の活動に支えられていることも来場者に紹介しました。さらに、外務省は、紺野美沙子国連開発計画(UNDP)親善大使ほかを迎えて、パネルディスカッション「国際協力について語ろう」や、ミニシンポジウム「国際協力におけるNGOとの連携」のほか、外務省のテントでは、自分の身近なところで途上国のためにできることを宣言し、実践につなげる試みとして、来場者に「私の国際協力宣言」をしていただきました。また、関口知宏さんや眞鍋かをりさんの国際協力に関するトークショーも行われました。このようなイベントを通じて、一人でも多くの方が国際協力への理解を深め、国際協力に参加するようになることが期待されます。
 |
「グローバルフェスタJAPAN2007」に参加いただいた眞鍋かをりさんにお話を伺いました。
■これまで国際協力に関するご経験がないとお聞きしました。
「国際協力というと、大学の友人でかかわっている人もいましたが、自分を含めた一般の人にとっては、少し遠い世界の話だと思っていました」
■現在、アフリカへの協力について、日本を含めた国際社会で取組を強化しています。
「インターネットを通じて、フェアトレード商品を購入したりしているので、アフリカに対して、あまり遠いところという印象はありません」
■というと、実はもう国際協力に参加されていらっしゃったんですね。
「そうですね(笑)。今後は、環境に配慮した日用品や、フェアトレード商品を意識的に買うなど、直接自分で身近に実践できる協力を行っていくことに加えて、活動を学んで伝えていく役割もしていきたいと思っています」
 |
日本国内における広報に限らず、政府開発援助を通じた日本の積極的な国際貢献については海外においても正しく認知され、評価されることが重要です。
日本は従来、海外において日本の援助が正しく評価され、個々の案件が日本の援助によるものであることを周知すべく、署名式や引渡式に際してプレスリリースを発出するなど現地プレスの取材に協力したり、日本の援助物資に日章旗ステッカー(英語、アラビア語)やODAシンボルマーク・ステッカー(英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ポルトガル語、中国語)を貼付したり、看板を設置するなどしています。
また、当該国に対する日本の援助政策やその成果について広く相手国国民に知ってもらうため、当該国向けに広報テレビ番組を放映しています。2006年度は、ネパール、ブルガリア、エルサルバドル、モンゴルで放映しました。また、在外にある日本大使館は現地プレスに対して日本の援助現場視察をアレンジし、現地のメディアでも日本の協力案件がとりあげられるような機会づくりに努めています。さらに、在外公館が各種講演活動や英語・現地語によるホームページ・メールマガジンなどによる発信を行ったり、現地のJICA、JBICなどとも協力しつつ、日本の国際協力に関する様々な広報資料パンフレットを作成・配布しています。他の援助国・機関を含む国際社会に対しても、日常の外交努力や国際会議における情報発信のほか、各種のシンポジウムやセミナーの開催やホームページを通じた情報発信に積極的に取り組んでいます。