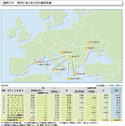日本の欧州に対する2006年の二国間政府開発援助は、約2億2,005万ドルで、二国間援助全体に占める割合は2.9%です。
バルトおよび中・東欧諸国は、旧社会主義体制を脱し、市場経済化・民主化に向けた取組を進めており、日本は各国に支援を実施してきています。これらの諸国の中でも発展の度合いは地域によって大きく異なっており、バルト三国を含む8か国(ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、ラトビア、リトアニア、エストニア)は、各国からの支援を得つつ積極的な国内改革を推し進めた結果、2004年5月に、ルーマニアおよびブルガリアは2007年1月に、欧州連合(EU)加盟を果たしました。日本も継続的かつ多岐にわたる支援を行うことによって、体制移行に伴う経済的・社会的困難を経験した市民の生活を改善し、安定的な体制転換に協力してきました。EU加盟国は、政府開発援助対象国から外れることとなり、欧州地域に対する支援環境も変化してきています。
バルトおよび中・東欧諸国の発展に伴い、日本の支援の役割も変化してきています。こうした中、より需要の高い地域や分野に援助を移していく必要があり、欧州地域における援助重点国についても、1990年代の旧ユーゴスラビア紛争の影響で経済状態が悪化した西バルカン地域やウクライナ、モルドバなどの更に開発の遅れた国々に援助の重点を移しつつあります。
● 新規EU加盟国への支援
新規EU加盟国に対しては、国ごとの経済発展の段階にあわせて政府開発援助による支援を段階的に縮小していき、より経済発展の進んでいる国に対しては、政府開発援助卒業後を見据え、二国間協力の在り方について模索していく必要があります。具体的には、今まで行われてきた政府開発援助の成果を民間企業や大学等研究機関間の協力に結びつけることなどです。また、被援助国から援助国へと転換しつつある国に対しては、日本の援助国としての経験を共有する等の協力をしていく考えです。さらに、これらの国々とともに、周辺地域におけるより発展段階の低い国に対して、共同で支援する三角協力を進めています。これにより、被援助国の開発が促進されるのみならず、三角協力の相手国にも援助国としての経験が蓄積されるという効果があります。
● 西バルカン地域等への支援
旧ユーゴスラビア紛争によって大きな被害を受けた西バルカン地域では、復旧・復興段階を脱して将来のEU加盟を目指しつつ、開発段階へと移行しています。同地域に対しては、紛争により破壊されたインフラの整備や、保健・医療分野に重点を置いた支援を従来行ってきましたが、近年その発展の段階にあわせ、市場経済化に資する支援として投資促進のための専門家の派遣や中小企業振興や貿易促進のための研修などの協力も進めています。さらに、平和の定着の観点から、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、民族融和のための支援や難民・帰還民等の社会弱者への支援を行ったりしています。バルカン地域共通の課題である環境分野については、専門家の派遣や研修等の支援を行っているほか、マケドニアおよびアルバニアにおいては、土壌汚染や下水汚染を改善するための開発調査による協力を行いました。
旧ソ連欧州部にあるウクライナでは、2004年12月にユーシチェンコ政権が成立し、民主化が進展する中、2005年7月に同大統領が訪日し、さらに2006年7月には麻生太郎外務大臣(当時)がウクライナを訪問するなど、日本との二国間関係がより深まっています。こうした動きを受けて、日本も国際社会と協調しつつ、ウクライナの一層の民主化、市場経済化に向けた努力を支援しています。
また、欧州地域で最も発展が遅れているモルドバに対しては、同国の主要産業である農業分野に対して、これまで貧困農民への支援として農業機械・肥料の供与を行っており、同国の農業自給率に大きく貢献しています。