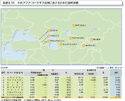日本の中央アジア・コーカサス地域に対する2006年の二国間政府開発援助は、約9,275万ドルで、二国間援助全体に占める割合は1.2%です。
図表II-34 中央アジア・コーカサス地域における日本の援助実績
中央アジアおよびコーカサス地域は、ソ連崩壊後の新たな国際情勢の下、ロシア、中国、南アジア、中東に隣接するという地政学上の要衝にあり、石油、天然ガス、ウラン、レアメタル等の資源を産出することから、日本にとって、資源・エネルギー外交上非常に重要な地域です。日本はこうした重要性を考慮し、日本の外交の地域的な幅を広げることも念頭に置き、同地域において普遍的価値(人権、民主主義、市場経済、法の支配)を共有できる体制を築いていくことが、同地域の長期的安定および持続的発展にとって重要だと認識しています。
● 中央アジア地域
計画経済体制から市場経済体制への移行を支援するために、法の支配確立のための法制度整備、市場経済化のための人材育成、経済発展のためのインフラ整備などを中心とした援助を行っています。特に、人材育成や制度づくりといったソフト面での協力は重要です。日本は、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスにおいて人づくり支援の拠点として「日本人材開発センター(日本センター)」を開設しており、日本から専門家を派遣し、日本の経験に基づくビジネスコースや日本語コースの実施を通じた日本の経験の共有を図るなど、同地域の市場経済化に対応する人材育成に貢献しています。またウズベキスタン、キルギスから若手行政官を中心とした将来の国づくりを担いゆく留学生を日本の費用負担により受け入れているほか、キルギスではIT技術者育成のための技術協力も行っています。また、法制度整備支援に関しては、ウズベキスタンにおいて、倒産法注釈および企業活動発展のための民事法令および行政法令の改善などの技術協力を実施中です。インフラ整備に関しては、これまで道路、空港、鉄道の整備などを行ってきましたが、中央アジアとその南方の地域を広域的にとらえた地域協力の促進の観点から、中央アジアからアフガニスタン経由でアラビア海へつながる道、いわゆる「南方ルート」に係るインフラ整備を重視し、2006年度は、タジキスタンにおいて、アフガニスタンへつながる道路の整備を支援しています。
● コーカサス地域
カスピ海のアゼルバイジャン沿岸には、未開発のものとしては世界最大級の油田があり、同油田から地中海に抜ける石油パイプラインのルート上に南コーカサス地域があることから、同地域の安定的な経済発展は国際的なエネルギー安全確保のためにも重要です。エネルギー分野については、2005年3月(アルメニア)および同年5月(アゼルバイジャン)に火力発電所を建設するための円借款による協力を行い、今後予想される深刻な電力需給不足の緩和のために支援しています。他方、2003年の「バラ革命」により民主化が進展したグルジアに対しては、グルジア支援国会合(2004年6月、於:ブラッセル)において同国を引き続き支援することを表明し、2006年3月には経済構造改善のために資金供与による支援を行いました。また、コーカサス地域は、所得向上のための雇用創設および公共サービスの改善が共通の課題となっており、中小企業振興、保健・医療および水分野に対して専門家の派遣や研修等を通じた支援を行っています。
2006年6月、日本と中央アジア諸国は、双方間の対話と協力の枠組みである「中央アジア+日本」対話の第2回外相会合を東京で開催し、5つの協力の柱((1)政治対話、(2)地域内協力(テロ・麻薬対策、環境保護、エネルギー/水、輸送、貿易・投資など)、(3)ビジネス振興、(4)知的対話、(5)文化交流・人的交流(観光を含む))を確認しつつ「行動計画」を採択し、同5分野を柱として協力を進めること、特に地域内協力を促進する種々の案件に政府開発援助を活用しつつ取り組んでいくことで意見の一致を見ました。また、2006年8月、小泉純一郎総理大臣(当時)は、日本の現職総理大臣として初めて中央アジアのカザフスタンおよびウズベキスタンを訪問し、同地域に対する日本の積極的な関与の姿勢を改めて内外に示しました。
 |