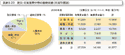2006年度の防災・災害復興分野の資金協力の実績は約909億円で、無償資金協力約162億円(43か国)、円借款約677億円(6か国)、国際機関への拠出約29億円となっています。このうち、二国間資金協力を災害形態別で見ると、地震・津波関係の割合が17%、暴風・洪水13%、土壌流出58%となっています。地域別では、アジアの割合が86%と最も高く、次いでアフリカ7%、中東5%となっています。ソフト面の取組としては、防災分野で31名の専門家派遣、408名の研修員受入、34件の技術協力プロジェクト等を行いました。また、国際緊急援助の実績としては、国際緊急援助隊の派遣が3件、緊急援助物資供与で15件総額約2億円相当の支援を行いました。
地震、火山噴火、津波、暴風、豪雨、洪水、土砂災害、干ばつなどの災害は世界各国に様々な形で毎年のように発生しています。大規模な災害では、多くの人命や財産が奪われるだけでなく、経済や社会システム全体が長期にわたって深刻な影響を受けることがあります。特に、開発途上国の多くは災害に対してぜい弱であり、極めて深刻な被害を受けます。また、一般に貧困層が大きな被害を受けて災害難民となることが多く、衛生状態の悪化や食料不足などの二次的被害が長期化することが大きな問題となっています。
日本は、自らの過去の災害経験から培われた優れた知識や技術に基づき、緊急支援と並んで災害予防および災害復旧分野の重要性を強く認識して、積極的な国際協力を行っています。特に、2005年1月に神戸で開催された国連防災世界会議において、今後10年の国際社会における防災活動の基本的な指針となる「兵庫行動枠組2005-2015」が採択され、日本は国連と協力してその世界的な実施を推進しています。同会議において、日本は政府開発援助による防災協力の基本方針等を「防災協力イニシアティブ」として発表し、制度構築、人づくり、経済社会基盤整備などを通じて、開発途上国における「災害に強い社会づくり」への自助努力を引き続き積極的に支援していくことを表明しました。また、2005年4月にインドネシアで開催されたアジア・アフリカ首脳会議においては、防災・災害復興対策のためにアジア・アフリカ地域を中心として今後5年間で25億ドル以上の支援を行うことを表明し、日本の役割に対する国際社会の期待はますます高まっています。2006年度には、「防災・災害復興支援無償資金協力」を創設し、防災・災害復興支援を強化することとし、インドネシア(注151)およびグアテマラ(注152)に対して実施決定しています。
このほかにも、2007年2月には無償資金協力により、バングラデシュの気象観測の要衝であるコックスバザールにおいて、気象レーダーの整備を行いました。これにより、降雨の探知範囲が拡大するとともに、レーダー稼働率が向上し、バングラデシュ気象局におけるサイクロンの監視能力が向上しました。
インドネシアは、2004年12月にスマトラ沖大地震・津波災害に見舞われましたが、2006年には5月のジャワ島中部地震、7月のジャワ島南西沖地震・津波災害をはじめ、洪水・土砂災害等立て続けに深刻な被害を受けました。日本はこれらの被害に対し、緊急援助物資の供与をはじめとする各種支援を実施しました。具体的には、5月のジャワ島中部地震については、国際緊急援助隊(医療チーム、自衛隊部隊)を派遣したほか、テント、浄水器、発電機など約2,000万円相当の緊急援助物資を供与しました。また、インドネシア政府に対して400万ドルの緊急無償資金協力を実施し、これに加え国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC (注153))を通じて100万ドルの緊急無償資金協力を行いました。7月のジャワ島南西沖地震・津波災害については、テント・簡易水槽など約1,300万円相当の緊急援助物資を供与しました。このほか洪水、土砂災害被害に対しては、1月および6月にそれぞれ約1,300万円相当および約1,200万円相当の、2007年2月には約1,500万円相当の緊急援助物資の供与を行いました。現在では復旧・復興の段階に入っており、防災・災害復興支援無償や円借款によるインフラの復旧、技術協力による復興計画支援や被災者の心のケアなどを実施しています。
また、災害が多発するインドネシアとの間において、2005年6月の両国首脳間合意に基づき、両国の防災担当の大臣を共同議長とする「防災に関する共同委員会」が設置され、2006年7月、インドネシアにおける包括的かつ効果的な災害対策に向けた指針となる報告書がとりまとめられました。本報告書で示された災害対策の重要性、課題等も考慮しつつ、引き続き同国の防災体制の強化に資する支援を行っています。
 |
(写真提供:国土交通省)
フィリピンへの緊急援助
2006年8月、フィリピン・ギマラス島沖で、小型タンカーの沈没により重油が流出する海難事故が起きました。海洋汚染被害は深刻なもので、環境・観光資源への影響が懸念されました。そのためフィリピン政府からの要請を受け、日本から国際緊急援助隊専門家チームを派遣し、指導および助言を行い、被災地の復興に寄与しました。
11月から12月にかけては、台風に伴う大雨により大規模な泥流災害が発生し、約2万5,000人に被害が及びました。日本は要請を受けて、テント、スリーピング・マット等、約2,000万円相当の緊急援助物資の供与を行い、また12月26日には、100万ドルの食糧援助を実施しました。その後、供与した物資が確実に被災者に届き、有効活用されているか調査を行ったところ、災害発生直後は一部混乱もありましたが、おおむね物資は被災者に行き届き、有効に活用されていました。こうしたフォローアップは、政府開発援助の効率的な実施に寄与するものとして、今後とも積極的な活用が期待されます。
災害分野における二国間の協力では、経済社会基盤整備などのハード面での取組に加えて、人材育成などのソフト面での取組にも力を入れています。具体的な案件例としては、地震国であるイランのテヘランにおいて、大地震発生後の緊急対応能力の向上を目的とした技術協力プロジェクトを開始しました。イランでは、1990年のマンジール地震(死者約4万人)、2003年のバム地震(死者約2万7,000人)により大きな被害が発生しており、近年テヘランでの大地震発生が懸念されています。日本が過去に実施した開発調査では、テヘランで大規模な地震が発生した場合、数十万人にも及ぶ犠牲者が出るとの結果が出ています。プロジェクトでは、テヘラン市における地震後の被害拡大を軽減することを目指し、行政機関が地震発生後に迅速かつ効果的に緊急対応を行うためのシステムづくりと行政官の能力強化、コミュニティの地震に対する対応力を強化するための計画づくりと訓練による能力向上を図っています。
地震学、地震工学分野での人材育成支援
日本は1962年以来、地震地域の開発途上国から若手の研究者や技術者を招いて、「国際地震工学研修(注154)」を実施しています。この研修を修了した研修生の帰国後の地震学や地震工学の分野での活躍には目覚ましいものがあり、高く評価されています。また、2005年度から、政策研究大学院大学と連携し、修士号の学位を取得することが可能な研修コースへと高度化し、2006年9月のJICA集団研修では初の修士が19名誕生しました。さらに、2006年度から、アジア地域を対象に津波防災に対する高度な能力を持った人材の育成を目的とした津波防災研修を新たに開講しました。
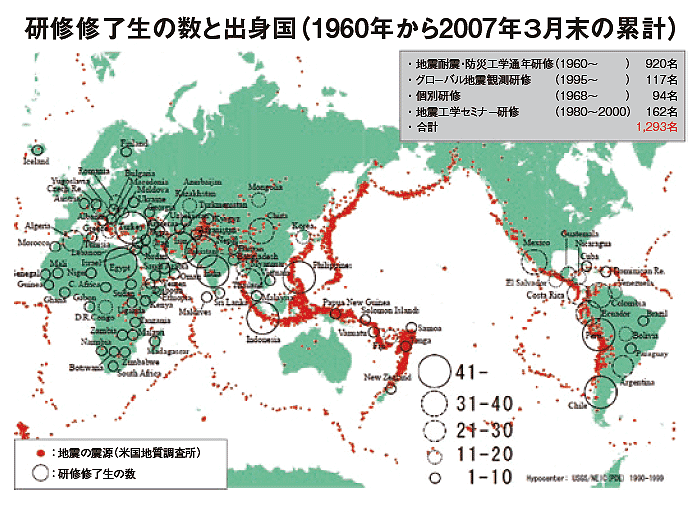 |
日本は、世界銀行防災グローバルファシリティ(注155)への資金拠出(注156)および日本人専門家の組織運営への参画(予定)等による協力を実施しています。同ファシリティは、災害に対してぜい弱な低・中所得国を対象に、災害予防の計画策定等の能力向上および災害復旧等を支援するもので、2006年9月に設立されました。(1)世界・地域レベルでの災害予防の知識共有や調査研究を行うトラックI、(2)マルチドナー信託基金を設立し、低・中所得国の貧困削減戦略や様々な分野の開発計画に防災の観点が組み入れられるよう支援するトラックII、(3)低所得国を対象に緊急復旧基金を設立するトラックIII-の3要素から構成されています。日本は、同ファシリティの創設を歓迎し、積極的な貢献を行うこととしています。
また、防災の重要性への認識の深まりを背景に、2006年の国連総会においては、各国と防災に関与する国連や世界銀行をはじめとした国際機関が一堂に会して防災への取組を議論する場として、防災グローバル・プラットフォームの設置が決定されました(注157)。日本は、「兵庫行動枠組」の推進を中心的に調整し、同プラットフォームの事務局である国連国際防災戦略(UN/ISDR (注158))事務局の活動を積極的に支援しています。
このほか、2006年度に新設された防災・災害復興支援無償資金協力においても国際機関との連携が図られており、国連開発計画(UNDP)が行う「南アジア地域における地震防災対策計画」に対し協力を行っています。これは南アジア地域協力連合(SAARC)の防災分野での能力強化も視野に入れつつ、南アジア地域において建物の耐震化等を進めるというUNDPの計画に日本が協力を行うもので、日本が地震災害に対して有している知見と経験の活用が期待されています。