(イ)テロ
テロは、国境を越えて引き起こされ、開発途上国のみならず、先進国を含めた国際社会全体に直接影響を及ぼす重大な地球的規模の問題です。世界各国で頻発しているテロ事件に見られるように、国際テロの脅威は依然として深刻です。また、テロは主体、手口が多様化する傾向にあり、テロ対策には以前にも増して、国際的な協調と強化が必要です。
テロの頻発は、観光、海外直接投資、貿易などを通じて、テロが発生した国の経済活動に重大な影響を与えます。そのため、開発途上国にとって、テロ対策を強化し、テロを未然に防止することは開発の重要な前提条件となります。
日本は、国際的なテロを防止するためには幅広い分野において国際社会が一致団結し、息の長い取組を継続することが重要と考え、国際社会におけるテロ対策への取組に積極的に参加しています。特に、テロリストにテロの手段を与えない、テロリストに安住の地を与えない、テロに対するぜい弱性を克服するという観点から、テロ対処能力が必ずしも十分でない開発途上国に対し、出入国管理、交通保安、テロ資金対策などの能力向上支援を重視しています。
日本と政治、経済、社会全般にわたり関係の深い東南アジア地域におけるテロを防止し、安全および安定を確保することは、日本の繁栄にとっても重要であり、重点的に支援を実施しています。具体的には、出入国管理、航空保安、港湾・海上保安、税関協力、輸出管理、法執行協力、テロ資金対策、CBRNテロ対策(注159)、テロ防止関連諸条約などの分野において、セミナーの開催、研修員の受入等を実施しています。
また、従来のスキームに加え、2006年度からテロ対策等治安無償資金協力を創設し、開発途上国に対するテロ対策支援を強化することを決定しました。
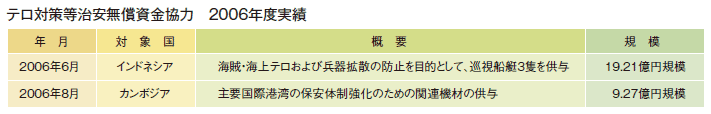 |
2006年9月には、日本で国際テロ事件捜査セミナーを開催しました。同セミナーは、アジア、中南米等の国々から国際テロ対策の担当者を招いて、日本の国際テロ事件に関する捜査および対策について技術の移転を図り、もって国際テロ対策における国際協力に資することを目的に開始され、JICAとの共催により、これまでに延べ130か国171名を招へいしています。
また、2007年7月には、クアラルンプールにおいて「化学・生物テロの事前対処および危機管理セミナー」を、東南アジア諸国等を対象に開催しました。このセミナーは、2002年10月のアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の際に、小泉純一郎総理大臣(当時)がテロ対策面における危機管理能力向上を目的とした取組を2003年度から5年間実施する旨表明したことを踏まえて、2003年および2006年に東京で、2004年および2005年にマレーシアで開催されたセミナーに引き続き実施されたものの第5回目です。
さらに、出入国管理の分野では、日本は東南アジア諸国等を対象に1987年以来毎年「東南アジア諸国出入国管理セミナー」を開催しています。同セミナーは、各国の出入国管理機関との相互の交流を深め、協力関係を強めるとともに各国の出入国管理業務に携わる職員の能力の向上を図り、各国の出入国管理行政の的確・円滑な運営に資することを目的としており、2006年は、水際における不法移民、国際テロリストおよび国際犯罪者の入国阻止や、入国を拒否した者の確実な退去のための航空会社との協力に関する現状と問題点および対応策等をテーマとして実施しました。日本は同セミナーで参加各国の出入国管理におけるテロ対処能力向上に向け、国際的な連携を図っています。また、参加国・地域から、同セミナーが東南アジア諸国等における出入国管理行政にとって非常に有益であるとの認識が示されました。
インドネシア空港保安訓練プロジェクト
日本はインドネシアに対して、2004年度には無償資金協力により航空保安検査機器等の供与を行い、2005年度には機器が供与された空港を中心にフォローアップとして主要空港保安体制強化計画の調査を実施しました。
この調査の結果、空港における緊急事案対応訓練が十分に実施されていないことが判明したことから、2006年度は、緊急事案対応訓練に対する指導・評価、バリ・デンパサール国際空港の緊急訓練計画についての提言、定期的事案対応訓練の重要性に関する講義を行い、同国における航空保安対策の更なる向上を図ることとしました。訓練は、爆発物を仕掛けた過激派の捕そくにより空港の脅威レベルが最高度に引き上げられ、警察の特殊部隊が爆発物処理を行うというシナリオで行われました。
この訓練に対する指導・講評等を通じて、今後はインドネシア航空局(DGCA)を中心に、同国の他空港へ効果的に波及し、航空保安対策の向上に向けた自立的取組の維持・発展が期待されます。
 |
(写真提供:国土交通省)
 |
(写真提供:国土交通省)
(ロ)海賊
日本は、石油や鉱物等のエネルギー資源の輸入のほとんどを海上輸送に依存しているため、海上の安全を脅かす海賊行為は、日本自身の平和と安定に直結する問題です。
特に、石油等の日本のエネルギー資源の大部分が通過する東南アジア地域においては、2005年3月にマラッカ海峡で発生した日本船舶および船員に対する襲撃に象徴されるような事件が近年発生しており、海上輸送に従事する日本国民の安全および日本経済活動にとっても直接の脅威となっています。日本は、海賊行為および海上テロの防止のために、沿岸国の取締り能力向上を図るとともに、情報共有強化や人材育成等に取り組んでいます。また、アジアの海賊問題に有効に対処すべく、地域協力促進のための法的枠組みとして、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP (注160))の作成交渉が日本主導の下行われ、2006年9月に同協定は発効しました。また、協定に基づきシンガポールに設置された情報共有センター(ISC (注161))には、日本から2名の職員を派遣しています。
2002年7月からフィリピン沿岸警備隊の業務遂行能力の向上を目的として「フィリピン海上保安人材育成プロジェクト」を実施し、海上取締り能力の向上などの海上保安人材育成に取り組んでいます。2006年10月には、「東アジア地域海上犯罪取締り研修」を実施し、アジア各国の海上保安機関の職員に対する研修を行いました。マラッカ海峡の沿岸国であるインドネシアやマレーシアに対しても海上取締り能力の向上を目的とした専門家を派遣しているほか、同9月には、マレーシア、タイ、日本の海上保安当局間による3か国海賊対策連携訓練を行いました。また、港湾におけるテロ対策として、2007年2月には日・ASEAN港湾保安情報伝達共同訓練を、インドネシアでテロが起こったことを想定して、保安情報の伝達訓練を日本およびASEAN9か国の運輸省、港湾管理者等関係組織間で実施し、26港湾が参加しました。同海峡の安全対策能力の強化のため、2006年6月に、テロ対策等治安無償資金協力によりインドネシアに対して3隻の巡視船艇を供与することを決定しました。