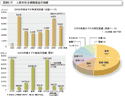日本政府は「人間の安全保障」の視点を日本の政府開発援助の実施に反映させるために、次の6つのアプローチをとっています(注3)。
(1)人々を中心に据え、人々に確実に届く援助
(2)地域社会を強化する援助
(3)人々の能力強化を重視する援助
(4)脅威にさらされている人々への支援を重視する援助
(5)文化の多様性を尊重する援助
(6)様々な専門知識を活用した分野横断的な援助
これらのアプローチは、日本の開発援助全体を通じて採用されていますが、特に取組を強化するための手段として、日本政府は、国連に設置した「人間の安全保障基金」を通じた支援および「草の根・人間安全保障無償資金協力」を通じた開発途上国のNGO等に対する二国間支援を実施しています。
(1) 人間の安全保障基金
1999年3月、日本政府は5億円を拠出し、国連に「人間の安全保障基金」が設置されました。日本は、2006年度までに170件の事業に対し、累計約335億円を拠出しています。これは、国連に設置された信託基金の中で最大規模となっています。
2006年度は、ペルーにおける「災害リスク・マネージメント・プロジェクト」約158万ドル、ブルンジにおける「戦争被災民の持続的社会復帰のためのプログラム」約218万ドル、ミャンマーにおける「国境地域におけるケシ栽培を停止した農民および困窮者に対する支援プロジェクト」約95万ドル等に対する支援が承認されました。
これらのプロジェクトは、複数の国際機関がNGO等と協力しつつ紛争と貧困といった複数の分野にまたがる現場の諸課題に対して包括的に対処するものです。これにより、様々な脅威にさらされている人々およびコミュニティを保護し、それらの脅威に対応していくための知識・技能を習得すること、すなわち「能力強化」を図ることで、持続的な発展を目指しています。
例えば、ブルンジにおける戦争被災民の持続的社会復帰のためのプログラムでは、国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF)、国連教育科学文化機関(UNESCO)および国連女性開発基金(UNIFEM)が、NGOとともにそれぞれの得意分野をいかして、紛争再発予防、貧困、保健・衛生、教育、ジェンダーといった様々な問題に包括的に対処しています。具体的には、(1)平和教育のための教員養成やワークショップの開催、(2)保健施設や衛生サービスの運営へのコミュニティの参加支援、(3)トイレの整備などによる衛生改善、(4)職業訓練・識字教育の実施、(5)帰還民女性に対する支援、(6)安全な飲料水・食料の確保-といった活動を分担して行うことで、紛争の被害者のよりよい将来のための基盤づくりを進めています。
人間の安全保障の実現のためには、他国や民間団体からも同基金の拠出を得て、その活動を一層充実させていくことが、今後の課題です。
(2) 草の根・人間安全保障無償資金協力
草の根・人間の安全保障無償資金協力は、開発途上国において活動している海外NGO、地方公共団体、教育・医療機関などが行う、現地の草の根レベルの住民に直結する基礎生活分野における比較的小規模なプロジェクトに対し支援を実施するもので、きめ細かく、かつ足の速い援助として内外から評価を受けています。
2003年度からは、「人間の安全保障」の理念をより強く反映させることとし、「草の根無償資金協力」から「草の根・人間の安全保障無償資金協力」に改称し、従来の重点分野である基礎生活分野の支援に加え、人間の安全保障の観点から特に重要な分野を優先的に支援する方針としました。また、これに併せ、最大供与限度額5,000万円(対人地雷分野以外)を、プロジェクトの内容に応じ、全案件最大1億円まで引き上げました。
このことにより、中東などの紛争後の地域において、地域住民の当面の生存を支える人道支援から「コミュニティづくり」や「国づくり」まで切れ目のない援助を実施しています。