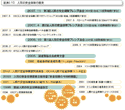国際社会において「人間の安全保障」という概念を初めて公にとりあげたのは、国連開発計画(UNDP)の1994年の「人間開発報告書」でした。その中では、「人間の安全保障」を「飢餓・疾病・抑圧等の恒常的な脅威からの安全の確保」と「日常の生活から突然断絶されることからの保護」の2点を含む包括的な概念であるとし、21世紀を目前に開発を進めるにあたり、個々人の生命と尊厳を重視する視点を提示しています。
その後、2000年9月の国連ミレニアム・サミットでアナン国連事務総長(当時)は、「恐怖からの自由、欠乏からの自由」とのキーワードを用いて報告を行い、人々を襲う地球規模の様々な課題にいかに対処すべきかを論じました。この事務総長報告を受け、同サミットで演説した森喜朗総理大臣(当時)は、日本が「人間の安全保障」を外交の柱に据えることを宣言し、世界的な有識者の参加を得て人間の安全保障のための国際委員会を発足させ、この考え方を更に深めていくことを呼びかけました。
そして、2001年1月のアナン国連事務総長の訪日時に森総理大臣の提案を受けて「人間の安全保障委員会」の創設が発表され、緒方貞子国連難民高等弁務官(現国際協力機構理事長)とアマルティア・セン・ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ学長(当時)を共同議長とする12名の有識者からなる委員会が創設されました。
人間の安全保障委員会は、5回の会合と世界各地での対話集会、分野別研究会などを経て、2003年2月に小泉純一郎総理大臣(当時)に最終報告書の内容を報告し、同年5月にアナン国連事務総長に報告書「安全保障の今日的課題」を提出しました。
同報告書では、安全保障の焦点を国家のみを対象とするものから人々を含むものへと拡大する必要があり、人々の安全を確保するためには包括的かつ統合された取組が必要であることが強調され、人間の安全保障を、「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守り、すべての人の自由と可能性を実現すること」と定義付けました。報告書の提言の推進と人間の安全保障基金の運用について国連事務総長に助言を行うため、2003年9月には「人間の安全保障諮問委員会」が創設され、緒方貞子議長の下、毎年会合が開かれています。
このような動きに加え、人間の安全保障を推進する活動として、1999年にカナダとノルウェーのイニシアティブにより「人間の安全保障ネットワーク」が創設されました。また、人間の安全保障を重視する国際機関も増加してきているほか、さらには、2005年国連首脳会合の成果文書においても「人間の安全保障」がとりあげられるなど、「人間の安全保障」の実現がグローバルな課題として注目されるに至っています。そして、2006年10月には、「人間の安全保障」に対する関心国の拡大を目的として、日本の主導の下、「人間の安全保障フレンズ」会合が開催され、これまで3回の会合が開かれています(注1)。また、2006年12月には、「紛争後の平和構築における人間の安全保障~人道支援から開発への移行~」をテーマに、日本の国連加盟50周年を記念する人間の安全保障国際シンポジウムを開催しました(注2)。