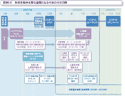日本は、「政府開発援助大綱」(2003年8月)において、国際社会がただちに協調して対応を強化しなければならない地球的規模の問題の一つとして、地球温暖化をはじめとする環境問題を位置付けています。また、「政府開発援助に関する中期政策」(2005年2月)において、環境分野の重点の一つに「地球温暖化対策」を挙げています。このような方針の下、環境と開発の両立を図り、持続可能な開発を進めていくため、気候変動対策を含む環境分野における途上国支援を積極的に実施してきています。
日本は、1970年代の公害やオイルショックの経験から環境・省エネルギー対策を推進し、優れた技術やノウハウを開発・蓄積してきました。これらを活用して、省エネルギー技術の普及、エネルギー効率の向上、森林対策などの緩和策を積極的に推進しています。例えば、中国においては、老朽化した石炭火力発電所に代え、小水力発電所や揚水発電所の建設を支援しています。2007年1月の東アジア首脳会議(EAS)では、日本は、「エネルギー協力イニシアティブ」を発表し、省エネルギーの推進、バイオマスエネルギーの推進、石炭のクリーンな利用、エネルギー貧困の解消を柱とする協力策を打ち出しました。これに基づき、省エネルギー分野の研修員受入やエネルギー・インフラ整備等を着実に進めています。また、エネルギー貧困の解消については、EAS参加各国の置かれている経済社会状況等を勘案した、電力設備の整備、地方電化等のエネルギー・アクセス改善や省エネルギー対策を含む資金協力・技術協力として、今後3年間で20億ドル規模のエネルギー関連の支援を実施するとともに、JBICの投資金融等も積極的に活用していく方針です。森林保全対策では、例えば、ラオス北部において、焼畑移動耕作、不法伐採などにより森林が著しく減少している状況を受け、地方政府の職員が住民とともに村落森林管理を実施できるよう指導するとともに、アグロフォレストリー(注3)、養豚、魚養殖や織物などで森林資源の持続的活用を図り、森林資源の回復と住民の生計向上を同時に図る技術協力プロジェクトを実施しています。
また、気候変動枠組条約京都議定書の下で導入されたクリーン開発メカニズム(CDM)の促進は、温室効果ガスの排出量を削減すると同時に日本が排出クレジットを獲得する可能性もあることから、CDM促進のための途上国支援も推進しています。例えば、CDM案件の申請書類を作成するためには技術的な知見が必要であることから、CDM案件形成のための能力強化の事業を実施しています(注4)。具体的には、アルゼンチンのCDM推進体制の強化と国内のCDMの理解促進を支援する「CDM基盤整備プロジェクト」を2006年6月から実施した結果、同国では具体的なプロジェクト(注5)につきCDM申請に必要となる設計書が作成されるなど、気候変動問題への取組が進んでいます。また、チリにおいて、植林に関するCDM能力開発および促進のための開発調査を2006年2月から実施しています。
また、対エジプト円借款「ザファラーナ風力発電計画」が2007年6月、二国間協力事業として政府開発援助により事業自体に支援・実施が行われる大型のCDM事業として、世界で初めて登録されました。この風力発電計画から生じた排出クレジットは、日本の民間企業が買い取ることになっています。また、同年9月、日本は、インドにおいて、デリーメトロに対する円借款による支援の一部が活用された温室効果ガス排出量の少ない車両を地下鉄に導入する事業と、スリランカにおいて、環境対策投資の資金を提供する円借款事業の一部を活用してココナッツ殻の木炭化と発電を行う事業を、CDM事業として承認しました(投資国による承認)。インド政府、スリランカ政府による承認(ホスト国による承認)は既に取得しているので、CDM理事会の承認を得れば、政府開発援助を活用した新たなCDM案件の具体例となります。日本は、今後も、政府開発援助等を活用したCDMを推進していくこととしています(注6)。
気候変動への適応策については、地球温暖化の進行が明らかになるにつれ、世界的な取組の強化が求められています。世界銀行や国連開発計画(UNDP)などの開発関連の国際機関においても、適応策の取組強化が議論され、先進国による取組強化の動き(注7)も出てきています。
日本は、これまでも、防災や水、農業などの分野で適応に資する支援を行ってきていますが、「気候変動への適応に対するODAに関する有識者会議」が2007年3月に外務省に提出した「気候変動への適応分野における開発途上国支援に関する提言」では、日本はこれまで適応分野で行ってきた支援の経験や知見をいかし、国際社会の連携促進のために先頭に立つべきであり、同時に、日本の援助実施においても適応への関心を高める取組をすべきことが提言されています。
しかしながら、援助実施の側面では、特に気候変動の影響に最もぜい弱な最貧国等においては、貧困削減や教育の普及、保健衛生の向上などの基礎生活分野における数多くの課題に優先的に対処する必要があり、生活に必要なインフラ整備における支援の必要性も高く、相手国政府からの支援要請もこれらの課題に集中する傾向があります。適応策を進めるためには、開発途上国自身が、気候変動による影響を考慮し、それを踏まえた開発計画を策定する必要がありますが、多くの途上国には、そのような能力が十分に備わっていません。さらに、気候変動をはじめとする環境問題への対応には、高度な政策調整能力が要求されます。先進国では、複数の省庁が政策を調整しながら、科学的な知見も活用しつつ、総合的な観点から施策を実施していくことが可能ですが、行政能力(ガバナンス)が弱い開発途上国においては、政策の調整自体が困難である場合が多く見られます。したがって、開発途上国において気候変動対策を進めるためには、このような途上国政府の人材育成等の能力強化も重要な課題です。
気候変動への適応支援は、政府、コミュニティ、個人まで、様々なレベルで行う必要があり、日本が提唱する「人間の安全保障」の確立にも資するものです。その一方で、開発援助の分野の新しいテーマであるため、今後、適応支援策の好事例を積み重ねていく必要があります。