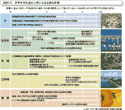2007年2月、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)(注1)は、第4次評価報告書(第1作業部会報告書の政策決定者向け要約)を発表し、人間の活動から生じる温室効果ガスの増加が地球温暖化の原因であるとほぼ断定しました。その上で、いくつかのシナリオをもとに平均気温の上昇について予測を提示するとともに、世界中のあらゆる地域の自然と社会が地球温暖化の影響を受けることを明らかにしました。2001年のIPCC第3次評価報告書では、気候変動の影響が地域ごとに部分的に出始めていることが指摘されるにとどまったのに対し、第4次評価報告書は、地球温暖化の進行に強い警鐘を鳴らし、国際社会の大きな関心を集めました。
地球上では、既に、海面水位の上昇、熱波による死亡、動植物の生息地域の高緯度・高地方向への移動などの生態系の変化、媒介生物による感染症の発生などの影響が現れており(注2)、今後も、地球温暖化の進行とともに様々な影響が顕在化してくることが予想されます。気候変動から受ける影響は、気候変動によって生じる現象そのものの大きさと社会システムのぜい弱性により大きく異なりますが、特に多くの開発途上国においては、現在の気象条件に対しても十分な対応ができていない状態であり、近い将来、気候変動の悪影響を受ける可能性が高まっています。また、同一の国の中でも、自然災害に対してぜい弱な土地に居住し、自然資源に依存した生活を形成している社会的弱者は、地球温暖化に伴う環境の変化の影響を最も受けやすいと考えられます。
どんなに厳しく温室効果ガス排出量の削減努力を行っても、今後数十年間は気候変化の更なる影響を回避することができないと評価されており、気候変動の緩和策(温室効果ガス排出量の削減)とともに適応策(気候変動による悪影響への対応)を組み合わせ、気候変動に伴うリスクを低減することが必要です。持続可能な社会の構築のため、国際社会全体で温室効果ガスの排出量削減に取り組み、温暖化の進行を食い止めると同時に、悪化していく地球環境に対応する能力を強化することが喫緊の課題となっています。