東京農工大学は、2008年1月から3年間、ベトナムのバクマー国立公園の緩衝地帯(注1)に住む住民を対象に炭利用の技術を普及し、自然と共存しつつ、住民の収入改善を目指すプロジェクトを開始する予定です。JICAが実施している草の根技術協力事業(草の根パートナー型)(注2)に申請し、2007年に採択されました。
対象地域となるバクマー国立公園は、2006年に世界自然遺産候補に推薦されました。周辺には約8万人が住み、主に農業を営んでいますが、決して収入は高くはなく、一月2,000円から4,000円で生活しています。これらの住民の多くは、公園内に生えている木を伐採し、薪として利用しているため、国立公園の自然保護と、住民の生活との両立が問題となっていました。そこで今回提案されたのが、農産廃物からつくられる炭や、改良かまど(注3)の利用です。
東京農工大学の関係者が、事前に現地調査をした結果、対象地域には大量の農産廃物(もみがら、椰子がら、トウモロコシの芯等)が放置されていることが分かりました。これらの農産廃物を炭化させ、燃料として利用することで、薪の量を減らし、伐採される木を減らすことが可能です。熱効率の良いかまどを導入すれば、さらにその効果は高まります。また、炭や炭化過程で生成される木酢を農作物に与えれば、化学肥料や農薬を減らしても、作物の育ちが良く、土壌や水の汚染が減るという利点があります。薪を採取するための労働力や、農業資材を購入するコストが削減されます。さらに「有機栽培」という付加価値をつけて野菜や果物を売ることで、より多くの現金収入も期待できます。
そこで、プロジェクトの内容と期待される効果や可能性について、地域住民に対する事前説明を行いました。その結果、このまま農薬や化学肥料を大量に使用することによる健康不安や井戸が汚染される心配を訴えたり、炭や木酢を使うことで生産性が高く、安全な農作物がつくれるのであれば是非挑戦したい、そして生活を向上させたい、といった意見が数多く寄せられました。これは、住民のプロジェクトに対する期待や関心の高さを表すものです。東京農工大学に留学していたバクマー国立公園の環境教育・エコツーリズムセンター長のグエン・ヴー・リンさんが、住民と大学側の橋渡しを申し出てくれたことも、プロジェクトを成功させるためには力強い手助けとなります。
プロジェクトを実施するにあたって、不安はありませんか、という質問に、東京農工大学の山田祐彰先生は次のように答えます。「今回私たちが行おうとすることは、世界各地で検証を繰り返してきたことです。ですからきっとうまくいくと信じています。そして一つでも、目に見える効果を現地の人々に実感してもらうようにすること、これが一番大切なことだと思っています」
プロジェクト開始まで、更なる事前の調査や準備など、時間はいくらあっても足りないようです。これから3年間、どのような成果が現れるのか・・・。現地の住民が、生活の豊かさと自然保護の両立ができたと感じられるように、今日も東京農工大学では、着々と準備が進められています。
 |
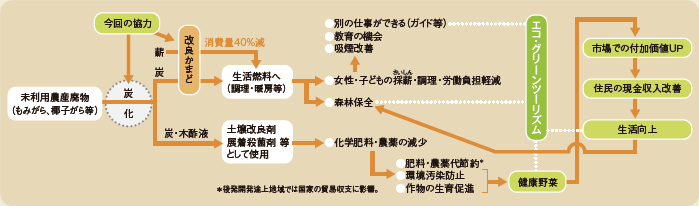 |
注1 : 自然保護地域設定の地域区分(ゾーニング)の一つで、核心地域(コアエリア)を取り囲んで、保護地域外からの影響を緩和するため人間活動に制限を加える地域。バッファーゾーンとも呼ばれる。
注2 : 日本のNGO、大学、地方自治体、公益法人団体等が、これまでに培ってきた経験や技術をいかし、開発途上国で国際協力を行う際、JICAがその活動を支援し、共同で実施する事業。
注3 : 今日でも、女性が背丈ほどもある薪を遠い山の急斜面から背負ってきて、かまども煙突もない土間に並べ、煙にいぶされながら煮炊きしている。熱効率は改良かまどの半分といわれている。