「思春期の女子、人身売買及びHIV/エイズ対策 : 南アジアにおける対応強化」プロジェクト
国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所で、プログラム専門家として働く宇治和幸さんに、人間の安全保障基金プロジェクトについて聞きました。
このプロジェクトを企画・実施することになった背景を教えてください。
南アジアは、HIV感染人口が非常に多く、また、世界でも有数の人身取引発生地域です。南アジアでは性的搾取を目的とした人身取引が横行していますが、性産業ではHIV感染のリスクが少ない低年齢の女性を客が求め、その需要に犯罪組織が対応したため、HIV感染者の低年齢化が進んでいます。
HIVに感染、または人身取引の被害に遭った女性・少女たちは、強い偏見と差別により家族や所属する地域社会から見捨てられ、暴力・暴言の対象となるなど、人間としての権利が奪われる状況にあります。このように、HIV/エイズ問題と人身取引問題は相互に密接な関係にあり、これらの両方の問題に包括的に対処するために、このプロジェクトが企画・実施されることとなりました。
このプロジェクトでは具体的にどのような活動が行われたのでしょうか。
このプロジェクトは、HIV/エイズ問題と人身取引問題を包括的に検証し、これらの対策を有機的に統合させる形でプロジェクトを進めました。特に、人間の安全保障の根幹をなす「保護」と「能力強化」の視点に立った活動を行いました。
「保護」の観点からは、人身取引・HIV感染の防止、それらの被害者の救助および保護、女性に差別的な法律・政策・慣習等の社会構造を検証し、その変革の提言などにより、女性を保護する環境を整備しました。また、「能力強化」の観点からは、女性・少女が出稼ぎしなくても済むように、重点地区における雇用創出・職業訓練の実施や被害者が支援を受けられるよう弁護士、警察等への啓もう活動などを行いました。これらの活動は、南アジア各国の約30のNGOと共同で実施しました。
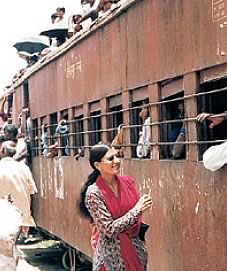 |
このプロジェクトを実施するにあたって困難だった点はありましたか。
南アジアでは、人身取引やHIV/エイズは政治的、社会的に非常に機微な問題であるため、政府や地域社会の理解と協力を得るにあたり困難に直面しました。また、特に人身取引に関する信頼性のあるデータがなかったことも、プロジェクトを推進する上での障害となりました。
強い偏見と差別がある中で、人身取引の被害者が売春婦やエイズ感染者と同一視され、被害者が更なる社会的制裁の犠牲にならないよう、細心の注意を払う必要がありました。
このプロジェクトを実施して良かったと思いますか。
様々な困難もありましたが、3年間実施されたこのプロジェクトを通じて、実に342名の人身取引被害者を救助・保護することができたことがうれしかったです。人身被害者の総数に比べれば氷山の一角にすぎませんが、342名を救ったことは、日本政府の支援を受けた本プロジェクトの最も大きな具体的成果であると思います。
 |
スーダンにおける「食料安全保障及び貧困軽減のための参加及び地域社会の形成促進を通じた紛争後の農業生産能力の再活性化」プロジェクト(国連工業開発機関(UNIDO))
スーダンでは、2005年まで20年以上にわたる内戦と干ばつのために、中部に位置するヌバ山地域の農業は疲へいし、地域に居住する多数の国内避難民、帰還難民(特に女性)の食糧確保および地域社会への定着が急務となっています。
日本は、農業生産性の向上、地域社会の強化を目的として2005年から開始されたこのプロジェクトに対して、人間の安全保障基金を通じて約125万8,000ドルの支援を行いました。
このプロジェクトでは、現地の鍛冶職人に対する技術訓練を通じた農具の生産、農民への農具の提供、家畜を使った耕作の導入等による耕地面積の拡大と農業生産性の向上、女性に対する食品の加工および保存に関する知識と技術の移転、集落代表者の能力の強化を行いました。
これらの職業訓練や営農支援活動を通じて、収入手段の確保と食糧の安定供給が実現し、さらにかつては対立していた住民同士に対話が生まれ、地域の安定に貢献することができました。地域の安定により国内避難民の帰還が促進され、彼らは元の居住地への帰還後も供与された農具と身につけた技術によって農業を続けたいと希望しており、将来の生計の維持も期待できます。
このプロジェクトは、世界銀行の報告書「Community-based Development in Northern Sudan-Lessons Learned」(2005年9月)においても優良案件として紹介されています。
 |