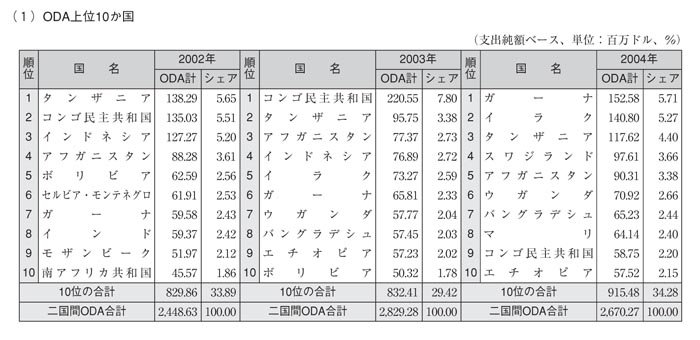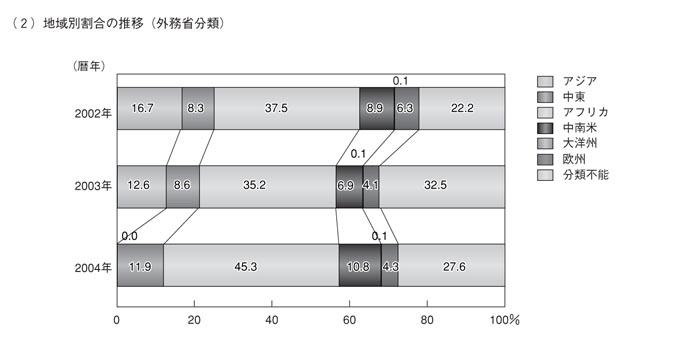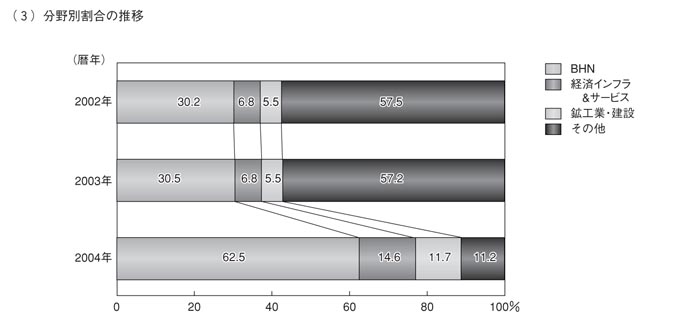資料編3,4,5章 > 第4章 > 第2節 > 5 オランダ
5 オランダ
(1)援助政策等
オランダは、外交政策の主要な目標8つを挙げており、特にその中の5つ(安全と安定、効果的な人道支援とグッド・ガバナンス、繁栄促進と貧困削減、人的発展と社会的発展、環境の保全・改善)が援助政策に密接な繋がりを持っている。
オランダは、貧困削減を援助政策の主要目的に掲げ、ミレニアム開発目標(MDGs)を自国援助政策のガイドラインと位置付け、MDGsで設定された対GNP比0.7%の目標を達成している数少ない国の一つである。ODAの対GNP比0.8%を政策目標として設定しているが、昨年2005年のODA実績は、スーダン及びインドネシアなどへの人道支援関係のために支出が増大し、対GNI比0.82%、51億3,100万ドルで世界第6位の援助国となっている(DAC統計ベース:暫定値)。
二国間援助の特徴としては、限られた資源をより有効に利用するとの観点から、長期的な援助の対象国を限定する政策をとっていることがあげられる。この政策を基に、現在は、36か国をパートナー国として二国間援助を実施している。
二国間及び多国間援助を補完するものとして、長年の経験をベースにしたNGOを通じての援助活動も活発であり、2005年のODA予算総額の約15%は内外のNGO支援に向けられた。
さらに、MDGs達成に向けた2015年までの長期援助政策として、以下の重点項目を掲げている。
[1]政策の統合性:援助政策と外交、政治対話、安全保障、貿易等の他の政策との統合性を追求。開発には安定が不可欠として、紛争中または紛争直後の地域の平和構築のために、迅速かつ柔軟な支援を行うことを可能にする「安定基金」を創設。
[2]地域アプローチ:国境をまたがる紛争や平和構築等においては、地域別の援助政策を実施しており、「アフリカの角」地域、アフリカ大湖地域、西バルカン地域が対象。
[3]アフリカ重視:NEPAD,ECOWAS等の平和と開発のためのアフリカのイニシアティブを強く支援しており、オランダの援助予算の50%がアフリカ向け。特に、教育、保健、環境、雇用創出の分野で貢献している。
[4]民間部門の重要性:援助国及び被援助国の市民社会、企業が果たす役割を重視。開発途上国の雇用の確保、産業・投資・輸出環境等を促進するプログラムを実施。
[5]一貫性:欧州連合の枠内で、援助政策と農業政策、貿易政策等の一貫性を追求し、開発途上国からの財・サービス等の国際市場へのよりよいアクセスを促進する。
[6]テーマ別の優先順位:教育、エイズ対策、環境と水、リプロダクティブ・ヘルスを掲げている。
特に教育分野を援助政策の中心に据え、2007年までには援助予算総額の15%が教育支援、特に識字率の向上や初等教育と基礎職業訓練の質の向上に充てられる予定である。また、エイズ対策には2007年までに予算を2億7,000万ユーロまで倍増する予定となっている。さらに、計36か国の援助パートナー国において貧困削減に資するための環境、特に水管理支援に力が入れられている。さらに、リプロダクティブ・ヘルスの向上は、貧困削減の達成及びエイズ予防に不可欠として特に性教育や保険衛生面における支援を行っている。
(2)援助実施体制
オランダでは外務省が援助政策の立案・実施に関し主要な責任を有し、同省には外務大臣に加えて、援助政策専任の開発協力大臣ポストが設置されている。
援助政策の基本的枠組みは外務省が決定するが、教育・経済関連等他省にも小規模ながらODA予算があることもあり、他省庁との調整を要する場合は、外務省がその調整役を務める。外務省の国際協力局にある「coherence unit」が他省庁にまたがる援助関連政策の一貫性を後押しする役割を果たしている。また、EUレベルでの政策決定に臨んでの準備作業の段階で他省庁間協議が行われるが、その際にも援助政策における利害関心事項が提起される。開発協力大臣は、内閣の中での援助政策の一貫性の監視役として、必要であれば閣議の際に調整役を果たす。
現在、外務省で開発援助に携わる職人の数は約1,560人(2006年1月1日現在、オランダ外務省による推定。在外公館に勤務する職員を含む)である。本省では国際協力局が援助政策の中心を担っており、在外公館は現地における案件発掘の役割を担っている。現地のNGOは在外公館に対して案件を持ち込むことができ、それを基にして在外公館は本省へのプロポーザルを行う。
援助実施は3つの主要な形態、つまり、二国間援助(多くがセクター別支援、全て贈与)、多国間援助(世銀・国連等の国際機関)、民間機関(企業・NGO)への補助金交付を通じて行われている。
条件を満たした一定数のNGOに対しては、共同出資プログラムにより、ODAの一定の割合(来年度よりは一定額)が補助金として交付されてきている。しかし、NGOの独立を尊重するという立場から、外務省とNGOの間には、ヒエラルキーは存在せず、監督・指導という関係にはない。
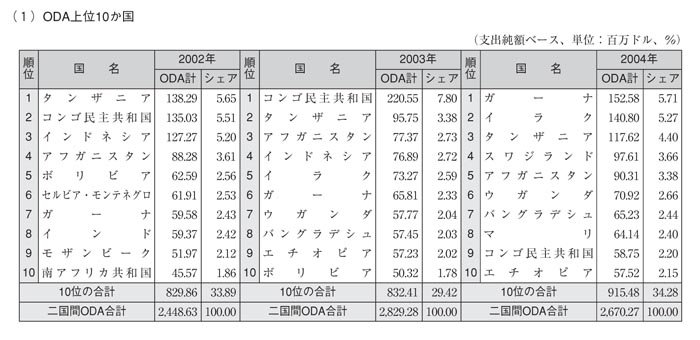
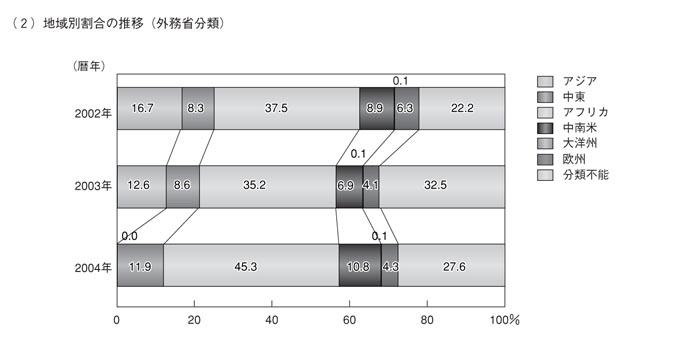
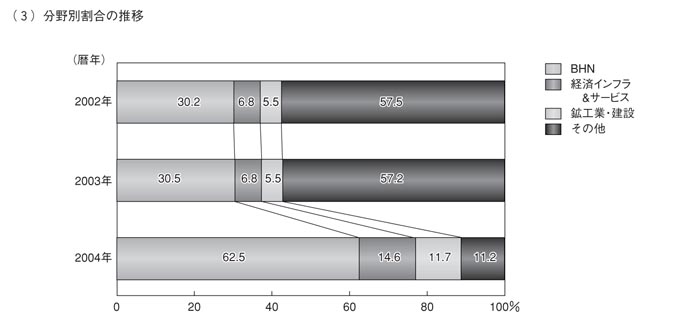

 次頁
次頁