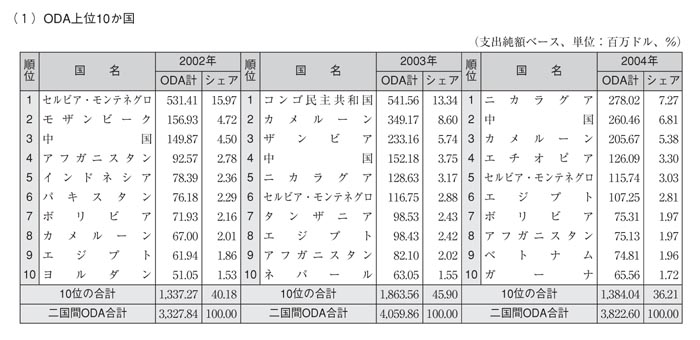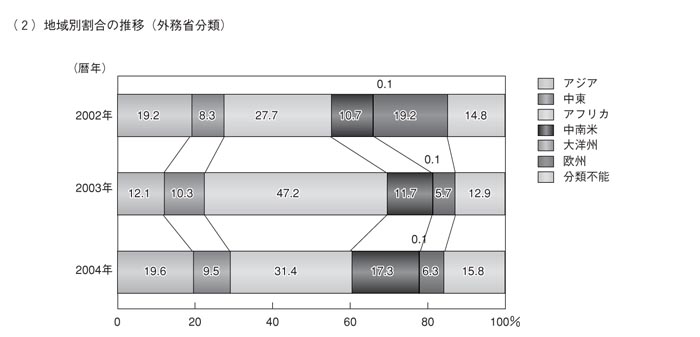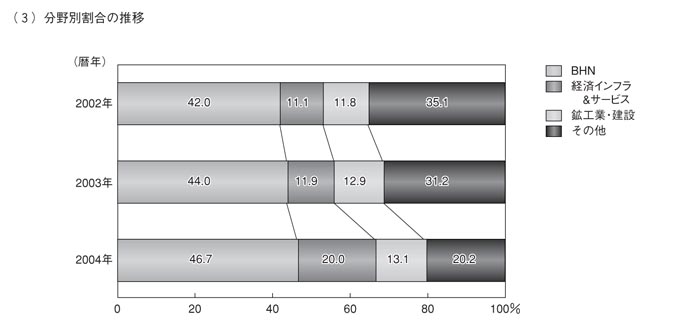資料編3,4,5章 > 第4章 > 第2節 > 3 ドイツ
3 ドイツ
(1)援助政策等
(イ)外交の一部としてのODA政策とその目標
(a)2005年11月に成立したメルケル政権は、キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)による大連立政権であり、同政権の基本政策は、政権発足時に合意された連立協定に明記されている。この中で「開発政策は独の外交政策の一部分である」とされ、開発問題はドイツ及び欧州における平和と繁栄に直接影響するものとの認識が示されている。
(b)独のODA政策の目標は、世界における貧困を削減し、平和を構築していくことにあるとされており、この目標を具体的に定めたものとして「行動計画2015(Programme of Action 2015)」がある。これはシュレーダー前政権時代の2001年に閣議決定された文書であるが、独開発政策の目標を定めたものとして現政権にも引き継がれている。
(c)この「行動計画2015」では、途上国支援における具体的な優先課題として、[1]経済開発と社会的弱者の経済活動への参加促進、[2]食料確保と農業改革の実現、[3]公正な貿易への参画促進、[4]債務の削減、[5]社会サービスの確保と弱者保護の強化、[6]資源と環境の保全、[7]人権擁護の実現、[8]ジェンダーへの配慮、[9]良い統治の実現、[10]「人間の安全保障」・軍縮の促進を通じての紛争の平和的解決、が挙げられている。
(ロ)援助政策における特徴
(a)ドイツは、ミレニアム開発目標(MDGs)を強く支持しており、2005年5月のEU開発大臣会合における決定に従い、2010年までにODAの対GNI比0.51%、2015年までに同0.7%を達成することを対外的に明らかにしている。2005年における独のODA実績は、米、日本、英国、フランスに次いでDAC諸国中では第5位であり、対GNI比は0.35%で同13位となっている(DAC統計ベース暫定値)。「0.7%目標」達成のためには、ODA予算の拡大、債務削減への協力、革新的資金調達メカニズムの導入が課題であるとされている。
(b)二国間援助と多国間援助の比率としては、伝統的に約3分の2が二国間援助、約3分の1が国際機関を通じた援助という構成になっている(2004年は世界銀行への拠出が伸びたため、二国間援助51%、多国間援助49%となった)。
(c)また、近年における特徴の一つとして、二国間援助における重点化が挙げられる。これは、途上国の経済面・社会面・環境面並びに政治面を考慮し、「重点的パートナー国」及び「パートナー国」を選定し、これら諸国に対して二国間援助(資金協力・技術協力)を集中的に実施することにより、援助の効率化及び効果向上を図るものである(2005年には合計で約70ヵ国を選定)。「重点的パートナー国」については、概ね3つの重点セクターが選ばれ、また「パートナー国」には1つの重点セクターが選定されることになっており、選ばれたセクターに独の支援(資金協力、技術協力、NGO支援等)を集中させるようになっている。なお、これら重点地域以外の途上国に対しては、二国間援助よりも国際機関経由の支援やEUによる支援が中心となっている。
(d)援助における重点セクターとしては、[1]民主主義・市民社会・公的セクター及び人権の促進、[2]平和構築・紛争予防、[3]教育、[4]保健・家族計画・HIV/AIDS、[5]飲料水・水管理・排水・廃棄物処理、[6]食糧・農業、[7]環境・天然資源開発、[8]経済改革・市場経済促進、[9]エネルギー、[10]輸送・通信・都市開発、等が挙げられている。これらのセクターのいずれを重点分野とするかについては、途上国の経済面・社会面・環境面及び政治面について検討し、他のドナーや国際機関の動向等も勘案して決定されることとなっている。
(e)連邦政府以外に多くの機関・団体が開発援助に関与していることも独の援助政策の特徴であり、特にNGO、教会系諸団体、政党関係の財団及び連邦各州(16州)は援助における重要なプレーヤーとなっている。
(2)実施体制
(イ)主務官庁としての経済協力開発省(BMZ)
(a)援助政策の企画・立案は、1962年に設立された経済協力開発省(BMZ)が所管しており、二国間援助(資金協力、技術協力)及び国際機関を通じた援助について同省(本省定員約600名)を中心に調整が行われる。予算については、その太宗がBMZに計上されているが、人道支援関連については外務省、国際開発金融機関関連については財務省、その他所管事項の国際協力について各連邦省庁(経済技術省、内務省、労働社会省等)がそれぞれの予算からのODAを実施する。各省庁によるODAの実績についてのとりまとめもBMZが行っており、同省を通じて独のODA実績がDACに報告されている。
(b)外交政策との関連からは、BMZは外務省と協議を行うこととなっており、両省庁間では関係者による定例の協議が行われている他、日常的には関係部局間で連絡が行われている。また、途上国の現場での経済協力の実施については現地ドイツ大使館が調整しており、BMZからは独在外公館に30名前後が出向している。
(ロ)実施機関
(a)独の援助政策におけるもう一つの特徴として、実施機関が相対的に多いことが指摘されており、実施機関の統合は、今後の大きな課題となっている。これらの実施機関の中でも中心となるのは、技術協力を担当する技術協力公社(GTZ)と資金協力を担当する復興金融公庫(KfW)であり、両機関の統合の可能性についても国内関係者の間で議論されている。
(b)GTZは、連邦政府を出資者とする有限会社の形態をとっており、本部をフランクフルト近郊のエッシュボルンに置いている(本部の定員は約1,000名)。監査役会の議長はBMZ事務次官であり、GTZの事業予算の殆どは独連邦政府からの委託金であるが、GTZは国際機関や第三国政府からの委託による事業も実施している。なお、GTZは67か国に在外事務所を有しており、現地独大使館と調整して技術協力を実施している。
(c)KfWは、復興金融公庫法に基づく公法人であり、連邦及び州がその所有者となっている。KfWは銀行グループの総称であり、ODA事業(資金協力)を実施しているのは、グループの中の「KfW開発銀行」(本部はフランクフルトで定員約370名)であるが、ODAの世界では同行を「KfW」と呼ぶことが多い。事業全般について監督する監査役会の正副議長は財務大臣と経済技術大臣であり(輪番制)、その他に外務大臣や各州首相等が委員に任命されている。KfWは、途上国等に28の在外事務所を有しており、GTZ同様、現地ドイツ大使館と調整しながら資金協力事業を実施している。
(d)自然災害時における重要なプレーヤーとしては、独赤十字を始めとするNGOが挙げられる。独外務省が予算計上している緊急・人道支援の大半がこれら独NGOを通じて実施されている。また、ODAとして計上される額としては小さいものの、外国における自然災害等において現場で機動的に援助を行う機関として連邦技術支援庁(THW:内務省所管)がある。同庁はドイツ国内の自然災害への対応を本来の任務としているが、海外にも協力チームを派遣しており、日本の国際緊急援助隊と同様の機能を果たしている。
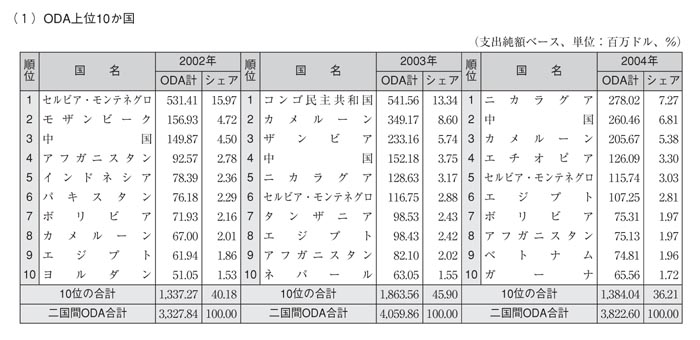
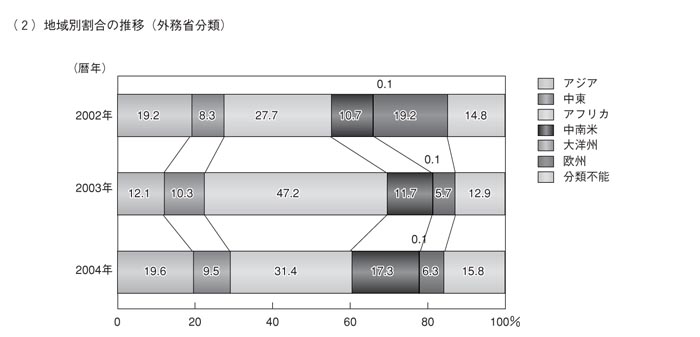
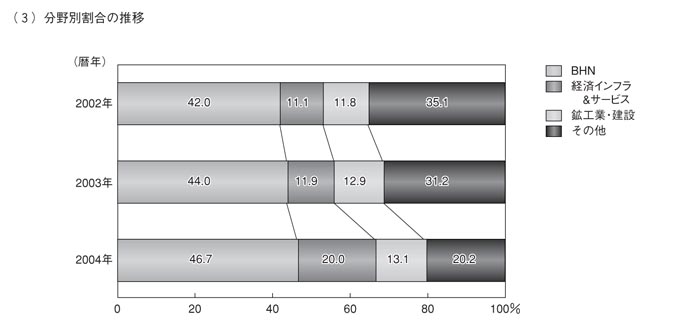

 次頁
次頁