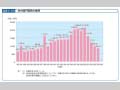本文 > 第II部 > 第2章 > 第3節 > 1.東アジア地域
第3節 地域別の取組状況
ODA大綱では、日本と密接な関係を有し、日本の安全と繁栄に大きな影響を及ぼし得るアジアを重点地域としています。その他の地域についてもODA大綱の目的、基本方針及び重点課題を踏まえて、各地域の援助需要、発展状況に留意しつつ、重点化を図ることとしています。以下では、各地域別の日本のODAの取組状況について説明します。
1.東アジア地域
日本の東アジア地域に対する2005年の二国間ODAは、約30億6,852万ドルで、二国間ODA全体に占める割合は29.3%です。
東アジア諸国は日本と政治・経済・文化などあらゆる面において緊密な相互依存関係にあり、東アジア地域の発展と安定は日本の安全と繁栄にとって重要な意義を有しています。日本は、これまで東アジア地域に対して、ODAによる経済インフラ基盤整備などを進めるとともに、経済連携の強化などを通じて民間投資や貿易の活性化を図るなど、ODAと投資・貿易を連携させた経済協力を進めることにより、同地域の目覚ましい発展に貢献してきました。ODA大綱においても、引き続きアジアを重点地域としています。
東アジア地域においては、高い経済成長を遂げ、すでに韓国やシンガポールのように被援助国から援助国へ移行した国も現れている一方で、カンボジアやラオスなどのLDCが依然として存在しています。また、中国のように、近年著しい経済成長を成し遂げつつも、国内格差を抱えている国や、ベトナムのように、中央計画経済体制から市場経済体制への移行の途上にある国もあります。日本は、このような各国の経済社会状況の多様性、援助需要の変化などに十分留意しつつ、援助を行っています。
2005年12月14日に、マレーシアのクアラルンプールにおいて、第一回東アジア首脳会議(EAS:East Asia Summit)が開催されました。同会議において「東アジア首脳会議に関するクアラルンプール宣言」が採択され、広範な戦略的、政治的及び経済的諸問題について、普遍的価値とグローバルな規範にのっとりつつ、東アジアにおける平和、安定及び経済的繁栄を促進することを目的とした対話を行うため、今後も東アジア首脳会議を開催することとしました。会議では、日本は、東アジア首脳会議を地域協力の理念や原則、共通課題への対処について、戦略的かつ大局的観点から議論する場に発展させるべきこと、また、鳥インフルエンザ、テロ、海賊対策等の諸問題について協力を進め、参加国の一体感を醸成すれば、東アジア首脳会議は共同体形成に重要な役割を果たすことができる旨表明しました。
2005年12月13日に行われた日・ASEAN首脳会議において、日本はASEAN共同体の形成に向けた努力に対し、75億円を拠出することを表明しました(これを受け、2006年3月に日ASEAN統合基金が設立)。また、アジアにおける鳥インフルエンザ対策のためにASEAN域内50万人分のワクチン(タミフル)の供与を含む、1億3,500万ドルの支援を表明しました。さらに、国境を越える犯罪とテロとの闘い、防災の強化、人的交流の促進等の分野で協力していくことも表明し、これらは着実に実施されています。ASEANはこのような日本の協力に対して感謝と歓迎を表明しています。
また、同13日に開催された第二回日・CLV(カンボジア・ラオス・ベトナム)首脳会議では、前年度の同首脳会議でCLV側から要請のあったCLV3か国にまたがる辺境地帯「開発の三角地帯」に対し、教育や医療など基礎的分野を中心として2005年度に計16件、総額約20億円の協力を行うことを表明しました。ASEAN域内で開発格差の是正に特に関心の高いCLV首脳より、こうした日本のイニシアティブに対し感謝の意が表明されました。
労働分野においてもASEAN諸国に対し支援をしています。具体的には、ASEAN諸国において健全な労使関係を構築するため、ASEAN事務局と協力してプロジェクト実施のための委員会を開催するとともに、ASEAN地域合同の政労使三者構成セミナー、能力向上ワークショップ及び国別セミナーを実施しました。特に国別セミナーについては、ASEANへの後発加盟国に対して、日本人専門家を派遣し講義を行うなど、対象国の実態に則した手法を選択することで、地域内格差の是正の観点からも本事業の効果をより一層高めました。
食料安全保障の強化には、食料安全保障に関する情報基盤の整備が不可欠であり、2005年度は食料・農業統計情報に係る人材を育成するため、ASEAN地域ワークショップ及び各国別セミナーを実施し、統計情報の整備にかかる講義・指導を行いました。しかし、ASEAN地域における農業統計の整備状況は各国間の格差が大きく、特に後発途上国においては人材や技術面の立ち後れが顕著であり、地域全体で進めている「ASEAN食料安全保障情報システム(AFSIS:ASEAN Food Security Information System)」(注)の推進にも支障が生じています。これに対応するため、例えば2005年度はミャンマーの担当官を日本に招へいし、研修及び指導会を実施しつつ、共同で農業統計人材能力改善プログラムを作成し、農業統計業務を担う人材育成のための基盤作りを支援しました。また、東アジア地域の食料安全保障の強化及び貧困緩和を図るため、「東アジア緊急米備蓄パイロット・プロジェクト」として、インドネシア東ジャワ島での備蓄米の放出及びラオスでの貧困緩和プロジェクトを実施しました。
図表II―25 東アジア地域における日本の援助実績


日・CLV会議

「ASEAN食料安全保障情報システム(AFSIS)」による研修(写真提供:AFSISプロジェクト事務局)
■対中国ODA
日本の対中国ODAは、中国沿海部のインフラ整備、環境対策、保健・医療などの基礎生活分野の改善、人材育成など中国経済の安定的発展に貢献し、中国の改革・開放政策を維持・促進させる上で大きな役割を果たしてきました。このような対中国ODAは、日中経済関係の発展を支えるとともに、日中関係の主要な柱の一つとして重層的な日中関係を支えてきたと評価しうるものです。この点、中国側からも、首脳レベルを含め、様々な機会に謝意が表明されてきました。
近年、中国の経済発展が進む中で、対中国ODAの大部分を占める円借款の必要性は以前より相対的に低下してきています。このような状況を踏まえ、2005年4月の日中外相会談において、日中両国は、2008年の北京オリンピック前までに円借款の新規供与を円満終了することについて共通認識に達しました。現在、その細部について事務レベルでの協議を実施しているところです。
その一方で、中国における環境問題や感染症等は、日本にも直接影響が及びうる地球規模の問題となっており、これらの問題をはじめとして日中両国民が直面する共通課題が数多く存在しています。また、日中関係の健全な発展を促進するという観点からは日中両国民間の相互理解の増進も重要な課題となっています。
このような状況を踏まえ、無償資金協力は現在、[1]環境、感染症等日中両国民が直面する共通の課題の解決に資する分野、[2]日中両国の相互理解、交流の増進に資する分野に絞りこみつつ実施しています。また、技術協力は、人と人との交流を通じ、日本の価値観、文化を中国に伝えるための重要な手段であるので、これらに加えて、市場経済化や国際ルールの順守、良い統治の促進、貧困克服に資する案件を中心に実施しています。
なお、2006年6月の第2回海外経済協力会議では、2005年度分の対中円借款供与を含め、対中経済協力のあり方について議論されました。対中経済協力については、今後とも日中関係全体や中国を巡る情勢を踏まえつつ、日本自身の国益に合致する形で、総合的・戦略的な観点から適切に判断した上で実施する必要があります。
図表II―26 対中国円借款の推移
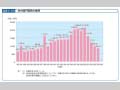

 次頁
次頁