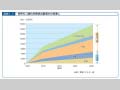本文 > 第I部 > 第2章 > 第3節 > ●開発途上国における温暖化対策への支援
第3節 地球温暖化と環境協力
●開発途上国における温暖化対策への支援
化石燃料の使用をはじめとする人類の活動により排出される二酸化炭素(CO2)、メタンなどの温室効果ガス(GHG:Greenhouse gases)は、地球規模の気候変動を引き起こし、その影響は将来ますます大きくなることが予測されています。既に20世紀の間に地球の平均気温が0.6℃上昇し、日本でも、平均気温が1℃上昇しています。
地球温暖化の原因となるGHGの排出は、その多くが先進国の社会経済活動によるものですが、近年では、中国やインド等の新興経済国の経済成長に伴い排出量が急速に増大しています。今後、開発途上国の排出量が先進国の排出量を上回ると予想されています。したがって、GHG排出を効果的に抑制・削減するためには、先進国だけではなく、開発途上国における取組の強化が不可欠です。
図表I―6 CO2の国別排出量(2003年)

また、地球の平均気温の上昇に伴ない、海水面の上昇とそれに伴なう低地・海岸地域の水没のほか、大雨・洪水・旱魃・サイクロン等の増加など気象パターンの変化、砂漠化の進展、農業への影響(穀倉地帯の高緯度シフトなど)、健康・衛生への影響(マラリアやデング熱などの熱帯型疫病の広域化など)などが予想されています。特にアフリカ等の最貧国や島嶼国など脆弱性の高い開発途上国での被害が懸念されています。このような国々における持続可能な開発そして人間の安全保障を確保していくためには、地球温暖化に伴なう悪影響や被害への対応策(適応策)に対して支援を充実させていくことが必要です。経済成長や貧困削減を達成しながら、GHG排出を抑制するためには、エネルギー効率を向上させたり再生可能エネルギーの導入を進めること、また、適応策として海岸林の保護・造成による沿岸の保護、農業の改良、水資源の確保などの対策が必要です。このような温暖化対策に資する取組は、同時に大気汚染の防止や自然環境の保全、農業生産性の向上といった面でも利益をもたらします。
日本のODAは、環境と開発の両立を実施の原則としており、従来より、環境分野への協力を重視しており、環境分野におけるODAはDAC諸国の中でも最大です。また、日本は京都議定書(注)の取り決めを果たす努力を進めていますが、その一方で、開発途上国が温暖化対策を行うにあたっても、日本のODAによる支援は重要な役割を果たします。こうした日本の協力は国際場裡において、日本が環境問題に対するイニシアティブを発揮する上でも重要な基礎をなすものになります。国際機関を通じた支援はこうした点に強みを持っており、日本は二国間支援と連携して国際機関を通じた支援も行っています。
特に地球温暖化対策に関しては、日本は、これまで国内において公害問題の克服や省エネの推進等の努力によって優れた技術やノウハウを蓄積してきており、この分野で日本の技術や経験を活用した支援を行うことは、国際的にも比較優位のある活動です。これまで日本は、1997年に発表した「京都イニシアティブ」(注1)の下で、開発途上国の地球温暖化への対応能力の向上を支援するため、1998年度から2005年度の間の8年間に15,000人の人材育成を支援するとともに、累計約1兆1,400億円の円借款を省エネルギー、新・再生可能エネルギー、森林の保全・造成等の分野で実施しました。2002年に発表した「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD:Environmental Conservation Initiative for Sustainable Development)」(注2)においても、地球温暖化対策を重要分野の一つとして掲げ、積極的に取り組んでいます。また、2006年1月には、日本として初めてのODAを活用したCDM(Clean Development Mechanism:クリーン開発メカニズム)*1プロジェクトである、エジプトのザファラーナ風力発電計画を日本政府として承認しました。
図表I―7 世界の二酸化炭素排出量増分の見通し
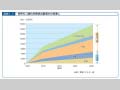
2005年7月、イギリスのグレンイーグルズで開催されたG8サミットにおいては、地球温暖化対策が主要テーマの一つとして取り上げられ、首脳間で「気候変動、クリーン・エネルギー、持続可能な開発行動計画」が合意されました。小泉総理大臣(当時)は、G8の行動計画の実施に貢献するべく、「日本政府の気候変動イニシアティブ」を発表しました。
前述したとおり、貧困や飢餓などの課題を抱える開発途上国や、一般に経済成長を優先しがちな新興経済国において、地球温暖化や環境問題に対して実効ある対策を講ずることは必ずしも容易ではありません。しかしながら、高度成長期に深刻な公害被害が発生し、社会問題に発展した日本自身の経験からも明らかなように、環境対策を怠れば、その代償は甚大なものとなりかねず、また地球環境への影響も生じます。そのため日本は、開発途上国、特に新興経済国における環境問題への対応能力を高めるために人材育成や政策立案、環境監視などの体制整備を支援しています。このような支援の一例として、「環境センター」を拠点とした協力を行うことにより、開発途上国の政策担当者等の環境問題に関する知識や理解を増進し、対応能力の強化を促進しています。現在、タイ、インドネシア、中国、メキシコ、チリ、エジプトの6か国に環境センター設立を支援し、ここに日本の専門家を派遣して、環境に関する技術などを伝えるとともに、日頃から相手国の専門家や政策担当者と継続的な情報交換を行っています。既に、いくつかの環境センターがそれぞれの国の地域協力の拠点となり、近隣諸国へ環境に関する情報や技術を伝えており、その活動の強化が期待されます。

日中友好環境保全センター(写真提供:JICA/吉田勝美)
6か国の中で、最も早く環境センター・プロジェクトを開始したタイでは、日本の無償資金協力及び技術協力を得て、環境研究研修センターを1989年に設置、1992年に開所しました。同センターで収集する環境汚染に関するモニタリング・データは、タイ政府汚染対策局の政策や活動において活用されています。また、タイの環境研究研修センター開所後、10年間の研修受講者5,027名のうち約3分の1が地方公務員であり、地方への情報や技術の普及に貢献しています。さらに同センターには、日本の専門家を講師として派遣し、周辺諸国からの研修員に対する酸性雨対策の研修を行っており東南アジア地域に対して環境に関する情報や技術を伝える拠点としても活発な活動を行っています。

 次頁
次頁