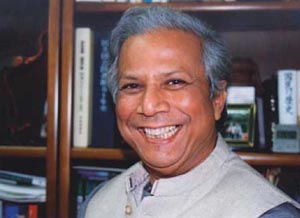column I-4 モハマド・ユヌス氏及びグラミン銀行のノーベル平和賞受賞
2006年のノーベル平和賞は、バングラデシュのモハマド・ユヌス氏と、同氏が設立・総裁を務めるグラミン銀行が受賞することになりました。グラミン銀行は貧困層の自立を支援するため、主に土地を所有していない貧困層を対象に小規模融資(マイクロ・ファイナンス)を行う銀行で、1983年にバングラデシュ政府が大半の株式を有する特殊銀行として創設されました。
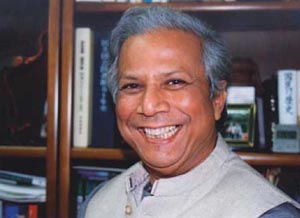
ノーベル平和賞を受賞したモハマド・ユヌス氏(写真提供:グラミン銀行)
マイクロ・ファイナンスは、貧しい人々に担保や保証人無しで小口の融資やサービスを提供し、事業拡大や収入の増加を図ることで人々の自助努力を促す手法です。日本は、貧困削減に対するマイクロ・ファイナンスの有効性に着目した支援を実施してきました。例えば、これまでに草の根・人間の安全保障無償資金協力及び日本NGO支援無償により、国内外合わせて11のNGOに対して合計約94万ドルをクレジットの原資として支援したほか、技術協力では1997年以降、JICAを通じたマイクロ・ファイナンスの制度作りや組織育成のための支援が29件実施されました。また、世界銀行やUNDP等の国際機関を通じた支援も行っています。
こうした一連の支援の中で、円借款による支援の対象となったのがグラミン銀行です。グラミン銀行は、単に融資を行うだけでなく、融資を受ける人が5人1組のグループを形成し、返済計画などについて互いに相談できるような体制を作ったり、容易に借金に頼らないよう預金を習慣づけることを奨励しています。また、銀行員が週に1度農村を訪問して、資金を回収するといった独特の方式を採用しています。こうしたグラミン銀行の提示した新たなモデルは、その有効性が認められ、活動範囲を徐々に広げていきました。日本が円借款によってグラミン銀行の活動を支援したのは、まさにグラミン銀行が第4次計画を策定し、その事業規模を拡大しようとしていた1995年のことです。
日本はこの年、バングラデシュ政府と交換公文を締結し、「農村開発信用事業」として総額29億8,600万円の資金を供与し、第4次計画に協力しました。供与された資金はマイクロ・ファイナンスの原資として、1998年までグラミン銀行を通じて貧困住民に融資され、彼らが主体となって、家屋、トイレ、井戸を作ったり、生産機器を購入するために使われました。例えば、家屋に関する融資は1件当たり25,000タカ(約390ドル)(注)が限度となっています。また、同行の融資対象は94%が女性で、彼女たちが融資を受けた資金を元手に家畜を飼うなどした結果、収入が増加し家庭あるいは社会での女性の地位向上に貢献しています。「農村開発信用事業」の第三者評価によれば、日本の支援により貧困住民の生活環境が改善された他、融資を受けた資金で自営業を営むことができるようになり、経済的自立が促進されたといった効果が確認されています。

返済するために待っている女性たち
その後グラミン銀行は活動を拡大していき、現在ではドナーの支援を必要としない自立した銀行になりました。さらにグラミン銀行のモデルは世界中に広まり、世界の貧困削減に多大な貢献をしたと高く評価されています。日本がかつて協力したユヌス氏とグラミン銀行がノーベル平和賞を受賞したことは、バングラデシュの全ての人々にとって更なる自信と誇りを与えるものとなっています。
注: 2004年度では、バングラデシュの国民一人当たりのGNIは440ドルとなっている。

 次頁
次頁