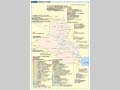本文 > 第II部 > 第2章 > 第2節 > 4.平和の構築 > (1)イラク
4.平和の構築
冷戦後の国際社会においては、民族・宗教・歴史などに根ざす対立が世界各地で顕在化し、地域・国内紛争が多発するようになりました。こうした紛争では、被害者の大多数が子どもを含む一般市民であるほか、通常、大量の難民・避難民が発生し人道問題や人権侵害の問題が発生しています。また、紛争は長年の開発努力の成果を瞬時に失わせ膨大な経済的損失を生み出します。平和と安定は、開発の前提条件であり、国際的な開発目標であるMDGs達成にも、平和の構築が重要です。
国際社会では、紛争要因や紛争形態の変化に伴い、紛争予防・紛争解決のための手段として、国連平和維持活動(PKO:Peacekeeping Operations)や多国籍軍の派遣、及び予防外交や調停などの政治的手段のみならず、紛争後の国づくりも含めた包括的な取組が必要であることが認識されはじめ、平和構築における開発援助の果たす役割が重要視されるようになりました。
このような背景のもと、日本は、2000年7月に「「紛争と開発」に関する日本からの行動-アクション・フロム・ジャパン」を発表し、紛争予防-緊急人道支援-復旧・復興支援-紛争再発防止と本格的な開発支援という一連の紛争のサイクルのあらゆる段階で被害の緩和に貢献するためODAによる包括的な支援を行っていくことを表明しました。小泉総理大臣は、2002年5月、シドニーにおける政策演説において「紛争に苦しむ国々に対して平和の定着や国づくりのための協力を強化し、国際協力の柱とする」とし、ODAを含め、平和構築の分野でより積極的な取組を行っていく決意を表明しました。
これを踏まえ、ODA大綱では、平和の構築を重点課題として掲げ、紛争の予防や緊急人道支援とともに、紛争の終結を促進するための支援から、紛争終結後の平和の定着や国づくりのための支援まで、継ぎ目なく機動的に実施することとしています。ODA大綱を受けた新ODA中期政策では、平和の構築とは、「紛争の発生と再発を予防し、紛争時とその直後に人々が直面する様々な困難を緩和し、そして、その後長期にわたって安定的な発展を達成すること」を目的とするとした上で、支援を実施していく上での具体的なアプローチ及び取組を提示し、人々が「平和の配当」を実感し、社会の平和と安定につながるよう、国際機関や他ドナー、国内の民間部門やNGOと協力して積極的に支援していくことを表明しています。
また、国際的な相互依存関係が深まる中で、世界の平和と安定は日本の安全と繁栄に密接な関係があります。このような認識から、2004年12月に策定された「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」においては、「III 我が国の安全保障の基本方針」の中で、「4 国際社会との協力」として、「国際的な安全保障環境を改善し、我が国の安全と繁栄の確保に資するため、ODAの戦略的な活用を含め外交活動を積極的に推進する」ことが明記されました。
日本は、これまでイラク、アフガニスタン、スーダン、カンボジア、コソボ、東ティモール、パレスチナなどにおいて平和の構築への具体的な取組を行ってきており、今後とも、同分野にODAを活用した取組を積極的に行っていきます。
(1)イラク
日本を含む国際社会は、イラクが中東の安定勢力となるために、テロに屈することなく協調して、イラクにおける平和の定着と国づくりへの支援を進めていく必要があります。イラクが主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建されることは、イラク国民にとって、また、中東及び国際社会の平和と安定にとって極めて重要であり、石油資源の9割近くを中東に依存する日本の国益にも直結しています。
日本は、自衛隊派遣による人的貢献とODAによる支援を「車の両輪」としてイラク復興支援を実施してきています。ODAによる支援については、マドリッドにおける2003年10月のイラク復興国際会議の際に、当面の支援として、電力、教育、水・衛生、保健、雇用などイラク国民の生活基盤の再建及び治安の改善に重点を置いた総額15億ドルの無償資金の供与、また、2007年までの中期的な復興需要に対しては、前述分野に加え電気通信、運輸などのインフラ整備なども視野に入れて、基本的に円借款により、最大35億ドルまでの支援を行うことを表明しました。総額15億ドルの無償資金の供与については、2005年5月までにすべて決定・実施しています。
(イ)イラクに対する二国間支援
日本のイラク政府機関などに対する直接支援は総額約9億ドルに上ります。日本のイラク支援は当初、国際機関経由の支援が中心でしたが、2003年10月に採択された安保理決議1511により、同年7月に発足したイラク統治評議会が、移行期間の間イラクの国家の主権を体現するイラク暫定行政機構の主要な機関であると決定されたことを受け、緊急無償資金協力による直接支援の実施に向けた準備が本格化し、2004年に入り、順次、支援案件が決定されました。

イラクに供与された消防車(写真提供:防衛庁)
治安の改善に貢献するための支援では、イラク内務省に供与した警察車両1,144台及び消防車69台が全国に配備されています(そのうち警察車両40台、消防車6台はサマーワを中心とするムサンナー県に配備)。また、電力分野では、移動式変電設備整備計画、サマーワ大型発電所建設計画、水・衛生分野では、バグダッド市浄水設備整備計画、サマーワ市ゴミ処理機材整備計画、保健・医療分野では、サマーワ総合病院を含む全国11か所の主要病院整備計画、ムサンナー県プライマリー・ヘルス・センター整備計画、通信分野では、南北基幹通信網整備計画及び市外電話交換機整備計画(サマーワも対象)に対して、それぞれ緊急無償資金協力を実施・決定しました。
イラクの債務問題については、2004年11月にパリクラブにおいて債権国とイラクとの間でイラクの公的債務の削減に関する合意(3段階にわたり公的債務を計80%削減)がなされ、一応の決着が見られました。この合意に基づき、日本とイラクの間で債務削減交渉が行われています。
●キャパシティ・ビルディング支援
復興が着実に進展するためには人材育成が重要であるとの考えから、日本は、研修事業を通じて様々な分野において、イラク人の行政官や技術者のキャパシティ・ビルディング支援を行ってきています。2005年7月までに日本国内やエジプトやヨルダンといった周辺国において研修を受けたイラク人は約900人に上ります。
例えばエジプトとの協力では、イラクの医療分野の復興を支援するため、小児科などのニーズの高い分野での人材育成に重点を置き、カイロ大学を中心としたエジプトの医療機関において、2004年3月、10月、2005年3月、7月の4度にわたって、計447名のイラク人医療関係者の研修を行いました。またヨルダンにおける第三国研修では、電力、統計、水資源、上下水道、博物館・遺跡管理、IT教育の分野でヨルダン側の各関係機関の協力を得て、計275名のイラク人関係者が研修を受けました。博物館・遺跡管理の研修はフランス、ドイツ及びUNESCOの協力も得て行われました。
さらに、日本国内での研修を通じてイラクの政治プロセスも支援しています。イラク独立選挙委員会に対する支援として、2004年12月に川崎市選挙管理委員会などの協力を得て第1回目の研修(注1)を実施し、2005年5月には岡山県選挙管理委員会などの協力を得て第2回目の研修(注2)を行いました。また憲法制定支援としては、2005年6月、ハサニー議長をはじめとするイラク移行国民議会各会派から幅広い参加を得て、日本の民主国家への道程における経験や克服してきた課題、日本憲法の基本理念、アジアのイスラム諸国の経験などに関するセミナーを開催しました。

イラクの選挙ポスター。ポスターには「イラクの未来のために選びましょう。民主主義と平等を実現するための婦人の選挙への参加。」と書かれている。
●ムサンナー県における取組
自衛隊が派遣されているサマーワを中心とするムサンナー県では、上記の緊急無償資金協力やNGOを通じた支援を含め、自衛隊の活動と連携して、草の根・人間の安全保障無償資金協力を中心としたODAによる支援が実施されています。草の根・人間の安全保障無償資金協力により、例えば、浄水機6基、給水・貯水タンク311台、給水車38台が供与され、日量3,000tの飲料水が供給されており、また、総延長55kmの生活道路の修復が実施されています。自衛隊との連携では、ODAにより供与された医療機材の使用方法を自衛隊医務官が指導したり、自衛隊が砂利舗装した道路をODAによりアスファルト舗装したりするなどの事例が挙げられます。
(ロ)NGOを通じた支援
日本はイラクの人道・復興支援のためNGOを通じた支援も行っており、その総額は約2,500万ドルに上ります。2004年3月にはイラク事業に限定して17億円をジャパン・プラットフォームに拠出しました。ジャパン・プラットフォーム傘下のNGOが2004年以降に行った事業としては、イラク北部地域における医療・教育施設などの応急修復、バグダッド市内の小学校、下水道設備の応急修復、ニネヴェ県における初等教育施設の水・衛生設備修復事業などがあげられます。ムサンナー県では、日本のNGOを通じて、サマーワ母子病院に対して新生児保育器などの医療機材を供与したほか、給水車をレンタルして水道管による給水を得られない地域の住民に給水するフランスのNGOによる活動を支援しています。

緊急物資を受け取るイラク国内避難民(写真提供:JPF/WVJ)
(ハ)国際機関を通じた支援・国際協調の促進
日本は、イラク復興支援にあたっては国際協調の促進が重要であるとの考えから、上記マドリッド会議で設立が合意されたイラク復興信託基金への4億9,000万ドル(注3)の拠出を通じて、国連機関や世界銀行が実施する各種復興事業を支援しています。具体的には、UNDPの中央配電所や4発電所の復旧事業、国連人間居住計画(UN-HABITAT:United Nations Human Settlements Programme)による教育施設再建事業や生活インフラ・コミュニティ再建事業、UNESCOによる文化遺産管理事業、国連環境計画(UNEP:United Nations Environmental Programme)によるイラク政府環境部門の人材育成事業やイラク南部湿原環境保全事業などが挙げられます。
また、日本は同信託基金に対する最大の拠出国として同信託基金のドナー委員会の議長を務めてきました。ドナー委員会は、2004年2月にアブダビ、5月にドーハで開催されたのに続き、10月に第3回会合を東京で開催し、初日の拡大会合には53か国及び4機関が参加しました。東京会合ではイラク暫定政府が2005年から2007年の「国家開発戦略」を発表し、経済開発についてはマドリッド会議で表明した支援を各ドナーが早急に実施する必要性について確認し、政治プロセスについてはイラク暫定政府から治安改善及び全国規模での選挙の予定通りの実施を行うとの強い決意が示されました。また、日本の4,000万ドルをはじめとして、2005年1月の選挙実施のための資金協力が表明されました。
イラク復興信託基金への拠出以外では、日本は約1億ドルの国際機関経由の支援を行っています。具体的には、UNDPを通じたウンム・カスル港の浚渫事業、中央配電所の緊急復旧事業、UN-HABITATを通じた学校再建事業、コミュニティ再建事業、UNICEFを通じた学校修復、学用品供与などを行うイラク初等教育再生計画、UNESCOを通じた文化遺産保存・修復などが挙げられます。また、ODAは雇用創出にも貢献しており、ムサンナー県では、UNDPの雇用創出事業、UN-HABITATの学校再建事業や住宅再建事業を支援することによって、2005年6月時点で延べ60万人近い雇用が創出されました。
2005年4月のイラク移行政府の発足を受けた国際協調促進の動きとして、2005年6月、イラク国際会議がブラッセルで開催され、日本からは町村外務大臣が出席して、経済復興セッションの共同議長を務めました。この会議は、政治プロセス、経済問題と復興、治安と法の支配をテーマとして開催されました。この会議の結果を受け、復興支援に関する国際的な取組を具体的に協議することに焦点をあて、7月には第4回イラク復興信託基金ドナー委員会がヨルダンで開催されました。日本は、イラク復興のための国際協調の促進に引き続き努力していきます。

UN-HABITATを通じた学校建設事業(写真提供:UN-HABITAT)
(ニ)今後の支援
イラクでは、2005年1月に実施された国民議会選挙の結果を受け、4月28日に移行政府が発足しましたが、その復興は道半ばにあります。ODAによる支援では、15億ドルの無償資金による当面の支援がすべて実施・決定されたことを受け、日本のイラク復興支援は、最大35億ドルの、基本的に円借款による中期的な復興需要に対する支援を進める段階に移りつつあります。日本政府は、イラク政府との円借款による支援ニーズについて協議を進めているほか、JICA、JBIC、JETROによる各種調査を実施し、案件発掘や案件の精査を行い、無償資金協力から切れ目のない支援が実施できるよう準備を進めています。また、資金協力との一層の連携を図りつつ、研修を通じたキャパシティ・ビルディング支援も継続していきます。
今後とも日本は、イラク人自身による国家再建の努力への支援を積極的に進めていきます。
図表II-21 イラク復興信託基金(IRFFI)を通じた日本のイラク支援

図表II-22 日本の対イラク支援
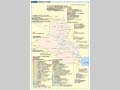

 次頁
次頁