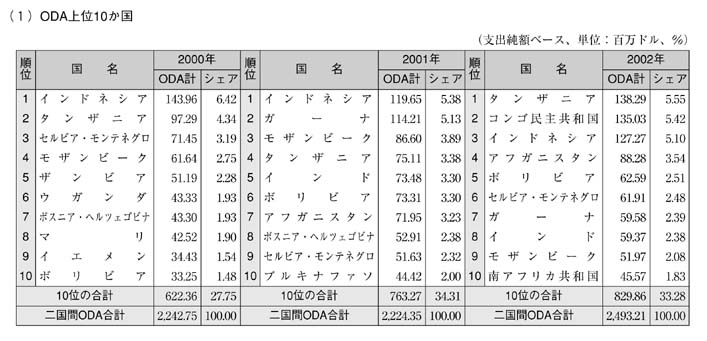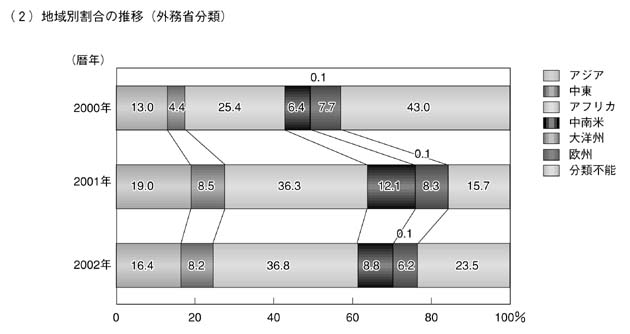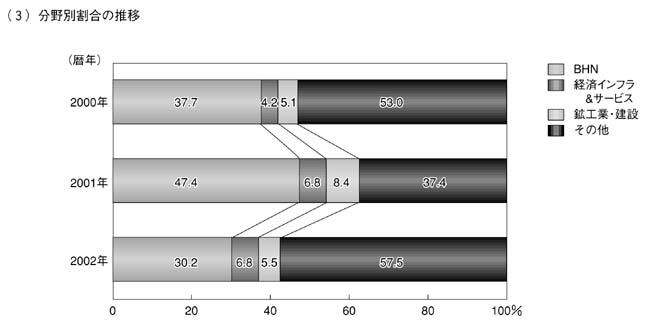資料編 > 第4章 > 第2節 > 7 オランダ
7 オランダ
(1)援助政策等
オランダは貧困削減を援助政策の主要目的としている。国際的取り決めではミレニアム開発目標(MDGs)を自国援助政策のガイドラインと位置づけ、2015年までの極度の貧困の半減、初等教育への子女の参加確保のテーマを特に重視している。
内閣においては、これまで外務大臣とは別個に無任所の開発担当大臣が任命されてきた。ODAの規模はGNP比0.8%が政策目標として設定されており、2004年の緊縮財政の下でも右政策目標は堅持されている。
また、援助実施の重点項目として以下を掲げている。
[1]政策の統合性:援助政策と外交、政治対話、安全保障、貿易等の他の政策との統合性を追求。この関連でオランダ政府は平和、安全保障、援助が交錯する分野で、緊急な紛争が発生する地域に迅速かつ柔軟な支援を行うことを可能とする「安定基金」を創設し、右基金は本年初めから運営が開始された。同基金は外務大臣と開発協力大臣が管理。ODA予算と通常の外交予算を利用することができる。
[2]地域アプローチ:紛争予防・平和構築における地域毎アプローチと同様に、国毎ではなく地域別の援助政策を追求。オランダは、アフリカの角、大湖地域、西バルカン地域で地域アプローチを実施している。
[3]アフリカ重視:外交政策一般におけるアフリカ重視と同一歩調。NEPAD、ECOWAS等の平和と開発のためのアフリカのイニシアティブを強く支援している。オランダの二国間援助予算の少なくとも50%がアフリカに向けられている。
[4]民間部門の重要性:援助国及び被援助国の市民社会、企業が果たす役割を重視。途上国の雇用の確保、産業、投資、輸出、環境等を促進するプログラムを実施。
[5]一貫性:欧州連合の枠内で、援助政策と農業政策、貿易政策等との一貫性を追求し、途上国からの財、サービス等の国際市場へのより良いアクセスを促進する。
[6]テーマ別の優先順位付与:オランダは援助の優先順位の高いテーマとして、教育、生殖保健、エイズ予防、環境と水を掲げ、2015年までにそれぞれのテーマのMDGs達成のためどれだけ支出するかを事前に明示する予定。
オランダは、限られた資源をより有効に利用するとの観点から長期的な二国間援助の対象国を限定する政策をとっている。現在、現政権の下作成された「構造的な二国間援助政策」に則り、統治、社会・経済政策、貧困レベル、援助の需要等の基準に基づき選ばれた36か国(パートナー国・リスト)、並びに民間部門に焦点を当てた援助を行う国31か国(ビジネス部門リスト(但し31か国のうち20か国はパートナー国である。))を対象に二国間援助が実施されている。
オランダの経済協力実績は、2003年には40億5,900万ドル(DAC報告ベース;暫定値)であり、金額面で世界第6位の援助国となっている。ODA対GDP比では0.81%の規模であり、OECD諸国内ではMDGsで設定された0.7%の目標を達成する数少ない国の1つである。さらにNGOによる援助活動も活発であり、経済協力予算の約10%はNGOを通じて実施されている。
(2)実施体制
外務省で開発援助に携わる職員の数は約1,050人(2004年。在外公館に勤務する職員を含む)であり、同省には外務大臣に加えて、援助政策専任の開発協力大臣ポストが設置されている。
援助政策の基本的枠組みは外務省が決定し、その他、他省との協力を要すべき主要な政策は閣議によって決定される。閣議の準備会合として、事務方レベルの「国際協力問題関係各省連絡会議」(議長は外務省国際協力総局長)及び大臣レベルの「関係大臣会合」(議長は開発協力大臣)が開催される。参考として、ODA予算の約9割が外務・財務の両省に計上され、残り1割が経済省を含む他省庁に分散計上されている。
外務省は援助政策の実施に関し主要な責任を有し、援助実施は3つの主要な形態、つまり、二国間援助(大体が政府間のセクター別援助)、多数国間援助(国連等の国際機関)、民間機関(NGO)を通じて行われる。
経済援助実施上の手続代行機関として、オランダ途上国投資銀行(NIO:オランダ国立投資銀行(NIB)の100%出資機関)があり、二国間援助すなわち贈与の支出を政府に代行して行っている。
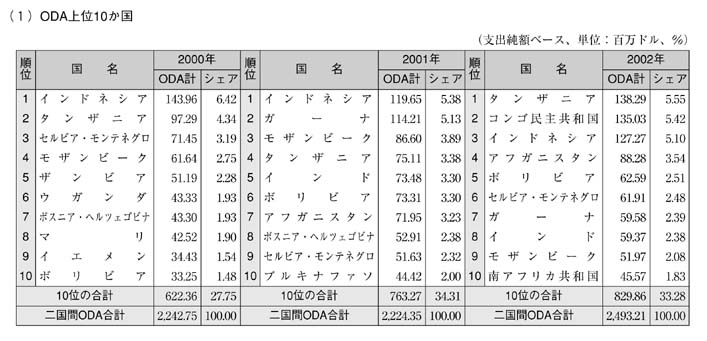
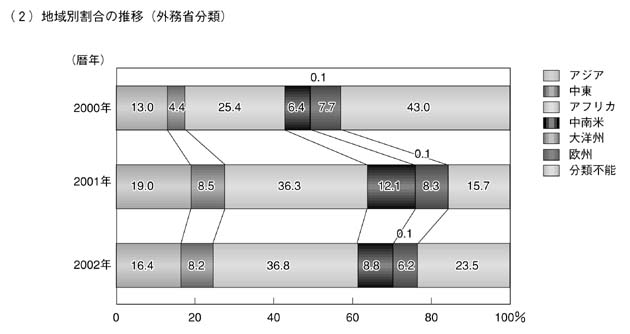
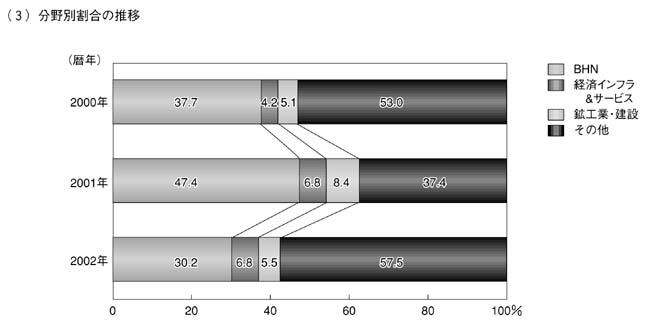

 次頁
次頁