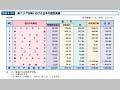本編 > 第II部 > 第2章 > 第4節 > 1.東アジア地域
第4節 地域別の取組状況
新しいODA大綱においては、日本と密接な関係を有し、日本の安全と繁栄に大きな影響を及ぼし得るアジアを重点地域としつつ、その他の地域についても各地域の援助需要、発展状況に留意しつつ、重点化を図ることとしています。以下では、各地域別の日本のODAの取組状況について説明します。
1.東アジア地域
日本の東アジア地域に対する2003年の二国間ODAは、約18億9,389万ドルで、二国間ODA全体に占める割合は31.5%です。
アジアは、日本が伝統的に外交の重点としてきた地域であり、ODA大綱も、アジアを重点地域としています。とりわけ東アジア諸国は日本と政治・経済・文化等あらゆる面において緊密な相互依存関係にあり、東アジアの発展と安定は日本の安全と繁栄にとって重要な意義を有しています。日本は、東アジア地域に対して、ODAによる経済インフラ基盤整備等を進めるとともに、民間投資や貿易の活性化を図るなど、ODAと投資・貿易を有機的に連携させた経済協力を進めることにより、同地域の目覚ましい発展に貢献してきました。
東アジアにおいては、高い経済成長を遂げ、すでに韓国やシンガポールのように被援助国から援助国へ移行した国も現れている一方で、カンボジアやラオスなどの後発開発途上国が依然として存在しています。また、中国のように、近年著しい経済成長を成し遂げつつも、国内に様々な問題を抱えている国もあります。日本は、このような各国の経済社会状況の多様性、援助需要の変化等に十分留意しつつ、援助を行っています。
ASEANとの関係では、加盟国の増加に伴い顕在化したASEAN域内の格差の是正とともに、民間貿易・投資を円滑化するための制度整備、経済社会基盤の支援、人材育成、環境保全の推進、経済構造改革のための政策形成、地方分権化支援とガバナンス支援、テロ・海賊その他国境を越える問題への支援等の分野において、ODAを積極的に活用して協力を実施しています。その際、東アジアにおける経済連携強化等にも十分配慮しています。
ASEAN域内においては、国ごとの経済・社会状況、開発状況を踏まえつつ、経済・金融危機からの完全な脱却と域内の経済成長による貧困削減等を目標としつつ協力を行ってきています。特に、2003年12月に東京で開催された日ASEAN特別首脳会議において、日本は、貧困削減と域内格差是正のための協力として、ASEAN統合イニシアティブ(IAI:Initiative for ASEAN Integration)*1や東アセアン成長地域(BIMP-EAGA:Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area)*2 等への支援に加え、メコン地域開発に対し今後3年間で15億ドルに達することが見込まれることを表明しました。また、人材育成では今後3年間で15億ドル以上の協力が見込まれること、約4万人規模の人的交流プログラムを予定していることを表明しました。また、比較的開発が遅れているASEAN新規加盟国(注)に対しては、市場経済への移行のための支援を実施するとともに、貧困削減、基礎生活分野支援といった社会開発分野における援助を実施しているほか、道路、配電網など各種の経済インフラ基盤整備支援も実施しました。インドネシア、フィリピン、タイ、マレーシアに対しては、主に円借款を通じた経済・社会インフラ基盤整備を中心に引き続き支援しており、域内の物流、人的交流、情報の流通等はスムーズになりつつあります。さらに、日本は、二国間援助とともに、ASEAN統合の強化の観点から、域内協力やシンガポール、タイ、フィリピン各国とのパートナーシップ・プログラム*1に基づく南南協力を積極的に推進しています。また、アジア・アフリカ協力の促進も重視しており、例えば、アフリカ諸国を対象としてアジアにおける第三国研修を行い、生産性向上などの支援を実施しています。
図表II-29 東アジア地域における日本の援助実績
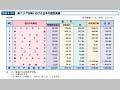

障害者施設「さをりクリエイティブセンター」を訪問する阿部前外務副大臣(「タイ障害者創造活動と就労機会開発および山岳民族の手紡糸ほか商品開発計画」:タイ)
東ティモールについては、独立して間もない国であり、経済社会開発面で多くの課題を抱えています。日本は同国の安定と自立可能な国家となるための自助努力を支援しており、2002年5月の支援国会合において、3年間で6,000万ドルの支援を表明しました。2003年度は、UNICEFに対し1億6,100万円を拠出し、東ティモールの乳幼児・妊産婦を対象とする保健医療サービスの向上を目的とした「母子保健改善計画」等を行っています。
モンゴルについては、これまでに同国の民主化及び市場経済化を積極的に支援してきており、人材育成などを行っています。また、夏の干ばつや冬の雪害等、気象災害の被害を最小限に抑えるために、「気象情報ネットワーク改善計画」において老朽化が著しい地方気象観測所の機材更新及び通信ネットワークの改善を支援しています。事前に的確な自然災害対策を講じることにより、モンゴルにおける自然災害の被害軽減に寄与することが期待されています。
また、東アジアの開発に関する日本の取組として、東アジア開発イニシアティブ(IDEA:Initiative for Development in East Asia)があげられます。日本の提唱により2002年8月に東京で開催された閣僚会合のフォローアップとして、政府は2003年8月に福岡県、福岡市の協力を得て日本国際問題研究所とともに東アジア開発イニシアティブ福岡シンポジウムを開催しました。このシンポジウムには、ASEAN各国、中国、韓国、アフリカ(ガーナ)等から有識者などの参加を得て、東アジア開発モデルの多様性、国内経済・社会改革や東アジア地域協力の拡充の必要性、アジアの経験のアフリカでの活用といった課題について学術的な観点から議論がなされました。
■対中国ODA
近年、中国は沿海部を中心に急速な経済発展を遂げていますが、深刻な貧困問題をはじめ、環境問題や感染症などの問題を抱えていることも事実です。中国が直面するこのような問題を解決し、更に開かれ、安定した社会となり、国際社会の一員としての責任を一層果たしていくようになることは日本の国益に叶っており、このような観点から、ODAも引き続き重要な役割を果たしています。
他方、中国に対する経済協力を考える際には、中国の経済成長に伴う援助需要の変化や対中国ODAに対する日本国内の厳しい見方等も踏まえる必要があります。
このような考えの下、政府は、2001年10月に策定された対中国経済協力計画を策定し、対中国ODAを大幅に見直してきています。その主な方針は次の通りです。
[1]従来重点分野の一つとされてきた沿岸部の経済インフラは基本的に中国自らが実施することとし、環境保全、人材育成、内陸部の貧困克服等を重視し、また日中間の相互理解の増進により資するよう注意を払っています。
[2]円借款については、多年度方式から単年度方式へ転換し、円借款を含む対中国ODAの規模については、従来の支援額を所与とせず、日本の国益の観点も加味しつつ、案件積み上げ方式により供与総額を決定することとしています。
その結果、対中国ODAの太宗を占める円借款の2003年度供与額は約967億円(交換公文ベース)となりました。これは2000年度と比べて約55%減の水準です。また案件の対象分野も2003年度には環境分野と人材育成案件に絞られており、さらに、個々の案件においても、日中両国の地方や学術研究機関間の交流と連携した案件となるよう留意するなど日中互恵的な案件の実施に留意しています。
政府としては、今後ともODA大綱と対中国経済協力計画にのっとり、日中双方にとって互恵的な案件の形成と実施に努めることを通じて、日本にとっても意義のある対中国ODAを実施していく考えです。
図表II-30 対中国円借款の推移


 次頁
次頁