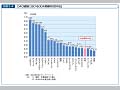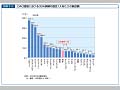本編 > 第II部 > 第1章 実績から見た日本のODA
第II部 2003年度のODA実績



第II部
Summary
第II部では、第1章において、2003年の日本のODA実績をDAC統計に基づいて概観し、第2章において、2003年度のODAの実施状況をODA大綱に沿った形で説明します。
2003年(暦年)の日本のODA実績は、対前年比4.3%減の約88億7,966万ドルとなり、前年に引き続きDAC諸国中、米国に次いで第2位の援助国となりました。
2003年8月、政府は、国内外の状況の変化を踏まえ、ODAを機動的、戦略的に活用するとともに、その効率性を高めていくため、ODA大綱を11年振りに改定しました。日本のODAは、現在、新ODA大綱を踏まえた形で展開しています。同大綱において、大綱の実施状況については、ODA白書において明らかにするとされたことを踏まえ、今次ODA白書では、2003年度のODA実績をODA大綱の構成に沿った形で報告しています。
今次白書では、ODA大綱の実施状況としてODA改革の着実な実施に向けた各種の取組を取り上げています。具体的には、国別援助計画の策定と現地ODAタスクフォースの活動を通じた「国別アプローチの強化」、これまでの取組を検証するとともに新たな中期政策の策定に向けての参考とするための「中期政策の評価と見直し」、ODA大綱に掲げられている環境社会面での配慮を一層強化するための「JICAの環境社会配慮ガイドライン改定」、無償資金協力に関する審査の視点及びその手順を示すための「無償資金協力審査ガイドラインの作成」、スキーム別の編成から地域別重視の体制へと移行する「外務省の機構改革」等、様々な改革努力が続けられています。
新しいODA大綱では、新たに「人間の安全保障」の視点が基本方針に盛り込まれましたが、日本はその理念の普及と実践のため積極的に取り組んでいます。近年、日本が積極的な役割を果たしている平和の構築も同様に重点課題の一つとして新たに盛り込まれましたが、日本は、イラク、アフガニスタン、スリランカにおける復興支援等を積極的に支援しています。また、貧困削減、持続的成長、地球的規模の問題への取組といった重点課題についても引き続き積極的な取組を行っています。
地域別の取組については、2003年度には、日・ASEAN特別首脳会議、TICADIII、太平洋諸島フォーラム(PIF)といった首脳レベルの会合を日本で開催し、これら諸国への支援を表明するなど、具体的な取組を推進しています。
さらに、ODA政策を立案実施する過程において、政府全体としての一体性と一貫性の確保、NGOをはじめとする内外の援助関係者との連携の強化、途上国との政策協議の強化、国民参加の拡大、評価の充実等についても、ODA大綱に沿って取組が進められています。
第1章 実績から見た日本のODA

円借款事業の建設契約にHIV/AIDS予防条項を盛り込んだ「シハヌークビル港緊急リハビリ事業」(カンボジア)。同事業実施にあたり、集まってくる労働者によりHIV感染者の増加が懸念され、予防対策に取り組んでいる。
(写真提供:国際協力銀行(JBIC))
Point
●2003年(暦年)のODA実績は、2000年から3年連続で減少。前年に引き続き世界第2位の援助国となる。
●政府貸付等の実績(貸出額から返済額を控除した支出純額ベース)は、過去の円借款の返済額が大きく積み上がっていることも反映して大幅減少。
2003年の日本のODA実績(注)は、二国間ODA(Official Development Assistance:政府開発援助)が対前年比5.4%減の約63億3,423万ドル、国際機関を通じたODAが対前年比1.7%減の約25億4,543万ドルで、ODA全体では、対前年比4.3%減の約88億7,966万ドル(円ベースでは、対前年比11.4%減の約1兆292億円)となりました。このうち、二国間ODAがODA全体の約7割を占め、国際機関を通じたODAが約3割を占めており、二国間ODAが中心であることが分かります。二国間ODAについては一般に、途上国との協議を経て策定した援助プロジェクトを実施することなどにより、人と人とのつながりによる日本と被援助国との友好関係の増進にも貢献することが期待されています。一方で、国際機関を通じたODAにも国際機関の専門的知見、政治的中立性、政府ベースの援助が届きにくい国・地域への支援が可能であるなどのメリットがあり、日本は国際機関とも連携しながら、柔軟な対応をとってきています。
二国間ODAを援助形態別に見ると、贈与では、無償資金協力が対前年比1.2%減の約16億9,572万ドル(二国間ODA全体の26.8%)及び技術協力が対前年比3.4%増の約27億4,738万ドル(同43.4%)で、政府貸付等は対前年比18.5%減の約18億9,113万ドル(同29.9%)となりました。これら援助形態についても、それぞれの援助形態ごとに特徴があり、日本は、相手国の実情や援助需要なども勘案しつつ、これら様々な援助形態を、バランスのとれた形で採用してきています。日本は、従来より技術協力を通じた人づくりや制度づくりを重視して支援してきており、このことが2003年度の実績にも反映されています。また、政府貸付等の実績が大幅に減少しているのは、貸付については、貸出額から返済額を控除した支出純額ベースの数字となっており、アジアを中心とした途上国からの過去の円借款についての返済額が大きく積み上がっていることも反映しています。
二国間ODAの地域別実績では、アジアへの援助が対前年比21.0%減の約32億2,609万ドルとなり、二国間ODAの約53.6%を占めたほか、アフリカは対前年比9.2%減の約5億2,998万ドル(二国間ODAの8.8%)、中東は対前年比99.5%増の約4億1,648万ドル(同6.9%)、中南米は対前年比21.7%減の約4億6,387万ドル(同7.7%)、大洋州は対前年比44.2%減の約5,214万ドル(同0.9%)、欧州は対前年比80.2%増の約2億1,547万ドル(同3.6%)となりました。このように日本の二国間ODAの約5割がアジアに振り向けられています。長い歴史的スパンで見れば、アジアの発展による近年の援助需要の変化等を背景にアジアへの経済協力の重点的配分の傾向は徐々に弱まっていますが、今日でも、引き続き日本との関係が深いアジアへの支援が最も多くを占めています。
図表II-1 2003年の日本のODA実績

図表II-2 日本の二国間ODAの形態別実績

図表II-3 日本の二国間ODAの地域別実績

図表II-4 DAC諸国におけるODA実績の対GNI比
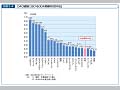
図表II-5 DAC諸国におけるODA実績の国民1人あたりの負担額
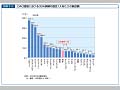
図表II-6 日本のODA実績と対GNI比率の推移

図表II-7 日本の二国間援助に占めるLDC向け援助額

図表II-8 日本の二国間援助に占めるLDC向け贈与の割合

図表II-9 日本のODA予算の推移・他の主要経費の推移


 次頁
次頁