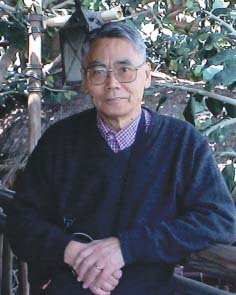columnI-12 冷戦後の世界経済のグローバル化と市民社会の台頭:国際潮流から見た日本のODA~成蹊大学名誉教授 廣野良吉 先生
日本内外でごく最近まで、日本のODAには理念が欠如しているとか、商業主義的とか、成果が上がっていないとか、不透明とか、もろもろの批判が寄せられてきた。しかし、1960年代から1970年代における日本のODAはともかくとして、1980年代になるとこれらの批判は当たらなくなった。すなわち、一方で大幅な国際収支の黒字の還流が国際的に要請され、他方では途上国の食糧増産、工業化や経済成長を円滑に促進する手段としてのインフラ整備と人づくりが急務となってきたために、日本はODAを計画的に拡充したのである。1990年代に入って冷戦体制が終結すると、主要援助国のODAは年々減少した。他方、多数の途上国では紛争の激化や軍備の拡大がみられ、貧困の削減、平和構築、民主的ガバナンス、「人間の安全保障」の確保が緊急の課題となってきた。このような大きな世界の変化の中で、日本のODA政策は如何に変遷してきたのであろうか。
第一は、日本のODAの目標ないし優先順位の変化である。世界的には、人道的介入が世界のいたるところで実施されている中で、日本は戦後、平和憲法の下で経済・社会・環境・文化協力等に徹して、軍事協力には一切関与してこなかった。近年漸く日本でも世界の平和構築のために、その持つ資金や技術や人員の提供について国民の間に冷静に議論する下地が出てきたといってよいであろう。
第二は、日本のODA対象の変化である。世界的には、一方では経済開発から社会開発への転換があり、他方では途上国の国内問題への焦点から、人口、環境等地球的課題への対処が急増してきている。日本は途上国の女性支援(WID)イニシアティブ(1995年)、21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)(1997年)、沖縄感染症対策イニシアティブ(2000年)等を矢継ぎ早に発表してその実行に努めてきたが、その成果については多くの課題を残している。その根本的要因は、これら新分野の専門家の不足と、他の主要援助国や国際機関等との政策・実施レベルでの連携がうまく進んでいないことによる。これには、国際機関に邦人専門職員が少ないことも影響している。
第三は、日本の国際開発協力枠組みの変化である。世界的には資金・技術の移転を重視した従来型のプロジェクト援助から国別援助計画の策定、途上国の政策支援、プログラム支援、人づくり、体制づくりという新しい国際協力の方向へ転化してきている中で、日本のODA政策は、自国の戦後経済復興の経験に基づき、早くから一貫して「自助努力」をうたい、途上国の開発政策・戦略を重視してきた。これは途上国の主体性こそが開発を促進する前提条件であるということであり、そこでは途上国の開発政策の樹立・実施・監視・評価のための人的・制度的能力の形成・増進が重視されている。
第四は、日本のODAも成果重視に変わってきたことである。従来からGNPの0.7%達成というような援助量拡大が世界的に重視されてきたが、近年では援助効果向上のための体制整備と援助国・機関間での協力関係の構築への転換が叫ばれている。この傾向は、1990年代後半から援助の量的拡大が一層困難になってきた日本では特に顕著であり、ODA評価を一層重要視するようになってきた。さらに、援助国・機関間の連携・協力を密にする一環として、援助国間で特定プログラム援助資金を共同化することも一案として提唱されており、現実に感染症といったグローバルな問題や平和構築に関し、一部途上国を対象に実験中である。また、社会開発、環境保全、難民・国内避難民救済等の支援が顕著になるにつれて、国内・国際NGO、被援助国内でのNGOとの連携・協力なくしては、効果的な国際協力が困難であるという認識が、二国間・多国間協力でもなされるようになってきたことは歓迎すべきことである。
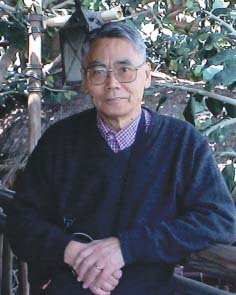
廣野良吉 先生

 次頁
次頁