米国提案の要旨
(●:10月に発表された内容、○:米国の従来からの提案内容)
(1)排出抑制
- 削減のための数量目的(QELROs)
- 各先進締約国は過去の排出実績をもとに、所与の期間(バジェット期間)に個別に「排出バジェット」を割り当てられる。
- 2008年~2012年(第1バジェット)における排出量を1990年レベルに戻す。
- 2013年~2017年(第2バジェット)における排出量は1990年レベル以下とし、その後も更なる削減のために努力する。
- 当該バジェット期間に割り当てられた排出バジェットが余れば次のバジェット期間に使用するために繰り越すことができ、足りなければ次の期間の自らの排出バジェットから利息つきで前借りすることが出来る。
- 数量目的の対象は、ネットアプローチ(排出量-吸収量)、バスケットアプローチ(すべての温室効果ガスを合算。合算のための温室効果指数(GWP)、計測方法については、第一回の議定書の締約国会議で決定)を採用。
- 排出権取引(International Emissions Trading:排出バジェットを各国間で売買する制度)を導入する。
- 共同実施(Joint Implementation:条約締約国間で温室効果ガスの排出抑制
- 削減措置を共同で行うこと)の成果を取得することを認める。
- 急速に成長しつつある国々が自発的に排出抑制
- 削減のための数量目的を約束することを奨励するため、新たな締約国のカテゴリー(附属書B)を提案。
(2)報告及び遵守
- 各国は排出量を正確に計測し、遵守を行い、実施を確実にするための国内制度を設け、これらに関する情報を事務局に提出する。
- 情報は専門家チームによりレビューされる。締約国の会合は不遵守に対処する制度を運用する。また、不遵守国に勧告を行う。実施委員会を設けることが出来る。
(3)条約4条1項の義務の強化
- 各締約国は排出目録を毎年事務局に提出する。
- 各締約国は、温室効果ガスの抑制のための政策
- 措置について国レベルでの計画を作成する。(政策
- 措置の分野はリストに示されている)
- 各締約国は、条約に規定された報告の一部として政策
- 措置の実施状況を事務局に報告する
- 締約国は情報をレビューするプロセスを確立する。
(4)途上国への数値目標の設定
- すべての締約国が温室効果ガスの数量化された排出義務を持つよう、(2005年)までに拘束力ある規定を採用する。(evolution)
[排出バジェットの計算法]
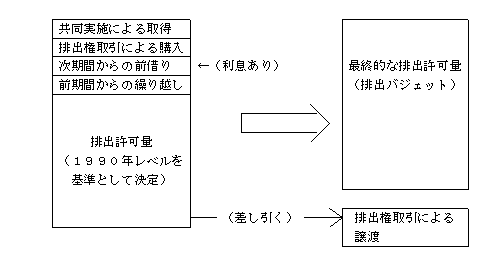
|