|
|
|
第1節 平和と安定の確保 |
|
|
|
冷戦後の国際社会には、様々な流動的要素が存在している。また、日本を取り巻くアジア太平洋地域は、政治的・社会的な安定性を高めてきているものの、核戦力を含む大規模な軍事力の存在や、多数の国による軍事力の拡充・近代化、朝鮮半島における緊張の継続等、依然として不透明・不確実な要素が残されている。
(ロ)防衛力の整備
(ハ)国際の平和と安定を確保するための外交努力
(A)日米安全保障体制の意義 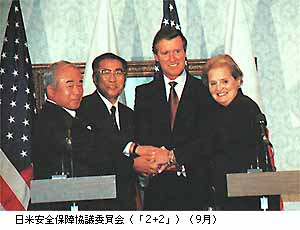 (B)新たな日米防衛協力のための指針の公表
(B)新たな日米防衛協力のための指針の公表「共同宣言」では、日米両国間に既に構築されている緊密な協力関係を増進するため、78年に作成された日米防衛協力のための指針(「指針」)の見直しを開始することが表明された。日米両国政府は、96年6月、「指針」の見直しを行うため、日米安全保障協議委員会(SCC、「2+2」)の下部機構である防衛協力小委員会(SDC)を改組した。SDC等における約1年余の緊密な協議の過程においては、透明性の確保が重視され、96年9月に「日米防衛協力のための指針の見直しの進捗状況報告」が、97年6月には「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間とりまとめ」が公表された。日米間の精力的な作業の結果、97年9月23日(現地時間)にニュー・ヨークで開催されたSCCにおいて、新たな「指針」が公表された。 新たな「指針」は、日米防衛協力の大枠及び方向性を示すものであり、いずれの政府にも立法上、予算上又は行政上の措置をとることを義務づけるものでない。新たな「指針」及びその下での取組は、日本の憲法上の制約の範囲内において、日米安保条約の権利・義務や日米同盟関係の基本的枠組みを変更せずに行われるものであり、また、国際法の基本原則及び関連する国際約束に合致するものである。新たな「指針」は、以上のような基本的な前提及び考え方の下、(イ)平素から行う協力、(ロ)日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等、(ハ)日本周辺地域における事態で日本の平和及び安全に重要な影響を与える場合(「周辺事態」)の協力、について、その基本的な考え方や具体的なあり方を述べている。特に、「周辺事態」における協力については、非戦闘員退避活動や後方地域支援等の機能及び分野における協力の具体的な項目例が新たな「指針」の別表に示されている。新たな「指針」については、関心を有する諸国に対し日米両国から既に説明を行っており、おおむね好意的な反応を得ているが、今後もその趣旨や目的について内外に対し必要に応じ説明していくことが重要である。 9月29日には新たな「指針」について閣議報告が行われ、その際、その実効性確保について閣議決定が行われた。現在、閣議決定の趣旨を踏まえ、法的側面を含めた国内体制の構築に向けて検討が進められている。
(C)技術・装備面での日米の防衛協力
(D)沖縄県における米軍施設・区域の扱い
|
|
|
|
|
冷戦終結後も、核兵器を始め化学兵器及び生物兵器等の大量破壊兵器の拡散の危険は依然として存在しており、これらの軍備管理・軍縮及び不拡散体制の強化が国際社会全体が取り組むべき課題となっている。 (A)核兵器及びその他の大量破壊兵器 [核軍縮]
日本は、核兵器のない世界の実現を目指して現実的な核軍縮措置を着実に積み重ねる努力を行っている。 大量破壊兵器、ミサイル、通常兵器及び関連物資等の軍縮・不拡散体制の概要 [核兵器の究極的廃絶に向けた核軍縮に関する決議] 日本は、94年以来、国連総会に「核兵器の究極的廃絶に向けた核軍縮に関する決議」を提出してきたが、97年の第52回総会でも引き続きこれを提出し、賛成156、反対0、棄権10の圧倒的多数を得て採択された。この決議は、この1年間の核軍縮・不拡散分野における動きを踏まえた上で、96年の決議を更に進め、核兵器の廃棄に関する努力を歓迎するとともに、その結果生じる核分裂性物質の安全かつ効果的な管理の重要性を指摘している。特に97年の総会では、94年以来初めてすべての核兵器国(米、英、露、仏、中)の賛成を得たが、この決議がこうした広い支持を得て採択されたことは、核兵器のない世界を目指して現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であるとの日本の考えが、広く国際社会に受け入れられていることを示すものである。 [非核地帯をめぐる動き] 3月27日、カンボディア及びシンガポールが「東南アジア非核兵器地帯条約(95年署名)」の批准書を寄託し、条約の発効に必要な7ヶ国の批准書の寄託が実現したことから同日、同条約が発効した。しかし、核兵器国による同条約議定書への署名の見通しは立っていない。 [米露間の核軍縮と日本の貢献]
現在、第1次戦略兵器削減条約(STARTⅠ)に基づき、米露それぞれの戦略核弾頭の配備数を2001年までに6000以下にするための作業が進んでいる。これを更に2007年までに3000ないし3500に削減しようとする第2次戦略兵器削減条約(STARTII)は、ロシアが未批准であるため、これまでのところ発効していないが、97年3月に米露両国は、STARTIIが発効次第、各々の戦略核弾頭の配備数を2007年までに2000ないし2500に削減する等の内容を含むSTARTIIIの交渉に入ることについて、共通の理解に達した。
化学兵器の廃絶を目指す化学兵器禁止条約(CWC)は、4月29日に発効した。これを受け、5月にはハーグ(オランダ)において第1回締約国会議が開催され、ブスターニ事務局長(ブラジル)を長とする技術事務局を設立するとともに、予算を始めとする行財政問題、検証手続などを審議した。また、技術事務局は、締約国からの申告を受け、6月より申告を確認する冒頭査察を締約国に対し実施している。なお、11月にロシアなどが批准書を寄託した結果、12月現在の締約国は、国連安保理の全常任理事国を含む105ヶ国となった。 [生物兵器禁止条約] 生物兵器禁止条約(BWC)は、生物兵器、毒素兵器の開発、生産、貯蔵、保有等を包括的に禁止するが、科学兵器禁止条約と異なり、検証規定が存在しない。このため、91年以降条約を強化するための作業が開始され、94年9月新たに設置された専門家グループが、95年1月以降「検証措置を含めた新たな法的枠組み」の作成作業に着手した。現在、2001年までのできるだけ早期に作業を妥結するよう審議を重ねている。なお、12月末現在の締約国は140ヶ国である。 [大量破壊兵器及びミサイルの不拡散のための輸出管理体制] 大量破壊兵器等の不拡散のためには、単にその保持を禁止するのみならず、新たな取得を防止するための輸出管理体制を整備することが重要である。このような観点から、核兵器、生物・化学兵器及びその運搬手段となるミサイルについては、これらの兵器の製造に使用されうる関連物資と技術に関する国際的な輸出管理体制の下で協調した規制を行っている。核関連品目についてはロンドン・ガイドライン(注)に基づく原子力供給国グループ(NSG:35か国)が、生物・化学兵器関連品目についてはオーストラリア・グループ(AG:30か国)が、ミサイル関連品目についてはミサイル輸出管理レジーム(MTCR:29か国)が存在している。日本はこれらの国際的な輸出管理レジームに積極的に関与しており、特に、MTCRについては、議長国として、97年11月に全体会合を東京において開催した。 注:原子力専用品についてはロンドン・ガイドライン・パート1で、原子力・非原子力の両分野に使用される品目については同パート2で規制されている。 (B)通常兵器 [国連軍備登録制度] 国連軍備登録制度は、日本などのイニシアティブにより、軍備の透明性と公開性を向上させることを目的として92年1月に発足した。この制度の下で、毎年90ヶ国以上が、戦車、戦闘機などの7種類の主要な兵器の輸出入数量等を報告している。日本は、この制度に未だ参加していない諸国への働きかけ等を通じ、その運営に大きな役割を果たしている。また、この制度においては、軍備保有や国内生産を通じた調達に関するデータの提供は求められていないが、日本は、これも自発的に提供し、制度の更なる充実に向けて関係国とともに努力している。 [小火器問題] 自動小銃などの小火器は、紛争地域で大量に使用され一般市民の間にも被害を及ぼしたり、紛争終了後の開発を妨げたりしているにもかかわらず、これまで特段の措置がとられてこなかった。日本はこうした小火器問題に積極的に取り組むため、国連事務総長の下に専門家会合を設置することを求めた決議案を95年の国連総会で提案し圧倒的な支持を得た。この国連決議により設立され、日本の堂之脇外務省参与が議長を務めた国連小火器政府専門家会合は、97年8月、20項目の勧告を含む報告書をアナン事務総長に提出した。97年の国連総会は、この報告書の勧告を承認し、勧告の実施を進めるため日本が提出した決議案を圧倒的多数で採択した。今後はこの国連決議に基づき、新たな政府専門家グループが設置されるほか、小火器に関する具体的な研究や国際会議の開催など小火器問題の解決に向けて更なる取組が行われることとなっている。 [通常兵器及び関連品目の輸出管理体制]
94年3月にココム(旧共産圏に対する戦略物資及び技術の輸出規制を目的とした輸出規制委員会)が解消された後、2年以上にわたる協議を経て、96年7月、「ワッセナー・アレンジメント」 (注) が、通常兵器及び関連汎用品・技術に関する新たな国際的輸出管理体制として発足した。 注:協議が行われてきたオランダの地名にちなんだ名称 [第三国の輸出管理の整備・強化への協力] 国際的な輸出管理の実効性を高めるため、上記の輸出管理レジームなどは、レジームの非参加国に対しても、輸出管理制度の整備・強化を呼びかけている。日本も、アジア諸国やNIS諸国に対し、セミナーや研修などの実施を通じて、輸出管理分野での協力、対話を進めている。
カンボディアやアフガニスタンに見られるように、紛争時に埋設され放置されている対人地雷は一般市民に無差別な被害を及ぼしている。国連によれば、放置された対人地雷は世界で1億1千万個以上にものぼり、毎月2千人以上の一般市民が死傷していると言われている。このような事態は、人道上極めて重大な問題であるのみならず、紛争が終結した後の復興にとっても大きな障害となっていることから、対人地雷問題は、国際的に緊急の課題となっている。 【対人地雷の禁止】
対人地雷の規制の強化は以前から国際的な課題として取組がなされてきており、93年から95年にかけて対人地雷の輸出停止を求める国連決議が毎年コンセンサスで採択されてきたほか、96年5月には地雷の使用制限を強化し移譲制限を導入するために特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の議定書Ⅱを改正する議定書が採択され、日本は97年6月に同議定書を締結した。
|
|
|
|
|
【PKOを巡る議論】
国連平和維持活動(PKO)は、旧ユーゴーやルワンダで見られたような大規模な派遣が行われなくなったことや、従来から活動しているPKOが徐々に派遣規模を縮小する傾向にあることに伴い、派遣要員の総数は最大時の約5分の1(97年12月31日現在で14879名)に減少した。また、97年に実施された国連PKOは、グァテマラにおいて人権監視ミッションから派生したPKOを除き、いずれも従来から活動していたPKOを継承するものであり、新たな地域における新規PKOの設立は行われなかった。こうした国連PKOをめぐる環境の変化や旧ユーゴー、ソマリアの国連PKOにおける苦い経験も踏まえ、ここ数年はむしろPKOの質的向上を図る動きが見られる。 【日本の協力】 日本は、92年の「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)」施行後、アンゴラ、カンボディア、モザンビーク、エル・サルヴァドルのPKOに参加してきており、現在は、中東地域の平和と安定に向けた包括的取組の一環として96年2月からゴラン高原の国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に自衛隊輸送部隊等45名を派遣している。UNDOFへの要員派遣は、当初2年を目途に開始されたが、同PKOの重要性に鑑み、98年2月以降も更に2年を目途に派遣を継続することとなった。その活動ぶりについては現地司令官を含む国連関係者及び派遣先国から高く評価されている。 また、国際平和協力法は95年8月に施行後3年を迎えたことから、同法附則に基づき、いわゆる法律の見直し作業が開始された。この法律見直し作業では、これまでの派遣の教訓や反省を踏まえて、関係省庁により、法律改正案の具体的内容が検討されており、(1)武器の使用を、原則として現場にいる上官の命令によるものとすること、(2)国連PKOとしての選挙監視活動に類する国際的な選挙監視活動に対しても円滑・適切な協力が行えるようにすること、(3)人道的な国際救援活動に対する物資協力につき停戦合意を要件としないこと、の3点に関して改正を図る方向で検討中である。
世界の難民数は、冷戦終結後、民族的、宗教的紛争が各地で表面化したことにより、90年代に入って急増し、95年には3,000万人に達したが、その後はインドシナ難民問題の収束、大量のモザンビーク難民及びルワンダ難民の帰還により減少傾向に転じ、97年1月現在では約2,600万人となっている。ただし、世界各地に滞留する難民および紛争などのためにやむなく居住地を離れ流浪する大量の国内避難民の存在は、人道上の問題であると同時に、関係地域ひいては世界全体の平和と安定に影響を及ぼしかねない地球規模の問題であることには変わりない。 [和平を巡る動き]
91年に開始された中東和平プロセスは、パレスチナ暫定自治原則宣言、ガザ・ジェリコ先行自治合意、イスラエルとジョルダンの平和条約締結、パレスチナ暫定自治拡大合意などの重要な成果をあげてきたが、96年2月から3月にかけイスラエルにおいて連続テロが発生し二国間交渉が中断する中、同年6月、イスラエルにリクード党のネタニヤフ首相による右派連立政権が成立した。ネタニヤフ政権は和平プロセスを進めるとしつつもイスラエルの安全保障を強調し、パレスチナ独立国家樹立の否定、入植地の存続、ゴラン高原における主権の維持など、労働党政権と異なる立場を主張したため、和平プロセスは停滞した。 [日本の役割]
日本としては、中東和平を支える国際的な協力の一翼を担う観点から、2月のレヴィ・イスラエル副首相兼外相の訪日、4月の柳井外務審議官の派遣、8月のネタニヤフ・イスラエル首相の訪日、11月のハリーリ・レバノン首相の訪日などの機会に、和平努力を当事者に直接働きかけてきている。 [ボスニア和平を巡る情勢]
ボスニアでは95年12月に署名された和平合意(デイトン合意)に基づき、96年9月に選挙が実施され、その結果、大統領評議会、議会、閣僚評議会等の共同国家機構が97年初めまでに成立した。 [クロアチア情勢]
クロアチアでは、95年5月と8月にクロアチア軍がセルビア人勢力の支配地域の大部分を制圧した後、残った東スラヴォニアについては同年11月に合意が成立、国連が東スラヴォニア暫定統治機構(UNTAES)を派遣した。 [旧ユーゴー問題に対する日本の貢献] 旧ユーゴー問題は地理的、歴史的に欧州に関わりの深い問題であるが、人道的観点から、また、冷戦終結後の国際秩序の構築にかかわる国際的な課題であるとの観点からも、グローバルな意味合いを有していると言える。このような立場から、日本はボスニア和平履行に積極的に貢献している。97年については、復旧・復興支援として最大1.3億ドルの支援を供与する旨表明し、また、人道・難民支援として、ボスニアを含む旧ユーゴー地域全体を対象に最大約5、800万ドルを拠出する意図を表明している。さらに、9月に行われた市町村議会選挙では計29名の要員を派遣し、OSCEの監理・監視活動に参加した。
|
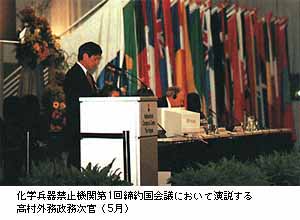 [化学兵器禁止条約]
[化学兵器禁止条約]
 【対人地雷の除去・犠牲者支援】
【対人地雷の除去・犠牲者支援】