|
|
|
|
|
【97年の国際社会の動き】
波乱と激動の20世紀も残すところわずか3年となった。今世紀後半40年近くにわたり国際社会を規定してきた冷戦構造が終焉を迎えて以後、新しい世紀を前に国際社会が90年代に取り組んできた最大の課題は、冷戦構造に代わる新たな安定的な国際秩序の構築であったと言えよう。
<新たな秩序の構築に向けて>
<新たな機会の活用と挑戦への対応>
<ますます多岐にわたる地球規模問題> 【97年の日本外交】
さて、このような国際情勢を踏まえて、日本は97年にはどのような外交を展開してきたのか以下概観するが、まず日本外交の方針について簡潔に述べることとしたい。
|
|
|
|
|
[全般]
日米両国政府は、96年4月のクリントン大統領訪日の際に発出された「橋本総理大臣とクリントン大統領から日米両国民へのメッセージ」及び「日米安全保障共同宣言」に沿って、政治・安全保障、経済、地球規模問題の各分野で協力関係強化に努めてきた。このような両国政府の基本方針は、97年4月の橋本総理大臣訪米の際にも確認され、97年も日米間の協力関係が一層進展した一年となった。
[日米経済関係(個別問題)]
(規制緩和)
(航空)
(港運) [コモン・アジェンダ]
発足以来ほぼ4年を経て、協力分野の大幅な拡大を見てきたコモン・アジェンダであるが、97年5月の次官級全体会合において、それまで多岐にわたっていた協力分野が、「保健と人間の開発」、「人類社会の安定に対する挑戦への対応」、「地球環境の保護」及び「科学技術の進歩」という4つの柱の下、18分野へと整理・統合された。整理・統合された枠組みの中には、「環境教育」といった協力分野も追加されている。 [国民交流] 日米両国の若者が、交流を深め、相互理解を促進することは、21世紀の世界にとって、重要な意味を持つ。そこで、日本政府は、より多くの米国の若者に対し、日本を学び、日本を知る機会を提供するという目的の下、米国の高校生、大学生、学部卒業生、教職員、若手研究者、若手芸術家等を対象とした対日理解促進のための包括的取組を推進している。また、橋本総理大臣は、98年夏より沖縄県の高校生を毎年40名米国に一年間のホームステイに派遣することを決定した。そして、これに呼応する形で、米国政府も5万ドルを拠出し、10名の米国人高校生を97年夏に沖縄に派遣して6週間のホームステイを経験させた。 [21世紀に向けて]
日米両国は、自由、民主主義、市場経済原理という共通の価値観を有する同盟国そしてパートナーとして、これまで長年にわたり、試練を乗り越え、経験を共有し、協力関係を発展させてきた。このような日米関係は、日米両国だけでなく、アジア太平洋地域、さらには国際社会全体の平和と繁栄にとって、重要な役割を担っており、日本外交の基軸である。 【全般】 97年は日中国交正常化25周年に当たり、9月に橋本総理訪中、また11月には李鵬総理来日と、首脳の相互訪問が実現し、記念すべき年にふさわしい二国間関係の発展が図られた。ここ数年の日中関係は、中国の核実験、日米安保、尖閣諸島、歴史認識等を巡って困難な局面もあったが、アジア太平洋地域、ひいては世界全体の安定と繁栄に果たす両国の役割に鑑み、双方が不断の努力を重ねてきた結果、97年の両国関係をめぐる雰囲気は大幅に改善した。
中国は96年7月に核実験停止宣言(モラトリアム)を表明し、これを実施している。これを踏まえ、原則凍結されていた中国への無償資金協力は、97年3月の池田外務大臣訪中の際に再開された。 【香港、台湾との関係】
香港は97年7月1日に中国に返還されたが、日本からは中国に対して、「一国二制度」の下で、これまでの開かれた自由な制度を維持していくことが、香港の繁栄を維持していく上で重要であることを指摘してきた。また、航空協定及び投資保護協定の締結、香港パスポートの取扱い等を通じて、日本は返還後の香港をできる限り支援してきた。10月には董建華香港特別行政区行政長官が来日し、「一国二制度」が順調に機能している旨説明し、双方で率直な意見交換を行った。 【国際社会における日中関係の役割】
日中両国は、二国間の困難な課題に取り組むとともに、地域や国際社会全体に関わる問題にも積極的に対応してきている。李鵬総理来日に際しての首脳会談では、アジア経済の安定化など国際社会の問題についての協力やロシア、米国等の国際情勢を中心に議論が行われた。 【98年に向けて】
72年の国交正常化から四半世紀を経た日中関係は、各方面での交流が進展してきているが、同時に両国は本来政治体制や国情の異なる国どうしであり、その交流が深化していく過程で、種々の摩擦が生じることも避けがたい面がある。そうした問題を解決していく上でも、将来に向けて若い世代を含む種々のレベルでの日中間の相互理解の重要性がますます高まっている。
日露関係では、93年10月のエリツィン大統領訪日の際に署名された東京宣言が、両国関係進展のための基盤となっている。日本としては、東京宣言に基づいて北方領土問題を解決して平和条約を締結し、日露関係の完全な正常化を達成するために最善の努力を払うとともに、ロシアの改革努力を支持し、同時に、様々な分野における協力と関係強化を図ることを対露外交の基本的考え方としている。そして最も重要な領土問題については、帰属の問題と、問題解決のための環境整備の両分野を車の両輪とみなして、同時に努力を傾けることとしている。 [日韓関係]
1月、金泳三(キム・ヨンサム)大統領が別府を訪問し、前年6月の韓国済州島での首脳会談に続き、打ち解けた雰囲気の中で両国首脳の幅広い意見交換が行われた。首脳会談においては、日韓両国間には解決すべき問題はあるが、双方の立場を主張しつつも、それらを乗り越えて未来に向けた協力関係を強化すべき点で認識が一致し、青少年交流拡充策等につき具体的な意見の一致があった。また、朝鮮半島情勢については、日韓米3国の緊密な連携が再確認され、さらに、国際社会の中での両国の協力を一層強化していくことで両国首脳の認識が一致した。その後、6月にはニュー・ヨークにおいて、11月にはヴァンクーヴァーにおいて首脳会談が行われた。 [日朝関係]
(イ)日朝間の懸案事項と国交正常化交渉再開に関する動き
(ロ)対北朝鮮人道(食糧)支援
(ハ)朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)
(ニ)四者会合・南北関係
97年後半、タイにおける通貨下落を発端として、アジアの通貨・株式が大幅に下落し、各国の経済は大きな打撃を受けた。まずタイにおいて、米ドルに事実上固定されていたタイ・バーツが、7月2日に実質上の変動相場制に移行したことに伴い、大きく下落した。
(イ)APEC
[ヴァンクーヴァー会合の具体的成果] 【アジア経済について】 非公式首脳会議では、アジア経済の問題に最大の関心が払われ、APEC地域の基礎的条件は依然として良好であり、なお高い潜在的成長力を有していることが確認され、健全なマクロ経済政策・構造調整を行うことが、潜在的成長を顕在化させる鍵であるとの点で認識が一致した。また、11月18、19日にマニラで採択された「金融・通貨の安定に向けたアジア域内協力強化のための新フレームワーク」が強く支持されるとともに、APECとしてもアジア通貨・金融問題について引き続き取り組んでいくことで一致した。 【貿易・投資の自由化・円滑化】 アジア経済の不安定化を受け、ともすれば各メンバーが内向き指向を強め、自由化の勢いが失われかねない中、一層の経済成長を実現するには「自由で開かれた貿易と投資」という目標の達成が重要であるとの認識のもと、ヴァンクーヴァー会合においても貿易・投資の自由化・円滑化を更に進展させることで一致した。その具体的成果として、まず、96年のフィリピン会合で各メンバーが提出した、貿易・投資の自由化・円滑化の対象分野における各メンバーの具体的な行動を示した個別行動計画(IAP)の改訂版が、ほぼすべてのメンバーから提出された。これにより、ボゴール目標の達成に向け、各メンバーの達成度の比較可能性、APEC地域の自由化行動の透明性・予測可能性が更に向上した。また、それを補完する形で、早期に自主的自由化を進める分野として9分野(環境関連機器・サービス、エネルギー、水産物、玩具、林産物、貴金属及び宝石、医療機器、化学品、電気通信端末機器認証手続相互承認)が閣僚会議で特定された。これら分野の自由化は、APECメンバーの多様性にかんがみ、あくまで自主性の原則の下に行われることも併せて確認された。
APECの車の両輪のもう一方である経済・技術協力については、96年のマニラ閣僚会議で採択された「経済協力・開発の強化に向けた枠組みに関する宣言」にて指定された経済・技術協力活動の優先6分野(人材養成、資本市場の発展、インフラストラクチャー(経済基盤)、環境、未来技術の活用、中小企業)についての活動の進捗を歓迎した。これら優先6分野中、97年の会合ではインフラと環境の2分野が特に重視され前者については首脳会議にて「インフラ整備官民協力増進のためのヴァンクーヴァー・フレームワーク」が採択された。環境については、日本より気候変動枠組条約第三回締約国会議の成功に向けて協力を求めた結果、同会議の成功に向けたAPECとしての強い政治的メッセージが発出された。さらに、現在APEC各種フォーラムにて個別に行われている経済・技術協力活動を効率よく調整するために、経済・技術協力に関する小委員会を高級実務者会合の下に設置することにつき閣僚レベルで決定された。 【新規参加問題】 閣僚レベルで新規参加基準が決定され、首脳レベルでは、98年から、ロシア、ヴィエトナム、ペルーの参加を認めることで一致した。また、今後10年間の新規参加の凍結期間設定についても一致した。従来よりメンバー間のコンセンサスのあったヴィエトナム、ペルーの参加に加え、日本は、閣僚会議、首脳会議を通じて、ロシアの参加を積極的に支持し、他のメンバーの賛同を得るところとなった。この3か国の参加により、APECがより完全にアジア太平洋地域経済を代表するフォーラムとなることが期待される。
アジア、欧州、北米という国際社会の三極間の関係の中で、従来相対的に希薄であったアジアと欧州の絆を強化することを目的として開始されたアジア欧州会合は、96年3月のバンコクでの第1回首脳会合を受け、97年も精力的な活動が展開された。特に、外相(2月)、蔵相(9月)、経済閣僚(9月)による閣僚級の会合が相次いで開催され、今後のASEMの体制が整った。また、民間人によるビジネス会議(7月)、第2回ビジネス・フォーラム(11月)が開催され、民間レベルでも充実した対話がなされた。 ASEMは政治、経済、文化等その他の分野を3本柱として、アジア欧州間に包括的な関係を築こうとする活動であるが、日本は、第1回首脳会合の際にそれぞれの分野で、様々なフォローアップ措置を提案した。まず、政治面では、政府間の対話に加え、民間レベルでの知的交流が重要との観点から、両地域の主要研究機関により設立されたアジア欧州協力協議会の活動を支援してきている。経済面では、千葉県幕張で経済閣僚会合を開催し、橋本総理大臣が冒頭挨拶を行った。その他、税関当局者間協力の提案に基づき、6月に第2回関税局長・長官会合が開催された。文化等その他の分野では、アジア欧州間の青年交流を促進する観点からミニ「ダボス」型青年交流を提案し、3月に宮崎県で100名を超える青年指導者を集めシンポジウムを開催した。 今後の活動としては、98年4月にロンドンで第2回首脳会合、99年に外相、蔵相、経済閣僚による第2回の閣僚級会合、2000年に韓国で第3回首脳会合が開催されることが決定している。特に98年4月の第2回首脳会合は、ASEMの将来を方向付ける上で極めて重要である。日本は、タイと共にアジア側調整国としてアジア側メンバー内の意見調整にあたるなど、第2回首脳会合の成功に向け積極的に努力している。
|
|
|
|
|
冷戦時代には、東西対立が国連の場にも反映され、国連はその第一の目的である国際の平和と安全の維持に必ずしも十分な役割を果たすことができなかった。しかし、冷戦の終結にともない、国連は、開発途上国における開発の推進、環境、人口、難民など様々な問題への対応に当たって一層大きな役割を果たすことが期待されるようになっている。
(安保理改革) 冷戦終焉後の国際社会において、安保理は、伝統的な安全保障の分野のみならず、人道、人権等の分野でも重要な役割を担うに至っている。他方、軍事面のみならず、経済・社会分野で貢献できる国の役割が増大している。このような新しい状況に適応するため、安保理にグローバルな貢献を行い得る新たなメンバーを加え、さらに安保理の作業方法などを改善して、その機能強化を図ることが必要となっている。 この安保理改革の問題は、94年1月以来、「安保理改革に関する作業部会」などの場において検討されてきている。97年は、3月に前述のラザリ議長の試案が提出された他、7月には、米国が途上国の常任理事国入りを認めること等を内容とする新たな立場を表明して、改革の早期実現に向けての決意を示したこと等、重要な進展が見られた。 これまでの議論を通じて、安保理の実効性と正統性を向上させるために、常任・非常任双方の議席を拡大する必要があることについては概ね各国の意見が一致しており、また、日独の常任理事国入りについては、幅広い支持が得られるに至っている。しかし、日独のみの常任理事国入りには途上国を中心に抵抗が強く、途上国の常任理事国入りを前提に、途上国からの新常任理事国をいかに選ぶかという問題について調整が続けられている。また、現在は15である安保理の総議席数をどこまで拡大するか、さらに、いわゆる拒否権の扱いについても議論が続いている。 日本は、(A)グローバルな責任を担う能力と意思を有する限定された数の国を新たに常任理事国に加え安保理の代表性を向上させること、(B)非常任理事国の議席数の適当な増加により安保理の機能を強化すること、(C)議席の地理的配分の不平等を改善する必要があること等を主張して、積極的に議論に参加してきている。また、日本の常任理事国入りについては、小渕外務大臣が9月に国連総会で行った演説で、憲法の禁ずる武力の行使は行わないという基本的な考え方の下で、多くの国々の賛同を得て、安保理常任理事国として責任を果たす用意があるとの日本の従来よりの立場を改めて表明した。
(財政改革) (開発分野の改革) 日本は、「新たな開発戦略」の考えの下、冷戦後の国際情勢に応じて先進国と途上国との間でお互いに責任を分担しつつ協調して開発に取り組むため、国連の諸機関が開発分野で有効に機能するよう改革されることが重要であると訴えており、97年7月には、沖縄県宜野湾市において「開発に関する沖縄会議」を開催した。また、日本の考え方は、アナン国連事務総長による改革案にも多く取り入れられた。
(アナン事務総長による改革案) [国際社会による地球環境問題への取組]
人類全体の生存に影響を与える地球環境問題の解決のためには、各国ごとの努力に加え、グローバル及び地域的な取組が不可欠である。地球環境の破壊は、現時点では目に見えない場合でも、数十年あるいは数百年後に現実の脅威となり得る性質を有しており、長期的な観点からの取組が必要である。他方、環境問題は、経済や社会の開発や発展と表裏一体の関係にあり、異なる発展段階と経済情勢にある各国が協調行動をとることは容易ではない。したがって、外交努力により国と国の認識の相違や利害の対立を調整し、もって全地球的、長期的な観点から適切な取組を行っていくことが必要である。
このように様々な分野で国際社会の努力が進展する中で、日本としても地球環境問題を外交の主要課題として位置づけ、次のように最大限の努力を行ってきている。 |
|
|
|
|
[在ペルー日本国大使公邸占拠事件] 96年12月18日(日本時間、以下同様)にペルーの反政府武装グループ、トゥパク・アマル革命運動(MRTA)によって在ペルー日本国大使公邸が占拠されたことで始まった本事件は、複数国の多数の人質を巻き込み、127日間の長きにわたり継続した未曾有の事件であった。事件は、97年4月23日、ペルー政府が電撃的な救出作戦を敢行し、3名の尊い生命の犠牲の上にようやく解決を見た。 [日本政府の対応]
日本政府としては、「テロに屈せず、人命尊重を最優先として、平和的解決を目指す」との基本方針の下、主に次のような対応を行った。 [教訓と課題]
外務省は、本事件を教訓として、反省すべき点、改善すべき点を調査し分析するために、事件解決直後に在ペルー日本国大使公邸占拠事件調査委員会を発足させた。同委員会において、警備の問題を始め事件発生に至るまでの経緯、発生後の対応等につき、検証と分析を行い、97年6月、その結果を報告書としてとりまとめた。その後フォローアップとして、人的・物的両面にわたる在外公館の警備体制の強化、テロ対策のための国際協力の推進(第2章第3節1.参照)、情報収集・分析体制の改善(具体的には、外務省内にテロ情報分析委員会、テロ情報分析室を設置)に取り組んできた。 |
 (1)日米関係
(1)日米関係
 【日中間の諸問題】
【日中間の諸問題】


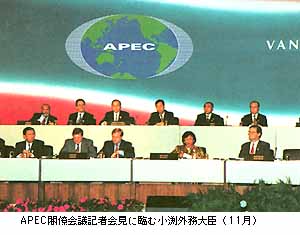 【経済・技術協力の重視】
【経済・技術協力の重視】
 (ロ)ASEAN地域フォーラム(ARF)
(ロ)ASEAN地域フォーラム(ARF) (国連改革)
(国連改革)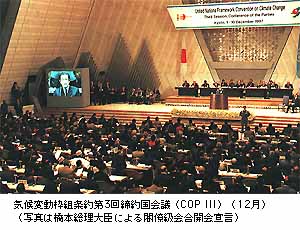 第二に、日本は環境分野での途上国支援に積極的に取り組んできている。92年6月の地球サミットにおいて、日本は92年度より5年間で環境分野の援助を9000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化することを発表した。その後92年度から96年度までの5年間の合計は約1兆4400億円となり、地球サミットの際に表明された目標額を大幅に上回る額が達成された。
第二に、日本は環境分野での途上国支援に積極的に取り組んできている。92年6月の地球サミットにおいて、日本は92年度より5年間で環境分野の援助を9000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化することを発表した。その後92年度から96年度までの5年間の合計は約1兆4400億円となり、地球サミットの際に表明された目標額を大幅に上回る額が達成された。