2.国際社会で活躍する日本人
(1)NGOの活躍
イ 開発援助分野
国際協力活動に携わる日本のNGOは400以上あると言われ、国際社会が貧困や自然災害、地域紛争など様々な課題に直面する中、地域社会や住民に密着したきめの細かい柔軟な対応ができるNGOの重要性はますます高まっている。
そうしたNGOとの連携の一環として、外務省は、日本のNGOが開発途上国で実施する開発援助事業に対して「日本NGO連携無償資金協力」等によりODAを提供している。2009年(12月末現在)には、日本の48のNGOが、アジア、アフリカ、中東、中南米等、30か国1地域において日本NGO連携無償資金を利用し、学校建設、水供給、医療、農村開発、地雷・不発弾除去等の幅広い分野にわたり76件の事業を実施している。
また、NGO、政府、経済界等が協力して、大規模自然災害や地域紛争の際にNGOが迅速に緊急人道支援活動等を行うことを目的に設立したジャパン・プラットフォーム(JPF)には、現在32のNGOが参加しており、2010年1月に発生したハイチ地震、2009年に発生した西スマトラ州パダン沖地震、フィリピン水害等における被災者支援のほか、パキスタン北西部、スリランカ北部等における避難民支援、スーダン南部における人道支援を実施している。
一方、日本のNGOは、前述のような政府資金を利用した開発援助事業に加え、支援者による寄付金、会費収入等を活用した援助活動も数多く実施しているほか、近年では、企業の社会的責任(CSR)への関心の高まりを受け、企業がNGOをパートナーとして、開発途上国で社会貢献事業を実施する新たな形の連携も見られるようになっている。
以上のようなNGOの国際協力の担い手としての重要性を重視し、NGOが活動基盤を強化して更に活躍していけるよう、外務省、JICA、国際開発高等教育機構(FASID)等は、NGOの組織強化、専門性向上、人材育成等を目指したセミナーを開催するなど、様々な施策を通じてNGOの活動を側面支援している。
外務省では、2009年にNGOの事業実施能力と専門性の向上を目的に、NGO研究会等のセミナー、シンポジウムに加え、NGOの組織強化を目的に、NGOの中堅職員が海外NGOや国際機関で実務研修を行うNGO長期スタディ・プログラム等、様々な施策を実施した。また、NGOの国際協力活動全般や組織づくり等についての、一般市民やNGO関係者からの質問・照会にこたえるNGO相談員を、全国に19団体配置している。
さらに外務省は、NGOとの対話・連携を促進するため、1996年からNGO・外務省定期協議会を実施している。年1回の全体会議に加え、2002年からは小委員会としてODA政策について協議するODA政策協議会、ODAの実施における連携策について協議する連携推進委員会を、それぞれ年3回ずつ開催している。

(ネパール 写真提供:(特活)シャプラニール=市民による海外協力の会)
ロ その他主要外交分野における連携
2009年2月から3月に開催された第53回CSWへの政府代表団には、NGO関係者が顧問として参加し、政府とNGOの橋渡し役として活動した。第64回国連総会では女性問題に取り組むNGOの代表が政府代表団に加わり、人権・社会分野を扱う国連総会第3委員会において議論に積極的に参加した。
「障害者権利条約」(注1)に関しては、障害者問題に取り組むNGOとの間で意見交換を実施し、その締結に向けた検討を進めている。
軍縮分野では、2月にATTアジア太平洋地域会合(於:東京)をNGOと共催し、6月にクラスター弾等の不発弾対策として、NGOとの共同調査ミッションをカンボジア、ラオスに派遣した。また、11月の対人地雷禁止条約(オタワ条約)第2回検討会議(於:コロンビア)においては、シンポジウムをNGOと共催した。加えて、日本NGO連携無償資金協力を通じ、アフガニスタンやカンボジア等で活動するNGOによる地雷・不発弾処理、犠牲者支援事業の実施を支援している。
国際組織犯罪分野では、内閣に設置された「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」の下に、定期的にNGOと協議の場を設け、官民が連携した被害防止策及び被害者支援の在り方等について率直な意見交換を行っている。特に、2009年にこれまでの「人身取引行動計画」を改定して決定された、「人身取引対策行動計画2009」の策定作業においては、NGOとの意見交換会を通じて広くその意見を聴取し、また、パブリックコメントを実施して、人身取引対策に日ごろから従事しているNGOの現場の声が計画に反映されるよう努めた。
国連改革の分野では、外務省は国連改革を考えるNGO連絡会と「国連改革に関するパブリックフォーラム」を共催した。2005年の国連首脳会合以降における国連改革の進展と本フォーラムの成果を振り返るとともに、新たな国際課題を踏まえ、更なる国連改革に向けた日本の取組の在り方などについて建設的な意見交換を行った。

(パキスタン 写真提供:(認定)日本地雷処理を支援する会)
(2)青年海外協力隊・シニア海外ボランティア
JOCVは、技術を有する20~39歳の青年男女が、開発途上国地域住民と生活を共にしつつ、当該地域の経済及び社会の発展に協力・支援することを目的とする事業で、派遣された協力隊員はまさしく日本の「顔の見える」協力を行い、開発途上国の発展に貢献してきた。2009年末までに累計で87か国に33,653人の隊員が派遣され、農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、スポーツ、計画・行政の8分野181職種にわたる活動を積極的に展開している。
また、SVは、幅広い技術と豊かな経験を有する40~69歳の中高年男女を開発途上国に派遣する事業である。1990年の事業発足以来、年々事業規模を拡大しており、2009年末までに63か国に4,050人を派遣し、計画・行政、公共・公益事業、農林水産、鉱工業、エネルギー、商業・観光、人的資源、保健・医療、社会福祉、その他(渉外促進、有資格登録)の9分野153職種にわたる協力を行ってきた。
近年は一線を退いたシニア層の再出発・再活用という観点からも、豊富な経験と熟練の技術を持つシニア海外ボランティアが注目を集めるなど、国内におけるボランティアへの関心は増大している。青年海外協力隊及びシニア海外ボランティアは、国民参加型国際協力の中核を担う事業として、開発途上国でボランティア活動に従事したいという国民の高い志(こころざし)を広く支援している。
2009年12月末現在、2,362人の青年海外協力隊と700人のシニア海外ボランティアが、世界各地(それぞれ75か国、56か国)で活躍を続けている。また、帰国したボランティア参加者はその経験を教育や地域活動の現場で共有するなど、社会への還元を進めており、日本独自の国民参加型による活動は、受け入れ国を始め国内外から高い評価と期待を得ている。さらに、1月、外務省及びJICAは、現下の世界的な不況の中、閉塞(そく)感の漂う日本経済の打開策の一環としてODAもその一役を担うとの観点から、例年1,800人前後を海外に派遣している青年海外協力隊及びシニア海外ボランティアの新規派遣人数を、2009年度におよそ1割、約200人をめどに増やすことを発表した。また、2009年度補正予算において更に約100名増やすことを決定し、要員確保のための積極的な募集広報及び要請案件の開拓に取り組んだ結果、2009年度目標をほぼ達成する見込みである。

(フィリピン 写真提供:JICA)

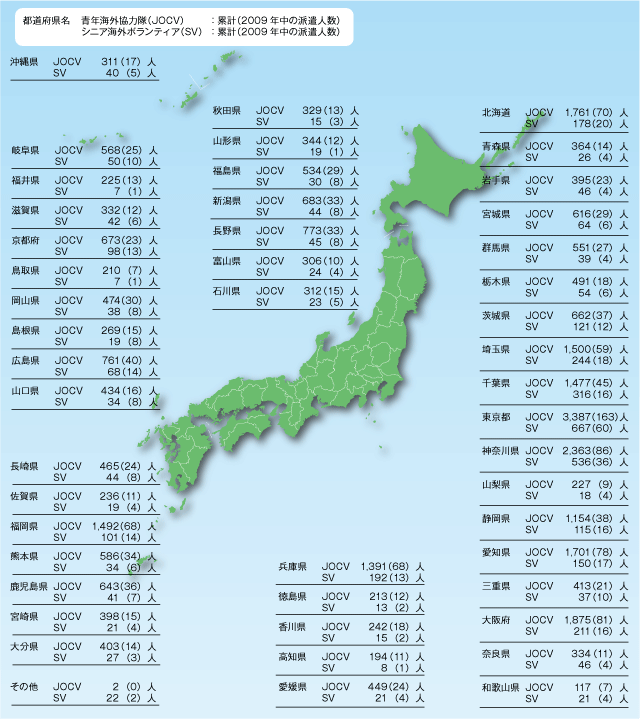
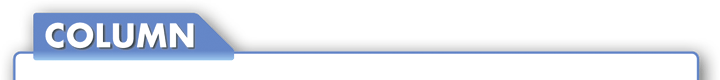
2007年に潘基文(バンギムン)国連事務総長から国連平和大使に任命されたことにより、特に私自身が変わったことは何もありません。それまで日米を中心に行ってきたコミュニティー・エンゲージメント(地域に根ざした社会貢献)活動を、プロの音楽家としての演奏活動や南カリフォルニア大学での後進指導とともに続けています。国連平和大使に課せられた“仕事”は特になく、従事している活動の中で、国連や国連が提起している問題などを世界にアピールしていくことが求められています。

私の場合、音楽家として30年近いキャリアと、米国で“Midori&Friends”(日本では「みどり教育財団東京オフィス(現:ミュージック・シェアリング)」)を設立して18年、様々な音楽を通じて、多くの人々と触れ合う機会に恵まれてきました。日米だけでなくアジアの国々の子どもたちとも音楽の喜びをシェアしたい、また音楽社会活動のノウハウや基礎を後輩に受け継いでいきたい。日本のNPO法人である「ミュージック・シェアリング」が率先してやるべきことだと考え、ベトナムを訪問したのが2006年。以後、毎年クリスマス前後に、カンボジア、インドネシア、2009年末にはモンゴルを、若手演奏家とカルテットを組んで訪問してきました。国や地域によって子どもたちを取り巻く環境は大きく異なりますし、成果がすぐに出るといった活動ではありませんが、音楽を聴く機会のなかった子どもたちが私たちの音楽を聴くことによって、好奇心や向上心というものを育んでくれれば、その子どもたちが大人になったときに必ず社会は違ってくると信じています。これらの活動を通じて、私たち音楽家は自分たちが当たり前と思っていたことがエゴにすぎなかったことに気付かされます。そうした経験を今度は日本の小学校で子どもたちに話すと、子どもたちは音楽家を通じてですが、自分たちとはあまりにも違う、同じ年頃の子どもたちの置かれた環境を知り、貧困や戦争など世界が抱える様々な問題を考えるきっかけとなります。私自身ができることは限られていますが、「やるべきことは必ずできる」をモットーにこれからも地道に活動を続けていきたいと思います。それが微力ながら、音楽家として、教育者として、国連平和大使として、社会に貢献できることだと信じています。
ヴァイオリニスト・国連平和大使 五嶋みどり


(注1)日本政府は2007年9月に署名を行った。