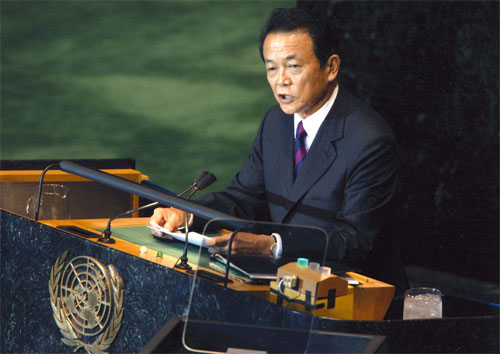
第63回国連総会で一般討論演説を行う麻生総理大臣
(9月25日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)
| 第1章 | 概観 |
| 2008年の国際情勢と日本外交の展開 |
2008年は、8年に一度のG8サミット議長国として一連のG8関連会議を開催するとともに、5年に一度のアフリカ開発会議(TICAD)を開催するという、日本にとり近年稀(まれ)な外交の年であった。
折しも、2008年は国際社会として多くの困難な課題に引き続き直面した年となった。気候変動問題、アフリカの開発をめぐる問題、地域紛争や大量破壊兵器の拡散等、いずれもいまだ解決への道半ばである。テロ事件は各地で頻発し、ソマリア沖・アデン湾等の海上交通路での海賊行為が多発・急増し、大規模な自然災害により各地で甚大な被害が生じた。また、2008年前半における食料・資源エネルギー価格の高騰は、生産国に大きな利益をもたらした一方で、輸入国、とりわけアフリカを始めとする開発途上国の経済に大きな打撃を与え、食料・エネルギー安全保障の確保が重要な課題となった。同年後半以降は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済に深刻な影響を与えている。
こうした状況の下、2008年は、深刻化する国際社会の共通課題の解決に向けて、日本が果たし得る役割について、自他共に再認識する年となったと言える。日本はG8議長国として、またTICAD開催国として、内外の期待にこたえ、共通課題の解決に向けて主導的に取り組んだ。
気候変動問題については、環境・省エネ国家として、公平で実効性ある2013年以降の枠組み構築に向けて積極的に取り組んだ。1月、福田康夫総理大臣は世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)において「クールアース推進構想」を発表し、今後の温室効果ガスの削減目標について、国別総量目標を掲げて取り組む方針を明らかにするとともに、排出削減と経済成長の両立を目指す開発途上国支援策として100億米ドル規模の「クールアース・パートナーシップ」を表明した。7月のG8北海道洞爺湖サミットでは、日本は議長国として2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも50%削減するという長期目標を、国連気候変動枠組条約のすべての締約国と共有し、採択することについて、米国を含む各国と精力的な協議を実施することで一致した。これは2007年のG8ハイリゲンダム・サミットの成果からの大きな進展であった。また中国、インド等新興国も含むエネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国首脳会合(MEM)において、長期目標の共有を支持することで一致し、公平で実効性ある2013年以降の枠組みづくりに向けた布石を打つこととなった。さらに麻生太郎総理大臣は、2009年1月のダボス会議の場で、6月までに日本としても中期目標を示すことを表明した。
アフリカ開発については、5月、横浜にて第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)を開催した。同会議では、経済成長の加速化、人間の安全保障の確立、環境・気候変動問題への対処を重点事項として、アフリカ開発の方向性について活発な議論が行われた。日本は、2012年までの対アフリカ政府開発援助(ODA)倍増、民間投資倍増支援等を表明し、各国から高い評価を得た。TICAD IVでの議論は、G8北海道洞爺湖サミットにも反映された。日本は同会議で表明した支援策の着実な実施に努めている。
テロ撲滅に向けた取組にも引き続き積極的に取り組んだ。アフガニスタンについては、テロの温床に逆戻りさせないため、治安・テロ対策と人道・復興支援を「車の両輪」として、インド洋における海上自衛隊の補給支援活動や、ODAを通じたインフラ整備や保健・教育分野での支援等を実施している。また、アフガニスタンの隣国パキスタンによるテロ撲滅及び経済安定化に向けた努力を積極的に支援している。イラクに対しても、ODAや自衛隊の活動を通じて復興支援に取り組んできた。12月には、イラクの政治・治安状況の改善等を踏まえ、約5年間にわたる自衛隊による支援活動を成功裡(り)に終了した。
さらにソマリア沖・アデン湾における海賊事案の多発・急増が国際的な問題になる中、関連する国連安全保障理事会(安保理)決議の共同提案国として、国際社会の取組の重要性を認識するとともに、2009年には日本としても海上自衛隊艦船を派遣すべく準備が進められている。
変動する食料価格について、日本は、議長国として7月のG8北海道洞爺湖サミットでこの問題を取り上げ、世界の食料安全保障に関するG8首脳声明を取りまとめるなど、積極的な外交を展開した。エネルギー価格の問題については、日本はG8北海道洞爺湖サミットにおいて取り上げたほか、産消対話のフォーラムへの積極的参加や国際エネルギー機関(IEA)との関係強化、国際省エネルギー協力パートナーシップ(IPEEC)設立の主導等を通じ、世界と日本のエネルギー安全保障の強化に取り組んだ。
金融・経済危機に関しては、11月、ワシントンにおける金融・世界経済に関する首脳会合及びペルーにおけるアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議にて、麻生総理大臣から、金融危機を克服した日本の経験を踏まえた提案とともに、中小国や新興国支援のため、国際通貨基金(IMF)への最大1,000億米ドル相当の融資を表明する等の具体的かつ重要な貢献を行った。アジアに対しては、地域の金融面での協力スキームであるチェンマイ・イニシアティブの強化を進めた。2009年1月のダボス会議においては、麻生総理大臣は、市場経済、民主主義を指向する諸国の努力を支援し、繁栄の道を共に歩むという「自由と繁栄の弧」の考え方に基づき外交を進めていくとともに、アジアについては、世界で最も潜在力を有するアジアが「開かれた成長センター」として世界経済に貢献するよう、アジアの諸国における金融・経済危機の影響への対応など成長力強化と内需拡大のため、総額1兆5,000億円以上の支援を行う旨表明した。さらに、TICAD IVで打ち出した対アフリカ支援策を必ず実行する旨述べた。
2008年10月、日本は国連安保理非常任理事国選挙において、国連加盟国中最多となる10度目の当選を果たし、2009年1月から2年間、安保理理事国を務めることとなった。これは国連の場を始めとする日本外交の実績とその姿勢とが国際社会において高く評価され、今後一層の貢献が期待されていることの表れであると言える。日本は、引き続き、山積する国際社会の諸課題の解決と、そのための新しい秩序づくりに向けて、日本の経験と英知を活用し、積極的・主体的な外交を展開していく方針である。
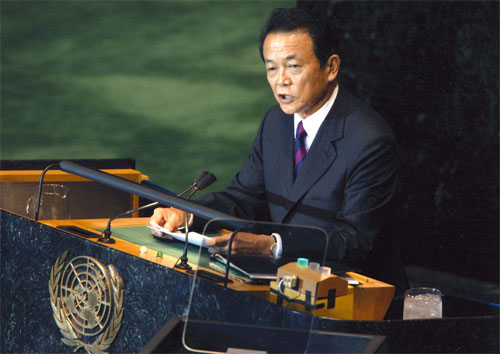
第63回国連総会で一般討論演説を行う麻生総理大臣 |
7月7日から9日までの3日間、日本はG8サミットの議長国として、G8北海道洞爺湖サミットを主催し、国際社会が直面する地球規模の課題の解決に向けた議論を主導した。G8サミットの日本での開催は、G8九州・沖縄サミット(2000年)以来8年ぶり5回目であり、G8首脳会合を核として、アフリカ首脳等との拡大会合、主要経済国首脳会合(MEM)等への招待国を合わせた22か国の首脳が参加する史上最大規模のサミットとなった。
G8北海道洞爺湖サミットは、地球温暖化の進行やエネルギー・食料価格の高騰など地球規模の問題が人々の生活に切実な影響を与えている中で行われ、G8首脳は、「世界経済」「環境・気候変動」「開発・アフリカ」「政治問題」を主要議題に、真剣な討議を行った。
世界経済については、不確実性に直面する中、G8が個別にあるいは共同して、引き続き適切な行動をとる決意を示し、世界の不均衡についても、G8として健全なマクロ経済運営及び構造政策を通じた円滑な調整を促進する旨誓約した。また、国際的な貿易及び投資に関するあらゆる形態の保護主義的な圧力への対抗、原油・食料等の価格上昇に対する強い懸念を示したほか、食料問題についての独立文書を取りまとめ、G8として食料価格高騰に対してあらゆる可能な対策をとる決意を確認した。
環境・気候変動の議論においては、G8として2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも50%削減するという目標を世界全体で共有し、採択することを求めるという首脳宣言をまとめた。さらに、日本が提案した「セクター別アプローチ」は有益な手法であるという点についてG8各国の一致が見られた。
また、開発・アフリカの分野では、「人間の安全保障」の確立に向けて保健・水・教育分野に焦点を当て、国連で定めた2015年を期限とする開発に関する目標であるミレニアム開発目標(MDGs)達成に向けた決意を新たにしたほか、対アフリカODAを2011年以降も増加させる必要性にも言及した。
6月に開催されたG8京都外相会合の成果を踏まえて行われた政治問題の議論においては、不拡散の観点から北朝鮮やイランの核問題について充実した議論を行うとともに、「テロとの闘い」や平和構築の観点で重要な課題であるアフガニスタンや中東和平について、G8のコミットメントを確認した。また、テロ対策、ジンバブエ問題についてはそれぞれ独立の首脳声明を発出した。
なお、今回のG8サミットでは会議の運営面でも徹底した環境配慮を行い、日本の最先端環境技術を国際メディアセンターで披露した。

G8北海道洞爺湖サミットに集う各国首脳(7月8日、北海道洞爺湖) |
 ロゴマークは公募により三重県立特別支援学校北勢きらら学園の近藤敦也さんら5名のグループのデザインが選ばれた。「地球がいつまでも緑あふれる美しい星であってほしい」との願いを込めた。 |

G8北海道洞爺湖サミットは、あらゆる面で環境配慮の図られたサミットだった。主要テーマが地球温暖化問題であり、低炭素社会をどう実現していくか、具体的に貢献する環境技術を打ち出すとともに、日本の自然観や文化を発信する良い機会となった。
国際メディアセンター(IMC)の建築、運営面での省エネ・省資源の試み、日本の環境技術の粋を集めた「環境ショーケース」の展示、会場間の移動に次世代自動車を採用するなど、各所に意欲的な取組が見られた。このようにCO2を極力削減した上で、最終的に排出されるCO2は排出権の購入やCO2削減プロジェクトなどを通じて相殺(カーボン・オフセット)された。
特に注目されたのは、IMCの雪冷房である。展示室の床面をガラス張りにして貯蔵する雪を見せ、建物そのものが省エネに徹していること、部材のほぼすべてを再使用、リサイクルすること、壁面緑化や薄膜太陽電池なども話題を呼んだ。
「環境ショーケース」では、次世代自動車や燃料電池、省エネ技術や水処理技術など、実物を交えて最新の環境技術を展示した。展示スペースの半分は、こうした技術を培ってきた日本の自然観や感性を「地球茶室」と称して演出した。地球温暖化の現状が直感的に分かるデジタル地球儀「触れる地球」が並び、大型スクリーンに月観測衛星かぐやの「月面からの地球の出」シーンが映し出されたのは印象的であった。福田首相を含む訪問者をロボットASIMOが案内したのもここである。
屋外でも、環境負荷を抑えたエコ住宅の展示、家庭用燃料電池を稼動させての「足湯」体験、燃料電池車やハイブリッド車等次世代自動車の試乗などが紹介された。各国首脳夫人もこうした展示や次世代自動車の試乗を楽しんだ。
各国の記者はこの「環境ショーケース」から世界に向けてニュースを配信した。首脳会議の外でも、環境をテーマに掲げた今回のサミットは、大きな成果が残せたと思う。余談だが日本古来のエコグッズとして会場で配布した団扇(うちわ)は大人気で、2,000枚もの団扇が世界へ広がっていった。
「環境ショーケース」展示計画担当
(株)アーバン・コミュニケーションズ 環境プロデューサー 森 高一

雪冷房システムを備えたメディアセンターと環境に配慮した最新技術が集められたエコ住宅 
省エネ技術を培ってきた日本の自然観や感性を演出した「地球茶室」 |
アフリカは、近年、年平均約6%という高い経済成長を続けるとともに、各地において政治的安定に向けた進展が見られている。その一方で、貧困、紛争、感染症、環境・気候変動問題等の大きな課題や新たな挑戦に直面している。日本は対アフリカ外交をアフリカ開発会議(TICAD)プロセス(注1)を基軸として推進しており、5月には横浜で第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)を開催した。同会議には、41名の国家元首・首脳級(ジャン・ピン・アフリカ連合(AU)委員長を含む)を含むアフリカ51か国、34か国の開発パートナー諸国及びアジア諸国、77の国際機関及び地域機関の代表並びに民間セクターやNGO等市民社会の代表等3,000人以上が参加した。
同会議では「元気なアフリカを目指して」との基本メッセージの下、「経済成長の加速化」、「人間の安全保障の確立」、「環境・気候変動問題への対処」を重点事項として議論が進められた。具体的には、[1]アフリカの成長を加速させるべく、インフラ、人材育成、農業、貿易・投資等を支援、[2]「ミレニアム開発目標」(MDGs)の達成に向け、コミュニティ開発、教育、保健、水・衛生などの分野におけるアフリカ諸国の取組を引き続き支援、[3]経済成長の大前提である平和の定着、経済成長の配当を貧困層にも配分するための良い統治の促進につき、アフリカ諸国自身の努力を支援、[4]アフリカの成長を持続可能なものとするため、アフリカ諸国による環境・気候変動問題への対処を支援の4点について活発に議論された。
日本は、同会議において、2012年までの対アフリカODAの倍増、対アフリカ民間投資の倍増支援等を発表した。また、今後のアフリカ開発の方針を示す政治的文書として「横浜宣言」を採択し、具体的な支援策を示した「横浜行動計画」、支援策の着実な実施をモニタリングする仕組みを示す「TICADフォローアップ・メカニズム」を発表した。
全体会合と並行して、福田総理大臣は、すべての首脳級参加者、AU委員長及び6名の個人招待者等計47名との間で個別に会談した。高村正彦外務大臣も、首脳級参加者、国際機関代表及び個人招待者等23名と個別会談を行ってアフリカ重視の姿勢を明確に示した。さらに、森喜朗元総理大臣、小野寺五典外務副大臣、中山泰秀外務大臣政務官も多くの個別会談を行い、日本とアフリカ諸国との二国間関係の強化を図った。
同会議では全体会合、分科会のほかに様々なイベントが行われた。その一つとして、天皇皇后両陛下御臨席の下、第1回野口英世アフリカ賞(注2)授賞式・記念晩さん会が行われ、顕著な功績を上げているグリーンウッド博士(英国)とウェレ博士(ケニア)に第1回野口英世アフリカ賞が贈られた。

2008年春、横浜市の境木小学校はアフリカとの「一校一国」運動で「レソト王国」と交流することになりました。「レソト」と聞いてもどこにあるのかさえも知らない子がほとんどでしたので、まずはレソトについて調べる事から交流が始まりました。
4月16日、いよいよレソト大使との交流会の日がやってきました。大使の奥さま、書記官の方の、レソトの空を思わせるような鮮やかなブルーの洋服やレソトの帽子、色とりどりの毛布に子ども達の視線は舞台にくぎづけとなりました。全校児童からの校歌のプレゼントを、大使は心から喜んでくださいました。続いてJICAの方からレソトの美しい自然や、人々の生活の様子の説明があり、子ども達は大変興味を持った様子でした。また大使は、音楽と英語活動の授業では子ども達と共に楽しく活動し、給食も一緒に食べて下さったので、休み時間になると校長室は大使に会いたいと言うたくさんの子ども達で溢れていました。午後は、6年生と大使ご自身のお仕事についてお話になり、子ども達の質問にも熱心に耳を傾けて、その後5月の横浜パレードにも招待して下さいました。
「一校一国」運動によって美しい「レソト王国」は境木小学校の児童にとって本当に身近な、行ってみたいと思う国になりました。この交流がきっかけとなり、これからも両国がより深く繋がっていくことを切に願っております。
横浜市立境木小学校 主幹教諭 中野 素子

(写真提供:横浜市立境木小学校) 
(写真提供:横浜市立境木小学校) |
「一校一国」運動とは、第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)開催に伴い横浜市で実施された、アフリカ各国の大使館等と小学生との交流事業です。横浜市内の55の小学校には駐日大使館を設置する35か国の大使等が招待され、小学校での交流事業を通じアフリカへの理解を深める機会となりました。
日本のアジア・大洋州外交の基本目標は、この地域を、基本的価値を共有し、相互理解と協力に基づく、長期的な安定性と予見可能性が確保された地域へと導いていくことにある。日本は、アジア・大洋州で日米同盟を基軸としつつ、積極的な外交を展開しており、2008年においても、引き続き顕著な進展が見られた。
中国との間では、日中平和友好条約締結30周年である2008年には、5月の胡錦濤(こきんとう)国家主席による中国国家主席としての10年ぶりの訪日や10月の麻生総理大臣の訪中等、5回の首脳間の相互訪問が行われ、「戦略的互恵関係」構築に向けて多くの対話が重ねられた歴史的な年となった。日中間には「食の安全」の問題や12月の中国公船の尖閣(せんかく)諸島領海への進入事案などが発生したが、幅広い層での交流が進むなど関係は着実に進展した。中国は、米国との安定的関係構築を始め各国との積極的な外交を行うとともに、多数国間外交も活発化させている。日本は、中国が国際社会の諸問題に関与する姿勢を歓迎しつつ、軍事力の近代化や対外援助の在り方等について、透明性を確保し、国際社会の規範にのっとった行動をとることを求めている。
地理的に最も近い隣国であり、基本的価値を共有する韓国とは、李明博(イミョンバク)大統領との間で、「シャトル首脳外交」を実施し、「成熟したパートナーシップ関係」の構築に向けた日韓関係の進展が見られた。また、日中韓協力については、12月、日中韓首脳会議を福岡において初めて単独開催し、未来志向で包括的な協力を進めることで一致するなど、画期的な進展が見られた。
2015年までのASEAN共同体形成を目指し、統合努力を継続している東南アジア諸国連合(ASEAN)に対しては、日本は、10月にASEAN担当大使を任命し、12月には日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定が発効するなど多くの分野での関係を強化し、日・ASEAN間の「戦略的パートナーシップ」の一層の強化に努めるとともに、域内の格差是正等ASEANの統合と発展に向けた努力の支援に取り組んでいる。
インドとの関係では、10月にシン首相が訪日した際、麻生総理大臣との間で、安全保障協力に関する共同宣言に署名するとともに、幅広い分野での協力を決定するなど、2007年に引き続き「日印戦略的グローバル・パートナーシップ」の力強い前進が見られた。
基本的価値を共有するパートナーであるオーストラリアとの関係では、6月のラッド首相訪日の際に、包括的な戦略関係の更なる強化を決定し、より具体的な安全保障協力を推進するとともに、日米豪戦略対話を中心とする3か国協力をより一層進展させている。
また、太平洋島嶼(しょ)国・地域との関係では、2009年5月に第5回太平洋・島サミットを開催することが決定された。
極東・東シベリア開発を進め、アジア太平洋地域との関係強化を目指しているロシアとの間では、高い次元の日露関係を構築すべく、懸案である北方領土問題の最終的解決に向け、精力的に交渉を行うとともに、ロシアがアジア太平洋地域との経済的、社会的、人的つながりを強化し、同地域において、建設的な役割を担うようにするための協力を進めている。
アジア太平洋地域における深刻な問題である北朝鮮をめぐる諸懸案については、日本は関係国と協調しつつ、朝鮮半島の非核化と拉致(らち)問題を含む日朝関係の双方が共に前進するよう、最大限の努力を行った。非核化については、無能力化作業等一定の前進があったが、検証の具体的枠組みの構築について、北朝鮮は前向きな姿勢を示していない。また、拉致問題についても、日朝実務者協議において日朝間で拉致問題に関する全面的な調査の実施及びその具体的態様等に合意したにもかかわらず、北朝鮮はいまだ調査を開始していない。
日本は、地域諸国が共通の課題に対処するため、様々な地域の枠組みにおいても積極的な協力を推進した。
日本と米国は、基本的価値及び戦略的利益を共有する同盟国であり、日米同盟は日本外交の基軸である。現在も東アジア地域に不透明性や不確実性が存在する中、日米安全保障体制を中核とする日米同盟は、日本の平和と安全及びアジア太平洋地域の安定と発展にとって不可欠な役割を果たしている。
日米両国は、在日米軍再編の着実な実施、弾道ミサイル防衛(BMD)協力の推進等を通じた日米安保体制の強化を含む日米二国間関係のみならず、北朝鮮問題を含むアジア太平洋情勢や、金融・世界経済問題、「テロとの闘い」、気候変動・エネルギー問題、アフリカ開発等の国際社会が直面する諸課題について緊密に連携して取り組んでいる。
米国では11月に大統領選挙が行われ、「変革」を掲げる民主党のオバマ候補が当選し、2009年1月に新政権が発足した。日本は、2009年2月のクリントン国務長官訪日の際の日米外相会談や麻生総理大臣訪米の際の日米首脳会談等において日米同盟の重要性を確認するとともに、種々の機会をとらえて電話会談を行うなど、新政権との間でも緊密な連携を図っている。
日本とカナダは、基本的価値を共有するアジア太平洋地域のパートナー及びG8参加国として、政治、経済、安全保障、文化等、様々な分野で緊密に協力している。7月のG8北海道洞爺湖サミットの際には、ハーパー首相が公賓として訪日、福田総理大臣と二度にわたり首脳会談を行った。日加修好80周年の2008年には、両国において様々な交流及び行事が行われた。
日本が原油の約9割を輸入する中東地域の平和と安定は、国際社会全体の安定と日本のエネルギー安全保障にとって不可欠であり、日本は、国際社会と連携しつつ、中東外交に積極的に取り組んでいる。
2008年、中東地域では、石油資源を背景にした湾岸諸国の経済成長、イラクの治安状況の改善など前向きな動きが見られた。その一方、アフガニスタンの治安情勢の悪化、イランの核問題、イスラエルによるガザ地区への攻撃などの問題を依然として抱えている。さらに、原油価格の高騰と急落、世界的な金融危機も地域経済に様々な影響を与えている。
こうした中、5月に高村外務大臣が、G8議長国の外相として、安定と復興のための努力が続くアフガニスタンを訪問し、改めて同国に対する協力を表明した。また、7月には、中東和平に貢献すべく、東京で「平和と繁栄の回廊」構想の4者協議閣僚級会合を主催し、同構想の具体化にも取り組んだ。
また、10月、アラブ首長国連邦で開催された拡大中東・北アフリカ構想(BMENA)「未来のためのフォーラム」閣僚級会合で、日本は共同議長として貢献した。
日本と欧州は、民主主義、人権、法の支配等の基本的価値を共有するとともに、国際社会の安定と繁栄に向けて主導的な役割を果たす上での戦略的パートナーである。日本が欧州諸国、欧州連合(EU)、北大西洋条約機構(NATO)等との間で協力を進めていくことは、不安定要素の多い今日の国際情勢の中で、グローバルな諸課題に国際社会が効果的に対応していく基盤を強化するものとして、ますます重要になっている。
2008年、欧州地域は、2月のコソボによる独立宣言、8月のグルジアとロシアとの武力衝突への対応等の安全保障問題が国際社会の注目を集めた。また、同年前半はエネルギー価格高騰への対応、後半は金融危機への対応で、EUや欧州諸国が国際的議論の中で積極的役割を果たしたことが注目された。
こうした中、日本と欧州間では、福田総理大臣が4月にロシア、6月にドイツ、英国及びイタリアを訪問し、一方、欧州からは、7月のG8北海道洞爺湖サミットに、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、欧州委員会の首脳が訪日し、G8サミット・プロセスを通じて、エネルギー、気候変動を始めとする様々な分野における協力を確認した。また、10月には、麻生総理大臣がアジア欧州会合(ASEM)首脳会合に出席し、金融危機への対応におけるアジアと欧州の連携強化を確認した。
ロシアについては、5月のメドヴェージェフ大統領及びプーチン首相の就任後も、全般的に安定した政権運営が続いている。また、対外政策においては、近年、極東・東シベリア開発を進め、アジア太平洋地域との関係強化を目指す方針の下、同地域における活動を活発化している点が注目される。日露間では、アジア太平洋地域における重要なパートナーとしての関係を構築するために、北方領土問題の最終的解決に向け、首脳・外相間を始めとした様々なレベルでの精力的な交渉が行われている。また、両国間の経済関係が順調に発展するなど、「日露行動計画」に基づいて幅広い分野で協力が進んでいる。
8月の南オセチアをめぐるグルジアとロシアとの武力衝突及びロシアによる南オセチア及びアブハジアの独立承認に関して、日本は、グルジアの領土一体性の原則に基づく平和的解決を一貫して支持する立場を表明し、関係国に働き掛けを行った。
さらに、日本は、地域的枠組みも活用しながら、中央アジア・コーカサス、中・東欧において、「自由と繁栄の弧」の考え方に基づき民主化や市場経済化を進める国々との対話と協力を進めている。
近年のアフリカでは、平和と安定に向けた動きや好調な経済成長などの前向きな兆しが見られる一方で、貧困や紛争、政情不安、感染症、テロや組織犯罪といった深刻な問題も依然として抱えている。特に2008年には、ケニアでの2007年末の大統領選挙後の混乱、ジンバブエの内政混乱、ダルフール問題を始めとするスーダン情勢、コンゴ民主共和国東部の情勢不安、ソマリア沖・アデン湾での海賊問題等が国際社会の注目を集めた。折からの世界的な金融危機・経済減速も、アフリカ諸国に様々な影響を与えている。5月に横浜で開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)では、アフリカ開発の今後の方向性について活発な議論が行われ、国際社会の取組を強化していくことをうたった「横浜宣言」が採択された。日本はアフリカのPKOセンターへの支援や貿易・投資促進合同ミッションの派遣など、政治・経済両面における積極的な取組を通じ、TICAD IV及びG8北海道洞爺湖サミットで発表した支援策の着実な実施に努めている。
近年の中南米地域には、鉱物・エネルギー・食料資源の一大供給源としての存在感の増大、経済規模の拡大、民主主義・市場経済の定着及び国際社会における発言力の向上が見られる一方で、貧困・格差等の問題も根強く存在している。
日本は、経済関係の強化、安定的発展に対する支援及び国際社会での連携強化を重視して中南米地域との関係強化に努めている。7月のG8北海道洞爺湖サミットや11月のペルーでのアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の機会には、メキシコ、ブラジル、ペルー、コロンビア等と首脳会談を実施した。
また、2008年は、日本人のブラジル移住100周年、日・コロンビア外交関係開設100周年等の節目の年に当たり、特にブラジルに関しては、「日本ブラジル交流年」として、様々な記念事業が実施された。4月には、東京において、天皇皇后両陛下並びに皇太子殿下の御臨席の下、外務大臣主催記念式典が実施され、6月には、皇太子殿下がブラジル各地を訪問された。これらを契機に日本との交流が強化された。
今日、日本がその領土、国民の生命・財産を保護するためには、伝統的脅威のみならず、大量破壊兵器の拡散、国際テロや海賊等の非伝統的脅威への対応も含め、多面的な安全保障政策が求められる。このため、日本は、適切な防衛力の整備を基盤として、日米安保体制の維持・強化、近隣国との安定した関係の構築、国際社会の平和と安定に向けた取組を引き続き積極的に進めた。
具体的には、米国との間で安全保障分野における幅広い協力を進め、ASEAN地域フォーラム(ARF)を始めとして、二国間・多数国間の対話の枠組みを近隣国との間で重層的に整備・強化してきた。また、国際社会の平和と安定があってこそ日本の国益も実現されるとの思いから、PKOへの参加、インド洋における補給支援活動の再開に加え、平和構築、軍縮・不拡散、海賊対策、国際テロや国際組織犯罪といった諸課題にも積極的に取り組んだ。日本国民の生命及び財産の保護の観点から火急の課題である海賊対策についても、できることから早急に措置を講じていく。
国際の平和と安全の維持に主要な役割を担う国連安保理の改革の早期実現は重要な課題であり、日本は、国際社会において一層の貢献を行うためにも、早期の安保理改革の実現と日本の常任理事国入りを目指して、積極的な外交努力を展開した。また、10月には、日本は安保理の非常任理事国(任期:2009年~2010年)に選出された。
平和構築については、G8北海道洞爺湖サミットやTICAD IVにおいて議論を深めたほか、現場レベルでも国連スーダン・ミッション(UNMIS)への自衛官派遣や、イラク、アフガニスタン等での復興支援等を行った。また、国連平和構築委員会で議長職を務めるなどの知的貢献や平和構築分野での人材育成についても一層取組を強化した。
また、国際組織犯罪対策では、2月の「人身取引対策に関するウィーン・フォーラム」へ日本から政府協議調査団を派遣するなど積極的に取り組んだ。
日本は、国際社会の平和と安定のため、また、唯一の被爆国として、戦後一貫して軍縮・不拡散問題に積極的に取り組んでいる。2008年も、国連総会に核軍縮決議案を提出し、圧倒的な支持を得て採択されたほか、2010年核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議の成功に資するべく、オーストラリアと共に、核不拡散・核軍縮に関する国際委員会を立ち上げた。また、国際原子力機関(IAEA)の活動にも積極的に貢献している。12月にはオスロで「クラスター弾に関する条約」の署名式が行われ、中曽根弘文外務大臣が出席し署名した。原子力の平和的利用に関しては、G8北海道洞爺湖サミットにおいて、いわゆる3S(核不拡散/保障措置、原子力安全、核セキュリティ)の確保のため、日本の提案により、「3Sに立脚した原子力エネルギー基盤整備に関する国際イニシアティブ」を立ち上げた。
科学面では、総合科学技術会議の提言や宇宙基本法の成立・施行を受け、2008年は「科学技術外交」や「宇宙外交」の取組を始動している。

「クラスター弾に関する条約」に署名する中曽根外務大臣(中央) |
地球環境問題は、人類共通の課題であり、国際社会の一致した取組が急務となっている。特に、気候変動問題については、2013年以降の枠組みを決定する、2009年末にデンマークで開催される気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)に向け、議論が活発化している。
日本は、地球環境問題の解決に向け、世界をリードする環境・省エネ国家として、技術力をいかし、ODA等を通じた環境分野での開発途上国支援のほか、多数国間環境条約などの国際的ルールづくりを通じて、地球環境問題への取組を主導してきている。
こうした中、2008年、日本は「環境・気候変動」が主要議題の一つとして位置付けられたG8北海道洞爺湖サミットの議長国として、福田総理大臣が1月にダボス会議において「クールアース推進構想」を発表し、6月に「『低炭素社会・日本』をめざして」と題する政策スピーチを行うなど、公平で実効性ある枠組みの構築に向けて積極的な役割を果たした。その結果、7月のG8北海道洞爺湖サミットにおいて、2050年までに世界全体で温室効果ガス排出量を少なくとも半減するという目標をすべての条約締約国で共有すること等につき米国も含め意見が一致するなどの成果が得られた。
日本は、近年、山積する地球規模課題に対応するため、国際協力の戦略性の強化とより一層の効果的実施に取り組んでいるが、2008年は、開発・アフリカを主要議題とする国際会議の開催、新JICAの発足等を通じ、日本の国際協力が国際的に注目される年となった。
2008年、日本はG8議長国として、4月にG8開発大臣会合を主催した。7月のG8北海道洞爺湖サミットにおいては、環境・気候変動、開発・アフリカ等を主要議題として議論し、G8としてミレニアム開発目標(MDGs)の達成に向けた決意を表明した。また、G8北海道洞爺湖サミットに先立ち、5月には横浜で第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)を開催し、日本は2012年までの対アフリカ援助の倍増等の支援策を打ち出した。
2008年10月には、政府開発援助のより一層の効果的実施を図るため、国際協力機構(JICA)と国際協力銀行(JBIC)海外経済協力部門が統合され、技術協力、有償資金協力及び無償資金協力の三つの援助手法を一元的に実施する機関として新JICAが発足し、開発途上国の需要に応じたより質の高い国際協力を実現するための体制が整えられた。

G8北海道洞爺湖サミットでの記念撮影に臨む福田総理大臣(中央)とG8首脳(7月8日、北海道洞爺湖) |
2008年は、前半には食料・原油価格が高騰、後半には、米国のサブプライムローン問題を契機とした金融危機が深刻化し、世界的な景気後退が起きるなど、世界経済にとって激動の1年となった。
11月、ワシントンでの金融・世界経済に関する首脳会合において、麻生総理大臣は自国の金融危機を克服した経験を踏まえて、金融機関の不良債権の迅速な処理と、公的資金による資本注入の必要性を提言した。同会合で打ち出された具体的な行動計画については、直後に開催されたアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議において、APECメンバーにも拡大して支持された。
2001年の交渉開始後、丸7年が経過した世界貿易機関(WTO)ドーハ・ラウンド交渉について、7月にジュネーブで閣僚会合が開催され、農業及び非農産品市場アクセス(NAMA)のモダリティ(関税削減方式)の合意に向けて急速に協議が進んだが、最終的には農業分野の開発途上国向け特別セーフガード(SSM)に関する関係国間の対立を原因として合意には至らなかった。世界的に保護主義が台頭しかねない状況の中、ラウンドの早期妥結に向けて日本を含む関係主要国が引き続き交渉の進展に取り組んでいる。
日本はまた、WTOを補完する取組として、経済連携協定(EPA)も積極的に推進している。2008年はインドネシア、ブルネイ、フィリピン、さらにはASEAN全体との協定が発効したほか、同年12月にはベトナム、2009年2月にはスイスとの協定が署名に至った。湾岸協力理事会(GCC)、インド、オーストラリアとは、2009年2月末現在交渉中であり、交渉中断中の韓国とも、2008年には日韓経済連携協定交渉再開に向けた検討及び環境醸成のための実務協議を2回実施した。また、地域の経済連携に関する研究・検討にも積極的に貢献している。
投資協定に関しては、7月にカンボジア、8月にラオスとの間で協定が発効したほか、ウズベキスタン、ペルーとの間で、それぞれ8月、11月に協定の署名に至った。
自由貿易・投資の促進と並んで経済外交において重要な柱となるのは、エネルギー資源や食料資源の確保といった経済安全保障の強化である。エネルギー資源について、日本は、生産国との関係強化や国際エネルギー機関(IEA)などの国際機関との連携強化等を通じて、安定供給の確保、市場の安定化等に努めている。食料分野については、6月の国連食糧農業機関(FAO)ハイレベル会合、7月のG8北海道洞爺湖サミット等の機会を通じて、世界及び日本自身の食料安全保障強化のために首脳レベルの外交を展開した。
政治、経済、社会、文化を含む幅広い分野で、各国の国民に日本への理解を深めてもらうことは、日本に対するイメージの向上及び信頼感の増進につながり、各国との友好関係や確固たる国際的地位の構築に寄与する。日本は、相手国の政府のみならず、世論形成に影響力のある有識者や国民一般に直接働き掛けるパブリック・ディプロマシーの取組を積極的に推進している。2008年、日本文化や日本語を相手国市民に伝えるボランティアを派遣する「日本文化発信プログラム」が発足し、26名が2009年1月にハンガリー、ポーランド、ブルガリア、ルーマニアへ派遣された。この活動は、将来の日本との友好関係の中核となる人材の育成につながることが期待されている。また、日本アニメへの関心を通じて日本への理解を深めてもらう「アニメ文化大使」事業を立ち上げ、3月にドラえもんがアニメ文化大使に就任した。世界各国で劇場版映画を上映した取組は現地メディアでも大きく取り上げられている。現在、世界で300万人程度の日本語学習者がいるが、その人数は30年間で20倍以上に増加している。海外での日本語普及は、将来の日本との交流の担い手を育てるものであり、今後も積極的に取り組んでいく方針である。

外務省でアニメ文化大使就任式に臨むドラえもん(中央)と高村外務大臣(左) (3月19日、東京) |
外務省は、海外における日本人への支援を中心とする領事業務を外交業務と並ぶ主要業務と位置付けている。年間1,700万人を超える国民が海外に渡航している現在、領事業務に対する国民の期待も、以前と比較にならないほど増大している。外務省では、こうした国民からの声を踏まえ、安全確保に関する情報提供、事件・事故発生時の邦人援護、パスポートの発給・更新、在外選挙の実施、海外在住者の生活に密着する戸籍事務など多岐にわたる領事業務とその実施体制の強化及びサービス向上に積極的に取り組んでいる。
また、外務省は、国民の幅広い層の理解と支持を得て外交を推進するため、地方自治体・企業やNGOとも協力しながら、オールジャパン体制の強化に取り組んでいる。また、外交政策について国民の幅広い理解を得るため、インターネットなど各種メディアや各種行事を通じ、国民との双方向コミュニケーションの強化を図っている。
国民と共にある外交を更に推進していくためには、在外公館の新設や、外務省職員の主要先進国並み水準への増員、情報の収集、分析機能強化といった外交力の基盤強化が欠かせない。今後とも、海外における日本国民の利益保護を始め、国益を踏まえた外交を展開するため、こうした外交力の強化にも積極的に取り組んでいく。