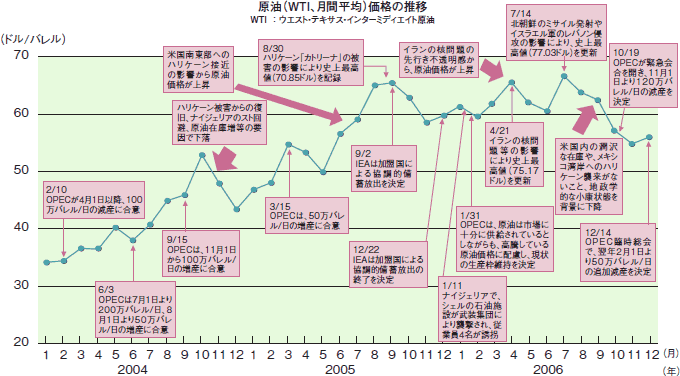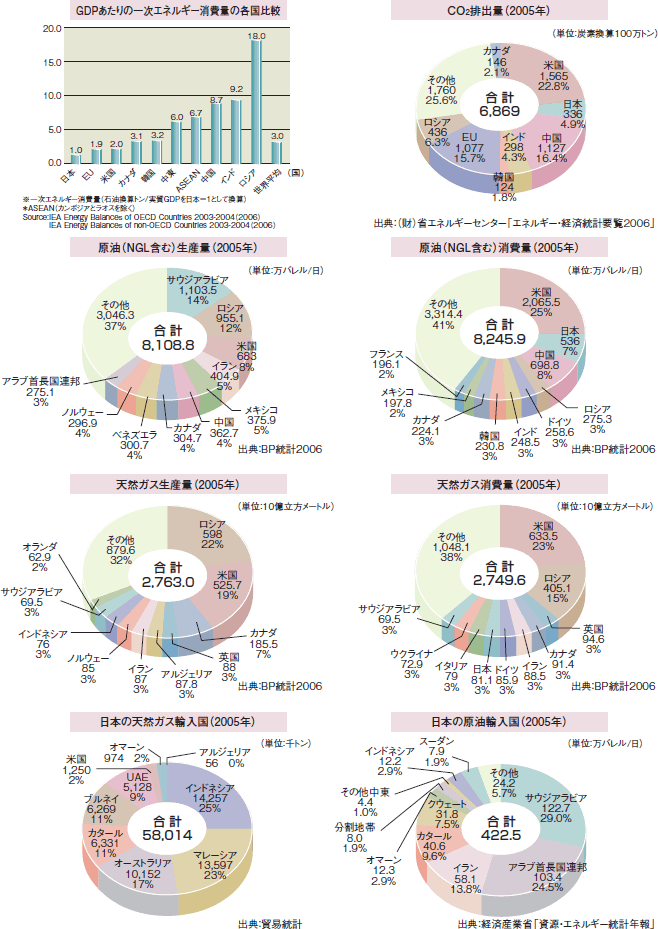7月、ロシアが議長国を務めたG8サンクトペテルブルク・サミットにおいて、主要議題の一つとして、「エネルギー安全保障」がとりあげられた。G8各国首脳は、「世界のエネルギー安全保障」との文書を採択し、国際社会が協力して取り組むための課題 (注23) に効果的に対処するための「行動計画」を作成した。日本は、G8のこのような経緯も踏まえて、各国と協力しながら以下のような外交政策を進めている。
(イ)安定供給の確保
エネルギー市場の安定化を実現し、日本へのエネルギー安定供給を確保するため、エネルギー生産国との関係強化、中東地域の安定 (注24) 等の環境整備等に努めている。具体的には、4月のサウジアラビア皇太子の訪日、7月のG8サミット、8月の小泉総理大臣のカザフスタン、ウズベキスタン訪問、11月のAPEC首脳会議、ユドヨノ・インドネシア大統領の訪日等の機会をとらえて、首脳レベルで生産国との一層の関係強化に努めた。一方で、資源輸入先の多様化に向け、ロシア等との関係強化にも力を入れている。また、エネルギー輸送路等の安全確保のため、シーレーン沿岸国に対する航行安全、海上取締り等の分野での支援強化等を実施している。
(ロ)エネルギー効率向上の世界への伝播及び代替エネルギー普及への取組
日本は、1960年~1970年代の公害問題や石油ショック以降、官民を挙げて省エネ推進に取り組んだ結果、世界で最もエネルギー効率の高い国の一つとなった。3月、外務省において、「中国、インド、ロシアに関するエネルギー安全保障」セミナーを開催したほか、7月のASEAN+3外相会合等あらゆる外交上の機会をとらえて、エネルギー需要が増大する中国、インド等アジア諸国との対話を進めてきた。
また日本は、ASEANやブラジルとはバイオ燃料面での協力の可能性について首脳レベルで話し合った結果を受けて、具体策を検討してきた。さらに、各国の実情にあわせた小規模水力発電、風力、太陽光発電等のテーラーメイドの支援が重要であるとの考え方をG8サミットや4月の国際エネルギー・フォーラム(IEF)等の場で主張し、各国の理解を深めた。
(ハ)多国間協力とルールの強化
ますます多くの国が資源エネルギーに対する国家管理を強める傾向にある中、国際的な規範の形成及び遵守の働きかけは、国際対話の推進とともに、今後も大きな課題である (注25) 。
こうした点において、国際エネルギー機関(IEA)は重要な役割を果たすが、12月には、日本の候補である田中伸男OECD事務局科学技術産業局長が次期IEA事務局長に選出された(2007年9月就任予定)。IEAは、緊急時の石油備蓄協調放出、環境とエネルギーの両立のための技術研究等、重要な活動を行っており、日本としては関係国と協調しつつ、IEAを一層戦略的に活用していく。
また、エネルギー憲章条約は、エネルギー原料・産品の貿易及び通過の自由化並びにエネルギー分野における投資の自由化・保護等について規定する唯一の国際約束である。11月には、同条約の最高意思決定機関であるエネルギー憲章会議において、河村武和欧州連合日本政府代表部大使が2007年1月に議長に就任することが決定された。日本は、貿易の自由化、投資環境の強化を通じてエネルギー安定供給を確保するとの目的を持ち、ロシアによる同条約の批准、アジアへの加盟国の拡大に向けて貢献している。
さらに、関連する国際機関を通じて、エネルギー・鉱物資源の安定供給に向けて、各国の生産・消費・輸出入動向の把握に努めている。
(ニ)原子力外交の推進
原子力発電は、日本の総発電量の約3分の1に達しており、基幹電源となっている。資源小国である日本は、ウランの安定供給を確保するため、供給国との二国間関係の強化等の外交努力を行っている。さらに、核不拡散、原子力安全及び核セキュリティーを確保した形での原子力エネルギーの利用の推進は、国際的なエネルギーの安定供給に資する。このため、日本は、IAEAをはじめとする多国間での枠組みを通じて、様々な協力を実施しており、また、将来の原子力システムを開発するための「第4世代原子力システムに関するフォーラム(GIF)」、「国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)」などの国際的な取組にも積極的に参加している。