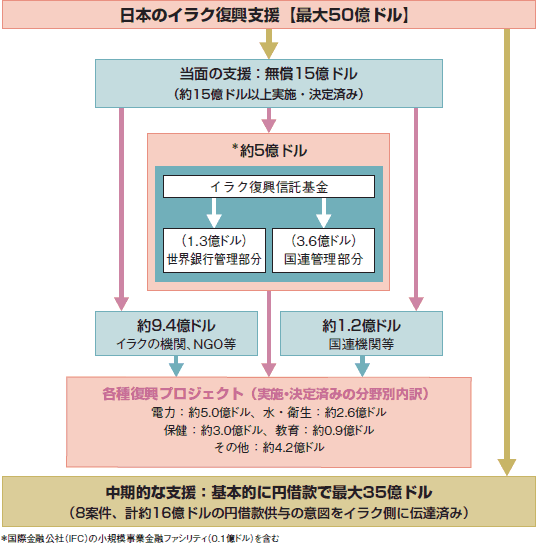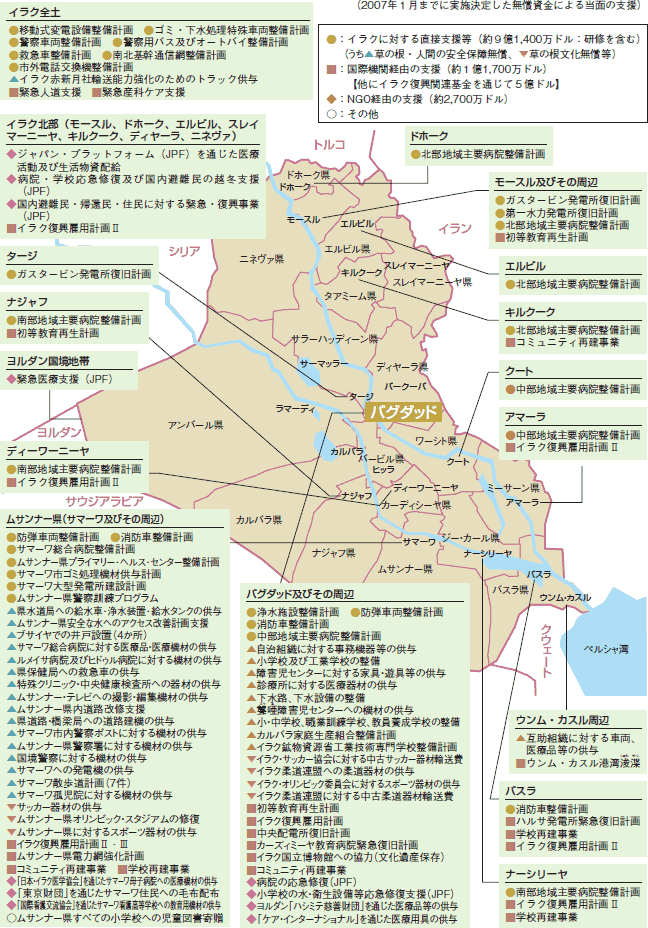イラクが平和的な民主的国家として再建されることは、中東地域の安定に不可欠であり、特に同地域に原油供給量の9割を依存する日本にとっては国益に直結する問題として極めて重要である。またイラクが不安定化すればテロの温床となりかねず、イラクの再建は、国際社会共通の課題といえる。国連安保理決議が加盟国等に対しイラクの復興を支援するよう求め、米国をはじめとする各国及び国連等の国際機関が実際に支援を進める中で、日本も、国際社会の責任ある一員として日本にふさわしい支援を行う必要がある。こうした認識の下、自衛隊をイラクに派遣するとともに、ODAを供与し、これらを「車の両輪」として最大限努力してきている。こうした日本の取組は、国際社会やイラクの人々から高い評価を得ている。8月3日、麻生外務大臣がイラク・バグダッドを訪問し、マーリキー首相及びズィーバーリー外相と会談した際や、シャハリスターニー石油相が10月の来日時に麻生外務大臣と会談した際には、イラク側から、日本の支援の継続を要請するとともに、これまでの取組に深い謝意が表された。日本側からは今後ともイラク復興支援に取り組む姿勢に変わりない旨を伝えた。
(イ)ODAによる支援
日本は2003年10月、イラク復興支援のための「当面の支援」として、15億ドルの無償資金(電力、教育、水・衛生、保健、雇用等のイラク国民の生活基盤の再建及び治安の改善を重点)、中期的な復興ニーズに対する円借款を中心とする最大35億ドルの支援(円借款では主に経済社会インフラ整備を支援)、からなる最大50億ドルのイラク復興支援を表明した。無償資金協力については、15億ドルの使途をすべて決定し、現地で次々と支援が実を結びつつある。円借款については、12月時点までに運輸、エネルギー、産業プラント及び灌漑等分野の8案件(総額約1,827億円=約16億ドル)に対する支援の意図を表明した。
(ロ)自衛隊による支援
日本は2003年、イラク人道復興支援特別措置法に基づき、同法に基づく対応措置を制定し、その対応措置に関する基本計画を閣議決定した。これに基づき2004年初めから、自衛隊がイラクに派遣され、サマーワを中心とした医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備といった人道復興支援活動等が行われた。陸上自衛隊については2006年6月、活動目的を達成したとして、その活動を終了させることを決定し、9月にはすべての人員の帰国が完了した。
航空自衛隊部隊については、5月、アナン国連事務総長来日の際、同事務総長から小泉総理大臣に対して、イラクにおける国連の活動について人や物資の空輸支援要請があったことを受け、従来の多国籍軍への支援を継続するとともに、国連への支援も行うこととし、クウェートから新たにバグダッド及びエルビルへの空輸を開始した。