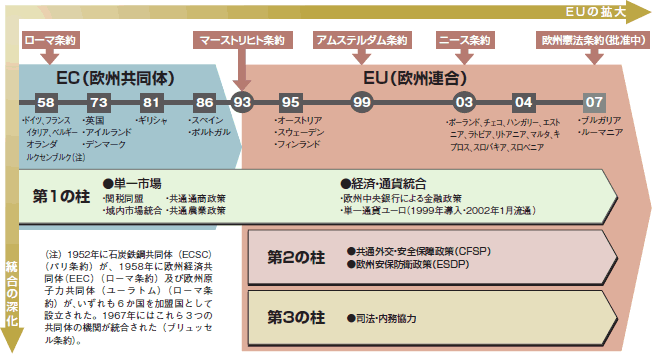2.各 論
(1)EU情勢
(イ)政治情勢
欧州憲法条約の批准が2005年にフランスとオランダの国民投票で否決されたため、EUは「熟慮の期間」を設けて対応を検討してきたが、2006年6月の欧州理事会で、既存の基本条約の枠内でEU諸機関の改革を行いつつ、批准プロセスを継続することが合意された。また、ドイツ議長国(2007年前半)の下、欧州憲法条約に関する議論の現状をとりまとめた報告書を作成し、フランス議長国(2008年後半)中までに必要な作業を行うことが合意された。
EU拡大については、2005年9月に欧州委員会が発表した報告書において、ブルガリア及びルーマニアの2007年1月1日付のEU加盟が勧告され、予定どおり加盟を果たした。加盟候補国のうちクロアチアとトルコとの間では2005年10月に正式な加盟交渉が開始されたが、トルコについては、人権問題など解決すべき法的ハードルが多いことに加え、キプロス問題が交渉に悪影響を与えており、欧州委員会は2006年11月、加盟交渉の一部凍結を勧告した。また、EU内においても、欧州憲法条約の今後について展望が明確でない中、更なる拡大の前に機構改革が必要であり、「新規加盟国を統合する能力」への配慮を必要とするという、拡大に消極的ともいえる意見が強まった。
EUは外交面で様々な取組を進めている。具体的には、域内においてエネルギー安全保障への関心が高まっていた中、ロシアが2006年1月にウクライナへのガス供給を停止したことから、EUにおけるエネルギー戦略に関する議論が活発化した。イランの核開発問題では英国・ドイツ・フランスのいわゆる「EU3」及びソラナ共通外交・安全保障政策(CFSP)上級代表がイランに対する働きかけを積極的に行い、国連安保理決議の採択で中心的な役割を果たした。また、北朝鮮の核実験の際にもEUはいち早く反応し、北東アジアにおける安全保障環境につき、日本と懸念を共有した。平和構築の分野では引き続きマケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナでEUの部隊を展開するほか、コンゴ民主共和国のEU部隊は同国での大統領選挙の実施を支援し、12月に任務を終了して撤退した。
(ロ)経済情勢
欧州経済は、設備投資をはじめとする内需の力強さ、世界経済の好調による輸出の拡大等により成長した。2006年通年の成長率(前年比)は、ユーロ圏で2.6%、EU25か国で2.8%となる見通しである。また、失業率は、2004年にEU25か国で9.1%、ユーロ圏で8.9%まで増加したが、2006年は共に8.6%まで低下する見込みである。
ユーロ圏経済が成長する中、欧州中央銀行は、中長期的な物価安定に対する上方リスクを考慮し、緩和的な金融政策を調整するため、2005年12月の2.25%から累次主要政策金利を引き上げ、2006年12月現在で3.5%とした。一方、英国では、8月に引き続き11月に政策金利をそれぞれ0.25%ずつ引き上げ5%とした。インフレ率は、2006年にEUは2.3%、ユーロ圏は2.2%と安定し、コアインフレ率は低下しており、原油価格の上昇による二次的効果はさほど現れなかった。また、欧州委員会によればユーロ圏のインフレ率は、2008年にインフレ参照値(2%)を下回る水準になる見通しである。
安定成長協定の下、EU加盟国は財政赤字を対GDP比3%以下に抑えるなどの財政規律の遵守が義務付けられているが、約半数の加盟国が、過去に同基準を満たせず、過剰財政赤字状態にあるとして、現在も監視下にある。なお、2006年は予想以上の税収増により、5つの加盟国を除きGDP比3%を下回る見通しである。
2004年にEUに加盟した10か国のうち、リトアニアとスロベニアは2007年1月からのユーロ導入を申請し、スロベニアについては、欧州委員会及び欧州中央銀行による審査を受けてユーロ導入が決定された。しかし、リトアニアについては、インフレ率が基準値を上回ったため、導入は見送りとなった。