(3)日本のNGO等の活躍
【総 論】
NGO等による国際協力活動は、開発途上国の多様なニーズに応じたきめ細かな援助や迅速かつ柔軟な緊急人道支援活動が実施できる観点から、また、「日本の顔の見える支援」という観点からも重要である。近年、NGO等は開発援助、緊急人道支援のみならず、環境、人権、貿易、軍縮・不拡散、国際組織犯罪等の分野において様々な活動を行ってきており、国際社会においてますます大きな役割を果たすことが期待されている。
政府としても、NGO等が果たす役割の高まりを認識し、2003年に改訂されたODA大綱では「NGOとの連携を進める」と定め、2005年に策定された新ODA中期政策では、NGO等との連携、協働が随所でうたわれた。
政府は日本のNGOの活動強化を図るため、NGOの海外活動に資金協力し、また日本のNGOの基盤強化に向けた各種協力やNGOとの対話・連携を実施している。
(イ)開発援助分野
(i)日本のNGOの活躍
日本のNGOは世界各地で活躍しており、2005年に政府資金が提供された主な活動には次のようなものがある。
(a)日本NGO支援無償資金協力(日本のNGOの海外活動に政府資金を提供する仕組み)では、29か国で70件、約12.3億円が提供された。主な対象国としては、カンボジア(8件)、ベトナム(6件)、スリランカ(6件)、アフガニスタン(6件)、ケニア(5件)などがある。また事業としては、学校の再建、医療協力・母子保健、被災者支援、農村開発、地雷・不発弾除去等がある。
(b)ジャパン・プラットフォーム(JPF:官・民・NGOが協力して、災害時に日本のNGOが迅速に緊急人道支援を行う仕組み。図表「外務省とNGOとのパートナーシップ」参照)を通じ、2005年には政府資金で50件(21.09億円)、民間資金で17件(2.2億円)の支援が実施された。対象は、スマトラ沖大地震被災者支援、ダルフール難民支援、リベリア帰還民支援、イラク支援、パキスタン等大地震被災者支援等である。
▼外務省とNGOとのパートナーシップ
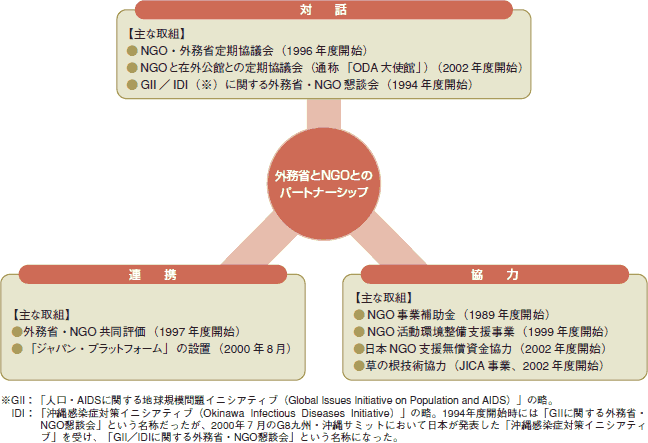
(ii)NGOの活動への政府の協力
NGOの活動への資金協力の形態としては、従来のNGO事業補助金や草の根無償資金協力に加えて、2002年に日本NGO支援無償資金協力を、2003年には草の根技術協力を新設した。日本NGO支援無償資金協力は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発活動に対して事業資金を提供する制度で、2002年の設立当初には20億円であった予算は、2005年度には28.5億円に増加した。外務省ではNGOとの協議を通じてNGO側より提出された提案をもとに、この制度の改善を図る一方、資金の適正使用を確保するため全対象事業について外部監査を義務付けている。草の根技術協力は、日本のNGO等と国際協力機構(JICA)が開発途上国の地域住民の生活向上に直接役立つ技術移転事業を協働して実施するもので、2003年度の設立当初の予算は10.9億円であったが、2005年度は19.4億円を拠出した。
災害時等にNGOが行う緊急人道支援活動については、後述のとおりJPFの枠組みで日本のNGOが迅速かつ効果的な支援活動を行うことができるよう、2001年度から政府資金を拠出し、民間資金とともに支援事業に当てられている。
(iii)NGOのキャパシティ・ビルディング(能力強化)への政府の協力
日本のNGOの多くは、国際協力において一層の活躍をするため、その専門性や組織運営能力の強化が必要である。このため、外務省やJICA、国際開発高等教育機構(FASID)が、政府資金により様々なプログラムを実施している。
外務省は2005年、災害復興、障害者支援、保健分野支援における分野横断的取組の3つのテーマでNGO研究会を開いた。さらに、NGO相談員(国民、NGOの相談先として政府が委嘱)を17名配置して各種照会に対応したほか、NGO専門調査員(NGOの専門性を高めるためNGOに派遣する者)11名をNGO11団体に派遣した。このほか、海外NGO等と共同で「NGO活動における危機管理セミナー」を開催した。
(iv)NGOと政府との対話・連携
外務省は、1996年以来年4回実施されていたNGO・外務省定期協議会を、2002年度から全体会議(年1回)、ODA政策協議会と連携推進委員会の2つの小委員会(各年3回)に改編し対話・連携に努めている。2005年は、全体会議が5月に、ODA政策協議会が2月、7月、12月に、連携推進委員会は3月、7月、10月に開催され、討議の模様は外務省ホームページで公開されている。ODA政策協議会では援助政策について討議がなされ、連携推進委員会では日本NGO支援無償資金協力の制度を使いやすくするための議論が進んだ。
日本のNGOが多く活躍する開発途上国において、大使館関係者、JICA、国際協力銀行(JBIC)及びNGO関係者がODAの効率的・効果的実施を協議する「ODA大使館」制度が2002年度から開始され、これまでにカンボジア、バングラデシュ、ケニア等12か国で実施されている。
外務省はまた、2002年11月からNGO担当大使を設置している。NGOと外務省の意見交換・情報交換の機会に双方の橋渡し役として参加するとともに、NGOとの対話・協力の機会が多く予定される国際会議等に際しても、NGOに対する協力を行っている (注4) 。
(v)緊急人道支援への対応:ジャパン・プラットフォーム(JPF)
JPFは、大規模自然災害や紛争の被害者に対して、日本のNGOが官・民の資金を活用し迅速で効果的な緊急人道活動が行えるよう、2000年8月にNGO、政府、経済界が協力して設立したシステムであり、現在、23のNGOが参加している。外務省は2001年度からJPFに政府資金を供与しており、2005年末までの間に、政府資金では累計103件で約48.4億円が供与された。
2004年末のスマトラ沖大地震及び2005年のパキスタン等大地震に際しては、JPFが迅速な緊急人道支援活動を行った。パキスタンでは12月、JPF事務局及び傘下のNGOが国際機関及びパキスタン政府、地方政府と連携し、被災者の越冬を支援するため、タンドリ地域に「キャンプ・ジャパン」を設置し運営に当たっている。これは被災地において、NGOを中心に国際機関や被災国政府が連携した模範例となっている。
(ロ)その他の分野
人権分野では、主要人権6条約の実施に関連して多くのNGOが条約の普及等の活動をしており、政府は人権条約委員会 (注5) に定期的に提出する政府報告の作成に当たり、NGOとの対話を実施しているのみならず、NGOと密接に連携をとっている。
児童の権利条約関連では、近年、グローバル化や情報社会の発展により、児童買春や児童ポルノ等、児童の性的搾取の問題が深刻化しているが、こうした問題でNGOが果たす役割は大きく、政府もNGOの活動に協力してきている。
2月から3月には、1995年に開催された第4回世界女性会議(北京会議)から10周年を記念して、第49回国連婦人の地位委員会(「北京+10」ハイレベル会合)が国連本部(ニューヨーク)で開催された。日本政府代表団にはNGO関係者3名が顧問として参加し、会議の議論に貢献するとともに、政府とNGOの橋渡し役として活動した。
「障害者権利条約」(仮称)の交渉は現在、国連の場で行われている。各会合の日本政府代表団には障害者自身が顧問として加わり、日本の障害者NGOも交渉の場に参加するとともに関連セミナーを主催するなど、国際的にも顕著な活動で評価されている。
国際組織犯罪分野では、人身取引問題についてNGOと意見交換している。政府は内閣官房に関係省庁連絡会議を設置し、包括的な人身取引対策行動計画を策定するなど諸施策を実施しているが、その過程で定期的にNGOと協議の場を設け、現状把握や保護策について率直な意見交換を行っており、NGOが重要な役割を果たしている。また、2006年2月、外務省はNGOとの協力の下、人身取引の根絶に向けた国際シンポジウム(国立女性教育会館及び国際移住機関(IOM)との共催)を東京で開催した。
環境分野では、環境教育について率直な意見や情報の交換を行う機会を提供する観点から、日本は2004年から年1回、アジア協力対話(ACD)のプライム・ムーバー・プロジェクト (注6) として、環境教育推進対話を開催してきている。この対話には、政府関係者のみならず、国際機関、NGO、研究者、民間企業等あらゆる関係者が参加してきており、9月に東京・横浜で開催した第2回対話では、21か国から約60名が参加し、「国連持続可能な開発のための教育の10年」を念頭に、「生産と生活のグリー
ン化」というテーマで活発な議論が行われた。各国から優良事例が紹介されたほか、生産の中心である企業での取組、生活の中心となる家庭や地域での取組について、政府やNGO等がそれぞれの立場から意見を述べ、有意義な議論が行われた。貿易面では、現在進められている世界貿易機関(WTO)ドーハ・ラウンド交渉を成功に導くために、政府としては民間団体等の理解と協力が不可欠であると考えている。12月のWTO第6回閣僚会議(香港閣僚会議)に関して、11月に外務省主催で民間団体等を対象とした説明会を開き、同会議中もNGO等への説明や意見交換を随時行うなど、昨年に引き続きNGOとの連携を図ってきている。
軍縮・不拡散分野においても、NGOとの連携がますます進んできている。5月の核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議の際には、河井外務大臣政務官がNGOと意見交換するなど、NGOの意見が同会議の成果に適切に反映されるように努めた。小型武器、対人地雷等の通常兵器の分野では、外務省は、カンボジア、タイ、スリランカ、アンゴラ等で地雷対策に取り組んでいる現場のNGOに「日本NGO支援無償資金協力」を通じ、資金面で協力してきている。
国連改革に関しては、「平和」、「開発」、「人権」の関連性が重要視されている。9月の国連首脳会合に向けて、8月にNGOと外務省の共催で「国連改革に関するパブリック・フォーラム」を開催し、日本がいかなるビジョンを持って国連改革を推進するかについて、セクターを越えて広くNGO、国際機関及び外務省関係者間で政策対話を行った。国連改革について市民社会と率直で建設的な意見交換を行うことは、外務省、NGOの連携の上で画期的であった。今後も、同様のフォーラムを続けていくことが有益である。

