2.経済連携協定(EPA)の推進
日本は、WTOを中心とする世界的な貿易自由化の推進を対外経済政策の基本としてきているが、WTOを補完するものとして、EPAを通じて国と国との多様な経済関係に即した新しい国際ルールづくりを推進している。
グローバル化の深化によって従来の「国家」を単位としてその「国境」を越える形を基本とした国際経済関係は性格を変え、国民と国民が直接かかわり合う、言わば面と面が重なり合うような経済・社会の実態が生じている。
特に日本と東アジア諸国との経済関係は急速に深化・発展しており、こうした実態にふさわしい法体系を形成する必要から、日本は、国境を前提としたモノの交易を中心とする自由貿易協定(FTA)を越えて、投資、サービス、知的財産、協力等の幅広い分野を対象とするEPAを推進している (注13) 。こうしたEPAの包括的な性質のために、交渉には多大な努力を要するが、交渉の加速化のために政府全体として様々な工夫をしてきている。
12月、マレーシアのクアラルンプールで開催された小泉総理大臣とアブドラ首相との首脳会談で、日・マレーシアEPAが署名された。二国間の貿易投資拡大・自由化の枠組みを提供し、幅広い分野における両国の連携を図る本協定は、東アジア諸国とのEPA交渉進展の大きな推進力となるものである。
タイ及びフィリピンとの間でも交渉を進めている(注:タイとのEPAについては、2006年2月初めの交渉において条文が基本的に確定した)。
▼日・マレーシアEPA<協定の概要>
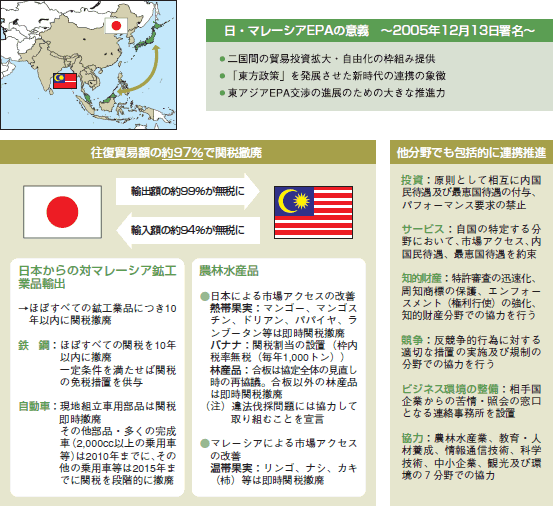
インドネシアとの間では、3回にわたって開催された「共同検討グループ」の報告を受け、6月、東京で開催された小泉総理大臣とユドヨノ大統領との首脳会談で、二国間交渉立ち上げについて首脳間で合意した。交渉は7月に開始され、現在進行中である。
こうしたASEAN諸国との二国間交渉と並行して、ASEAN全体との間でも、包括的経済連携協定の交渉を行っており、12月の日・ASEAN首脳会議では、4月の交渉開始から2年以内に交渉を終えるよう最善の努力をすることで一致した。この協定は、日本のEPAに新たな地平をひらくものであり、交渉は加速されつつある。
ベトナム及びブルネイとの間では、ASEAN全体との交渉の一環として、4月から二国間協議を実施してきたが、12月の両国との二国間首脳会談では、二国間のEPA交渉立ち上げに向けた準備協議を開始することで一致した。
韓国との間では、2003年12月の第1回交渉以降、これまでに6回の交渉会合を重ねてきたものの、韓国側は依然として物品の関税撤廃交渉を開始することに慎重な構えを示している。日本としては、早期に交渉のテーブルに着くよう、韓国側に粘り強く働きかけている。
日中韓三国間では、投資に関して、2004年11月の首脳会議で「ビジネス環境改善のための政府間メカニズム」及び「投資関連の法的枠組みに関する政府間協議」という2つの政府間協議の創設が合意された。2005年から政府間協議を開始し、これまでに4回協議を開催した (注14) 。
▼経済連携強化に向けた取組の現状(2006年2月現在)
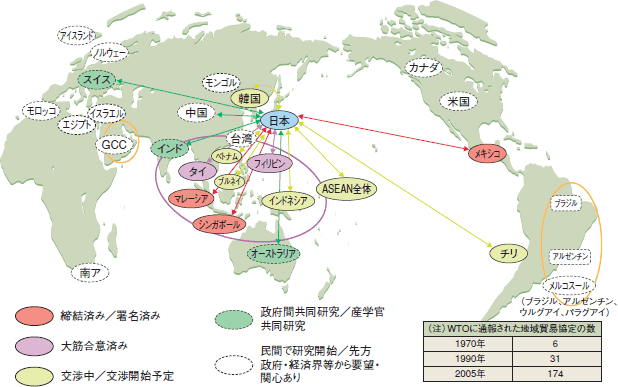
インドとの間では、EPAの可能性を含め、経済関係強化の在り方について包括的に協議するための共同研究を7月から開始した。この共同研究会は、2006年6月に報告書を提出する予定であり、その中で、インドとのEPA交渉立ち上げについても積極的に検討していくことになる。また、エネルギー安全保障の観点から重要な湾岸協力理事会(GCC)との間でも、早急にFTA交渉を開始する方向で作業を加速していく。
さらに、オーストラリア及びスイスとの間でも、経済関係の強化の在り方について政府間の共同研究を行っている (注15) 。
中南米地域に目を向けると、既にEPAが発効したメキシコに続き、1月以来、チリとの間で4回の共同研究会合が開催され、11月のAPEC首脳会談の際の小泉総理大臣とラゴス大統領との首脳会談でEPA交渉の立ち上げに合意した。チリは、銅鉱石等の豊富な資源を有しており、また民主主義の定着、経済の近代化に成功した国である。チリとのEPA締結により、南米地域における拠点を確保することも期待される。