内政面では、改革派のこれまでの成果に対して国民の失望感が広がる中、第9期大統領選挙が6月に実施され、決選投票の末、「貧困、汚職、差別の撲滅」を訴えた強硬保守派のアフマディネジャード・テヘラン市長が1,700万票(得票率62%)を得て大勝した。8月に就任した大統領は組閣に着手し、国会の信任投票ではモッタキ外相(元駐日大使)等が信任されたが、石油相候補を含め4人が否決された。11月に教育相、協同組合相、福祉社会保障相の3閣僚が信任されたものの、石油相候補者は信任票が得られず、12月になってようやくハーマーネ石油相代行が石油相に信任された。経済状況の改善に対する国民の期待に、新政権がこたえられるかが注目される。
外交面では、前年に引き続き同国の核問題が国際社会の注目を集めた。8月、長期的取決めに関するEU3(英国、フランス、ドイツ)の提案の内容を不満として、イランは直ちにこれを拒否、累次のIAEA理事会決議の要求事項と2004年11月のEU3とのパリ合意に反して、ウラン転換活動を再開した。これを受け、再開直後にIAEA特別理事会が開催され、イランに対し深刻な懸念を表明するとともに、ウラン転換活動の再停止などを求める決議が無投票で採択された。その後もイランはウラン転換活動を停止しなかったため、9月のIAEA理事会では、賛成多数(賛成22(日本を含む)、反対1、棄権12)で決議を採択した。その後、イランによるウラン転換活動の再開以降中断している交渉の再開に向けた外交努力が続けられたが、事態の打開につながるような合意は得られず、2006年1月には、イランはウラン濃縮関連活動を再開した。これを受け、2月に開催されたIAEA特別理事会では、本件を国連安保理に報告すること等を内容とする決議が賛成多数で採択されたが、その後、イランは、国内の研究施設でウラン濃縮活動を再開した。
▼イランの核問題を巡るクロノロジー
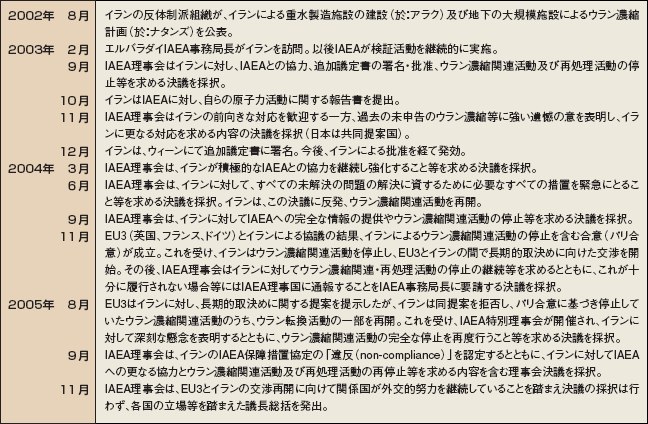
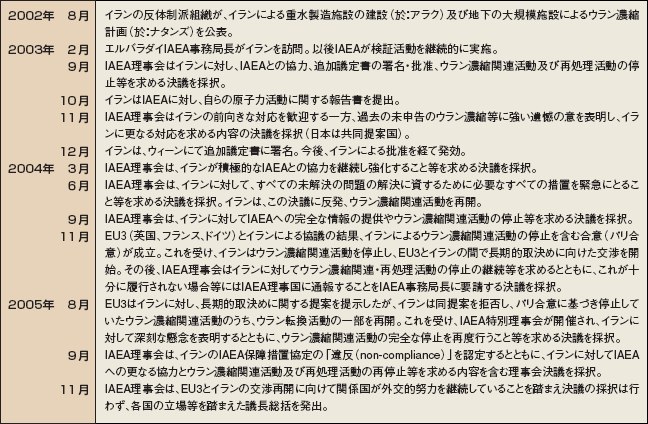
新政権は、近隣諸国やイスラム諸国との関係拡大などを優先政策として掲げ、モッタキ外相は10月にクウェート、アラブ首長国連邦、カタール、オマーン、バーレーンを、11月にトルクメニスタン、シリア、エジプト、アゼルバイジャン、トルコを訪問した。他方、アフマディネジャード大統領によるイスラエルの存在や第2次世界大戦中のナチス・ドイツによるユダヤ人迫害(ホロコースト)の事実に疑問を示す発言(10月、12月)は、西側諸国を中心に激しい反発を招いた。
5月のハラズィ外相のイラク訪問に続き、7月にジャアファリー・イラク首相が同国首脳としてはイラン・イラク戦争(1980年~1988年)後初めてイランを訪問した。これ以後、イラクからイランへ閣僚級の訪問が続いている。また、4月にトルコで行われたイラク周辺国外相会合や6月にブリュッセルで行われたイラク支援国際会議にハラズィ外相が出席するなど、イランの積極的な姿勢が示された。
日本は、中東地域の大国であるイランが国内改革や国際社会との関係拡大を推進し、中東地域や国際社会の平和と安定のために一層積極的役割を果たすよう、活発な政治対話を通して同国に働きかけてきている。特に、核問題については、日本は唯一の被爆国としての立場から、1月の逢沢外務副大臣のイラン訪問、5月のNPT運用検討会議、9月の国連総会の場での日・イラン外相会談、11月のバーホナル国会第一副議長の訪日などの機会を通じて、イランが累次のIAEA理事会決議のすべての要求事項を誠実に履行するよう働きかけている。
3月から4月にかけて、「愛・地球博」の博覧会賓客として、シャリアトマダリ商業相が訪日したほか、8月にJICAのテヘラン事務所が開設され、7月に日本で行われた世界文明対話フォーラムにイランから参加者を得るなど、経済・文化などの面で活発な交流が行われた。