【重点課題・分野別ODA】
<貧困削減>
貧困削減は、国際社会が共有する重要な開発目標となっており、新しいODA大綱においても重点課題の筆頭に掲げられている。日本は、「教育、保健、医療・福祉、水・衛生、農業」といった分野、すなわちMDGsの根幹をなす基礎生活分野における協力を重視しつつ、途上国の人間開発、社会開発を支援している。
<持続的成長>
途上国の安定と発展にとって、持続的成長は不可欠な要素であり、また、経済成長を通じて貧困削減を達成するというアプローチは重要であることから、日本は、途上国の持続的成長を支援するため、経済活動上重要となる経済社会基盤の整備とともに、経済分野における政策立案、制度整備や人づくりといった支援を通じて貿易・投資を促進させることや、民間セクターの育成及び技術移転の促進を通じ、被援助国の経済成長を支援することを重視している。
(開発途上国の自助努力支援~民主化支援~)
良い統治(グッド・ガバナンス)に基づく途上国の自助努力の支援は、日本のODAの最も重要な考え方であり、平和、民主化、人権保障のための努力や経済社会の構造改革に向けた取組を積極的に行っている途上国に対しては、重点的に支援を行うこととしている。こうした考えに立って、日本は、政策立案及び制度整備の面で、研修員受入や専門家派遣などの技術協力をはじめとした多角的な民主化支援を展開している。
<地球的規模の問題への取組>
近年、経済分野における諸活動の高度化・拡大に起因する地球温暖化、オゾン層の破壊等の地球環境問題や、途上国における人口増加、グローバル化の進展に伴う武器、薬物の密輸や人身取引をはじめとする国際組織犯罪、テロ、そしてHIV/AIDS等の感染症といった国境を越える問題が深刻化する中で、一国では対処できないこれらの地球的規模の問題に対する取組強化の重要性が認識されるようになった。ODA大綱ではこうした地球的規模の問題は、国際社会が直ちに協調して対応を強化すべき問題であり、日本としてもODAを通じてこれらの問題に取り組んでいくこととしている。また、2004年12月に発生したスマトラ沖大地震及びインド洋津波被害も踏まえ、防災分野でもODAを活用して、積極的に対応していくこととしている。
<平和の構築>
国際社会では、紛争要因や紛争形態の変化に伴い、紛争予防・紛争解決のための手段として、国連平和維持活動(PKO)や多国籍軍の派遣、及び予防外交や調停などの政治的手段のみならず、紛争後の国づくりも含めた包括的な取組が求められていることが認識されはじめ、平和構築における開発援助の果たす役割が重要視されるようになっている。
日本は、これまでカンボジア、コソボ、東ティモール、アフガニスタン、イラク、パレスチナ自治区、アフリカ等において紛争下の緊急人道支援(紛争当事国、周辺国への緊急援助、難民・国内避難民支援)、紛争の終結を促進するための支援(和平プロセスの促進、貧困削減、格差是正への支援等)、紛争終結後の平和の定着や国づくりのための支援(和平プロセスの支援、人道・復旧支援、国内の安定・治安の確保、復興・開発支援)まで、状況の推移に即した継ぎ目のない支援を行っており、今後とも、アフガニスタン、イラクをはじめとした国・地域への平和の定着と国づくりに積極的に貢献していく考えであり、さらには、スリランカ、インドネシアのアチェ、フィリピンのミンダナオなどにおける和平の促進のためにも、日本のODAを活用した取組を検討・実施していくこととしている。
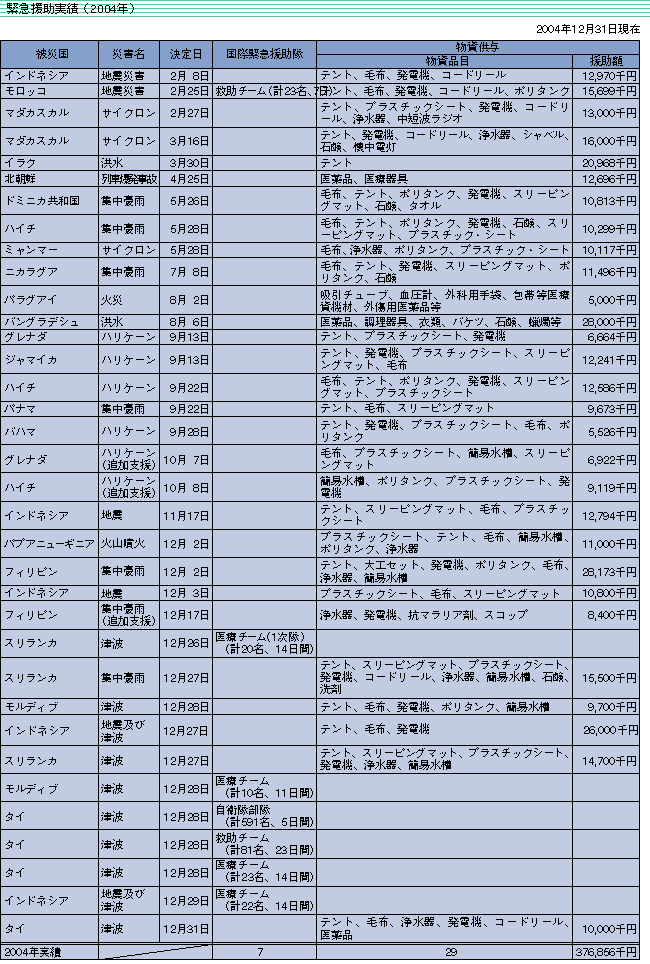
Excelファイルはこちら
現場発で組織の枠を超えてODA改革を推進~バングラデシュからの報告~
テキスト形式のファイルはこちら |