第4節 政府開発援助(ODA)
【総論】
近年の厳しい日本の経済・財政状況の中にあっても、自然災害による被災国への支援や貧困問題等の開発問題への取組をはじめ、日本が国際貢献を行う上でODAが果たす役割は依然として大きく、国際社会からも高い評価を得ている。日本としては、過去半世紀以上にわたって積み上げてきたODAの成果に立脚するとともに、2003年に改定されたODA大綱に則して、引き続き国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて日本の安全と繁栄の確保に資するよう取り組んでいく考えである。ODAが日本外交において重要な外交手段の一つであることは今後も変わりはなく、引き続き外交上の政策目的との整合性を維持しつつ、一層戦略性を高め、効率的・効果的な実施に努めていく考えである。
以下では、日本のODAの50年の歩みを振り返ってみたい。
<これまでの歩み:日本のODA50年>
2004年、日本の政府開発援助(ODA)は50周年を迎えた(注1)。これまで日本は、自助努力支援という考えに立って、途上国の国づくりの基盤となる経済社会インフラの整備や人づくりを進めており、経済発展の促進、所得の向上、貧困削減、保健医療、教育等の分野における支援を通じて人々の生活向上に寄与してきた。また、自らの経済発展の経験を生かしつつ、経済力の向上とともに援助量を拡大させ、1991年から2000年までの10年間にわたり、ODA実績で世界第1位の地位にあった。援助実績が減少している今日においてもなお、米国に次いで世界第2位の援助国であり、これまでに援助をしてきた国・地域は185か国・地域、2003年までの総額は累計約2,210億ドルにのぼる。
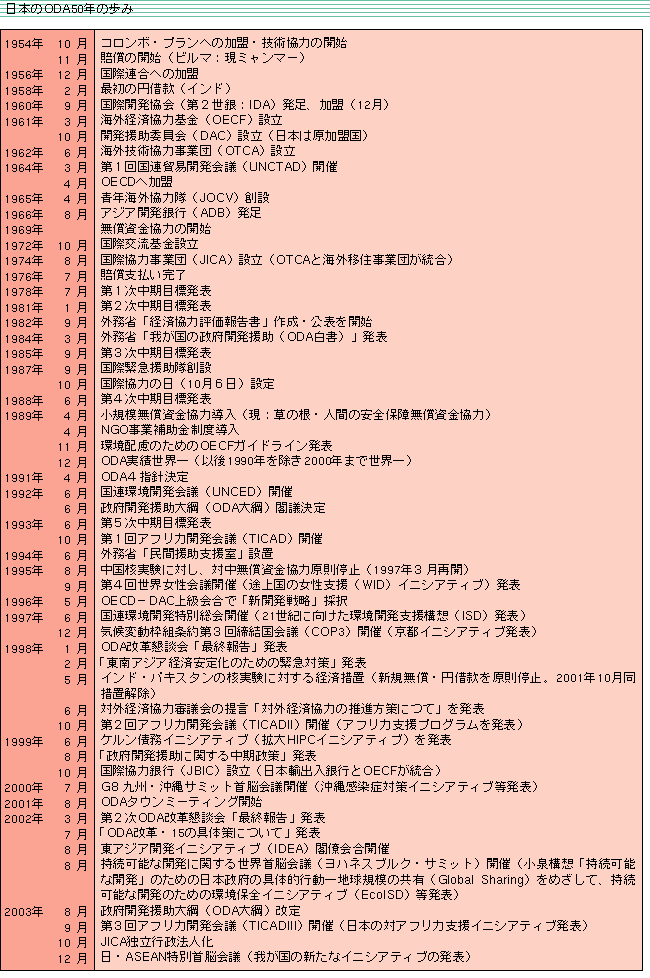
(1)体制整備期(1954年~1976年頃)
日本は、1954年10月、コロンボ・プラン(注2)への加盟によりODAを開始した。当時はアジア諸国との賠償等に関する協定の締結が進み、戦後処理としての賠償と平行して経済協力が実施された。この間、現在の国際協力機構(JICA)の前身にあたる海外技術協力事業団や、国際協力銀行(JBIC)の前身にあたる日本輸出入銀行、海外経済協力基金(OECF)が創設されるなど、援助体制も徐々に整備された。
(2)計画的拡張期(1977年~1991年頃)
1976年、フィリピンを最後に賠償支払が完了したことを受け、日本のODAは新たな局面を迎えた。1978年には国際社会からの期待と国内のODA拡張・推進論を背景に、3年間でODA実績額を倍増させるという第1次ODA中期目標を発表し、その後も量的拡大を図るとともに、災害緊急援助、文化無償資金協力、食糧増産援助を開始するなど、質的改善を図った。
(3)政策・理念充実期(1992年~2002年頃)
1992年には、冷戦後の国際環境の下で、中長期的かつ包括的な援助政策をまとめたODA大綱を策定した。ODA大綱では、日本の援助の基本理念として、1)人道的考慮、2)相互依存関係の認識、3)環境保全、4)開発途上国の離陸に向けての自助努力の支援を掲げた。以後、このODA大綱に従い、地域別・国別の援助政策を強化すると同時に、各種の分野別イニシアティブの発表・推進を通じて、地球的規模の諸問題への取組を強化した。こうした動きは、国際的な援助の議論における日本の発言力強化につながり、国際社会全体の開発目標「ミレニアム開発目標(MDGs)」(注3)の前身たるDAC「新開発戦略」(注4)策定の際にも日本は中心的な役割を果たした。また、1999年にはODA中期政策(注5)を策定した。外務省は、透明性確保、効率性向上、国民参加を柱とするODA改革を着実に進めている。
(4)新たな時代への対応(2003年~現在)
2003年8月、ODAを取り巻く国内外の状況の変化を踏まえ、ODAの戦略性、効率性を高め、国民参加を拡大し、日本のODAに対する内外の理解を深めるため、ODA大綱を11年ぶりに改定した。新しい大綱では、「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じてわが国の安全と繁栄の確保に資すること」をODAの目的とし、日本のODAの基本方針、重点課題、重点地域などを包括的に提示している。
<変化しつつある日本のODA>
新ODA大綱は、日本の援助の理念や原則等を明確に示しているが、新ODA大綱に示された考え方を踏まえ、これを更に、中期政策、国別援助計画、分野別イニシアティブなどの具体的な政策、そして、個々の援助プロジェクトに反映させていく必要がある。
国別援助計画は、現地ODAタスクフォースの積極的関与の下で、有識者から構成される各国別の国別援助計画策定タスクフォースを中心に検討作業を行い関係府省との協議、NGO、経済界、援助実施機関との意見交換、被援助国における政府、経済界、NGO等からの意見聴取等、援助に係る多様な関係者の意見を踏まえて策定される。
2000年以降、2005年2月までに19か国の国別援助計画が策定されているが、特に近年作業が行われた、対ベトナム国別援助計画の改定と対スリランカ、対モンゴル、対インドネシア、対パキスタン国別援助計画の新規策定に関しては、ODA総合戦略会議(注6)での議論を経た上で、対外経済協力関係閣僚会議(注7)において正式に了承された。2004年12月現在、今後1、2年を目途に、インド、ラオス、ウズベキスタン・カザフスタン、エチオピアの5か国について国別援助計画の新規策定作業及び、バングラデシュ、ガーナ、タイ、エジプト、フィリピンの5か国についての改定作業が進められている。
また、これまでのODA中期政策が旧大綱の下で策定され、策定後5年が経過したこと等に鑑み、2005年2月、ODA中期政策を抜本的に見直し、新たな中期政策を策定した。新中期政策では、「人間の安全保障」の視点や、貧困削減、持続的成長、地球的規模の問題への取組、平和の構築といった重点課題の考え方、アプローチ及び具体的取組、現地機能の強化を主眼とした効率的・効果的な援助の実施に向けた方策等について記述し、ODAを一層戦略的に実施するための方途を示した。
諸外国との貿易や投資から恩恵を受け、天然資源や食料を海外に依存する日本にとって、平和で安定した国際環境は必要不可欠である。日本がODAを活用して平和で安定した国際秩序の構築や、途上国の開発問題、さらに地球規模の課題への取組に主導的な役割を果たしていくことは、国際社会の調和的かつ互恵的な発展に貢献し、国際社会からの厚い信頼を獲得し、ひいては日本の安全と繁栄につながるものである。そのため日本は、より効果的な援助実施のために様々な取組を積極的に進めており、今後ともODA改善に向けた取組強化を図っていく考えである。
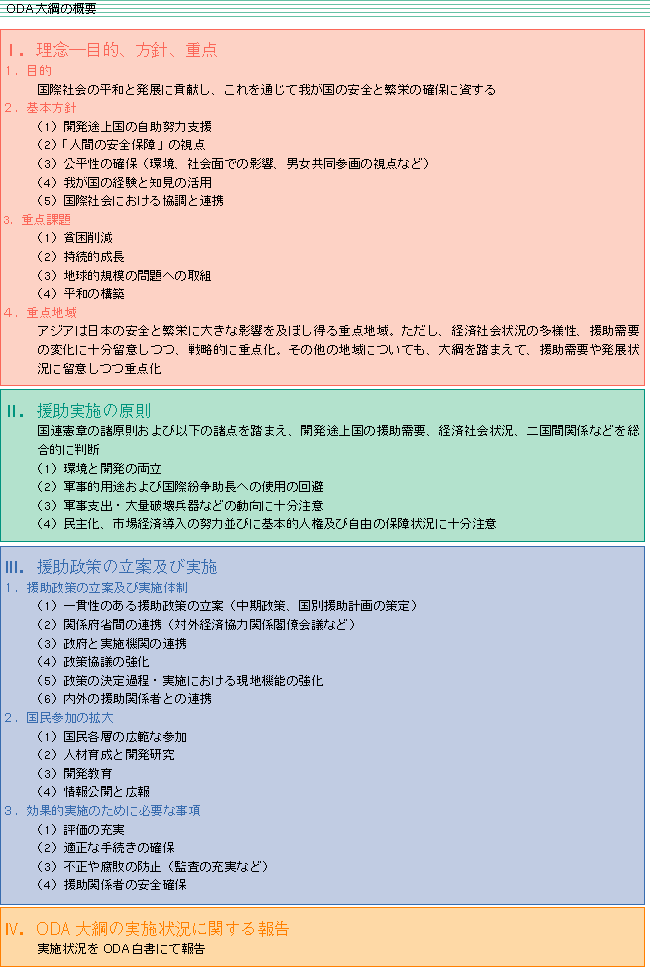
Excelファイルはこちら