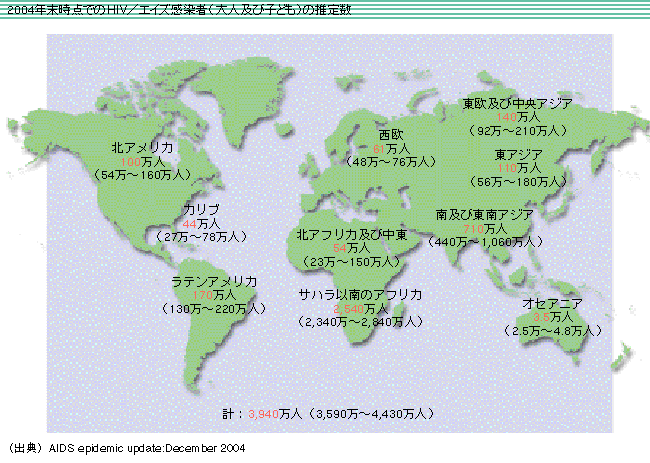2 感染症対策
エイズ(HIV/エイズ)、ポリオ、結核、マラリア、寄生虫症等の感染症は、特に途上国にとっては、単に住民の生命への脅威という保健・医療の問題にとどまらず、経済・社会開発への阻害要因となっている。また、グローバル化の進展により容易に国境を越えて他国にも広まる可能性があることから、国際社会が取り組むべき地球規模の課題となっている。
日本はこのような認識の下、2000年のG8九州・沖縄サミットにおいて「沖縄感染症対策イニシアティブ」を発表した。同イニシアティブでは、向こう5年間に30億ドルを目途とする感染症対策支援を表明し、被援助国政府、他の援助国、国際機関、NGO、民間セクター等と連携することを基本方針として包括的な感染症対策を推進している。具体的には、感染症予防のための啓発活動や物資・ワクチンの供与、医療従事者の養成等の人材育成などを実施しているほか、SARSや鳥インフルエンザ等の新興感染症に対しても適切な対策を実施してきた結果、2000年以降の日本の援助実績は総額24億ドル以上に達している。
また、前述の九州・沖縄サミットにおける日本の主張が契機となり、その後のG8サミット、国連エイズ特別総会等での議論を経て、2002年1月に世界エイズ・結核・マラリア対策基金(以下「世界基金」と略)が設立された。日本はいち早く同基金への2億ドルの拠出を表明し、米国、フランスのほか主要なドナー国とともに理事会の一員として世界基金の管理、運営に重要な役割を果たしている。世界基金は、開発途上国におけるエイズ、結核、マラリアの予防、治療などの対策を支援するため既に合計130か国の約300案件に対し総額30億ドルの資金供与を決定している。日本は、2005年1月現在で既拠出分と併せて総額2億6,500万ドルを世界基金に拠出した。2004年6月のG8シーアイランド・サミットにおいても世界基金の重要性が再認識され、小泉純一郎総理大臣は11月末のASEAN+3の首脳会議において、アジアでエイズの脅威に対する認識を高める必要があり、世界基金を活用し有効な対策を講じていくことが重要であると訴えた。
そのほか、2004年7月にタイで開催された「第2回HIV/AIDSに関するアジア太平洋閣僚会議」においては、エイズ対策における日本の貢献を積極的にアピールするとともに、共同宣言の中でアジア太平洋地域におけるグローバル基金の活用や南南協力、人間の安全保障等、地域最大の供与国としての日本の考え方を示した。