【ロシア情勢】
<ロシア内政>
2003年12月のロシア議会選挙における与党「統一ロシア」の圧勝を背景として、プーチン大統領は、2004年2月、4年間首相を務めてきたカシヤノフ首相を解任し、3月、フラトコフ駐EUロシア代表を首相に任命し、閣僚を半数近くに減らす大幅な機構改編を断行した。その後、同大統領は3月14日の大統領選挙で約71%の高い得票率を得て再選され、自らの政治基盤をさらに強化して任期2期目に入った。
一方、チェチェン問題に関連したテロ事件などはむしろ激化の様相を呈し、特に、2004年5月には、カディロフ・チェチェン共和国大統領が爆弾テロにより暗殺され、これを受け、8月に行われた共和国の大統領選挙前後には、2機の旅客機の同時爆破、モスクワ市内地下鉄付近での自爆テロ、北オセチア共和国ベスラン市での学校占拠事件が起きるなど、緊迫した状況が続いた。プーチン大統領は、これら一連のテロ事件を受けて、国家体制を強化する必要があるとして、一連の政治制度の改革を提案した。同提案のうち、12月には、知事など連邦構成主体の首長の直接選挙を廃して大統領が事実上任命する制度に改める法案が採決されたが、これにより大統領の権限はますます強化された。
<ロシア経済>
2004年のロシア経済は、主として石油の国際価格が高値で推移したことを背景に、前年と同程度の高い成長率(対前年比GDP7.1%増)を維持した。なお、プーチン大統領は2003年の年次教書演説の中で今後10年間に国内総生産を倍増する目標を表明したが、2004年の教書演説でもこれに言及し、最近の好調が続けば2010年までに目標達成も可能である旨述べた。
一方、経済改革の分野では、構造改革の停滞が指摘されている。また、巨大石油企業「ユコス」社が、ロシア当局により巨額の追徴課税を受け、その支払いのために、同社の中核を成す子会社が売却される(12月)など厳しい措置を受け破産の危機に瀕したほか、その子会社を国営企業である「ロスネフチ」社が事実上購入するなどの動きも見られ、国際的な注目を集めた。
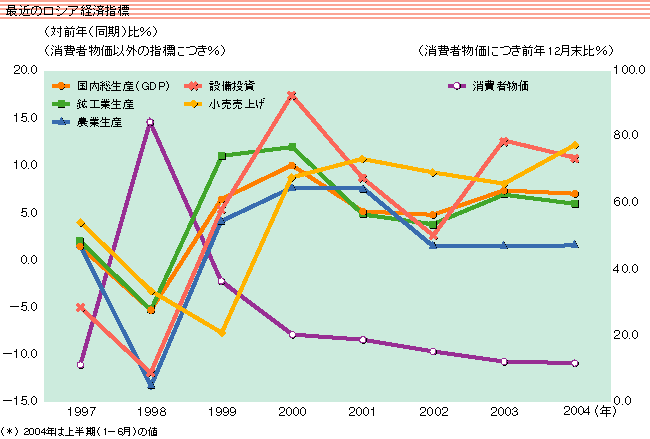
Excelファイルはこちら