【ASEAN情勢全般】
加盟国間の社会体制の相違や経済格差が顕在化する中、ASEANにとってはASEANの地域としての競争力を強化し、より高いレベルでの統合を達成するという観点から、地域共同体としての一体性の確保が重要な課題となっている。これまでASEAN統合イニシアティブ(IAI)を通じ、原加盟国と新規加盟国であるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムとの格差を是正するため、積極的に税関、輸送インフラ整備、FTA等に関するキャパシティ・ビルディング支援プロジェクトを実施するなど、地域統合に向け地歩を固めてきた。2003年の首脳会議の際にASEAN各国間で署名された第二ASEAN協和宣言(バリ・コンコードII)(注40)において、ASEAN安全保障共同体(ASC)、ASEAN経済共同体(AEC)及びASEAN社会・文化共同体(ASCC)が、2020年までのASEAN共同体構想の柱(注41)として示され、2004年のASEAN首脳会議では、その実現のためのロードマップとしてビエンチャン行動プログラム(注42)が採択された。
また、ASEAN首脳会議に合わせて開催されるASEAN+3(日中韓)首脳会議の他にも、ASEANは、オーストラリア及びニュージーランドとの特別首脳会議を2004年に初めて行い、両国とのFTAの締結に向けた交渉の2005年の早期の開始と二年以内の交渉終了に合意するなど、ASEANと域外国との関係の強化を目指す動きは一層活発化している。
このほか、国際的なネットワークを有するテロリストの脅威やマラッカ海峡の海賊問題といった国境を越える問題が非伝統的安全保障の問題として認識され、また東南アジア友好協力条約(TAC)に日本(2004年)のほか、中国(2003年)、インド(2003年)、韓国(2004年)、パキスタン(2004年)、ロシア(2004年)が加盟するなど、80年代から90年代にかけて経済成長という文脈で語られがちであった東南アジア地域の国際情勢は、ASEANを中心として政治面を含めて多様なダイナミズムを見せている。
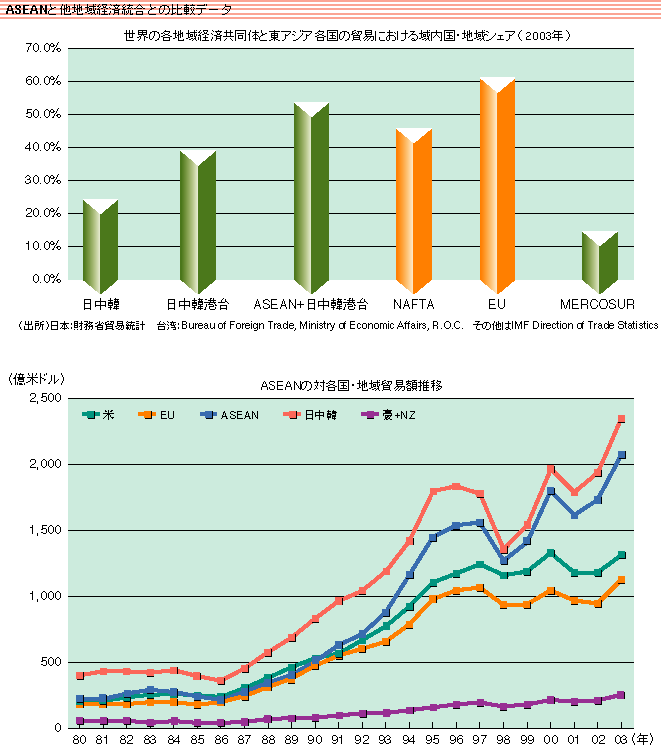
ドキュメントファイルはこちら