【中国情勢】
<内政>
胡錦濤国家主席を中心とする新指導部は、2004年3月に行われた第10期全国人民代表大会第2回会議において、雇用、教育、医療衛生といった国民にとり身近な問題に重点的に取り組む姿勢(「親民路線」)を強調した。また、市場経済化を通じた急速な経済発展による歪みを解消し、調和のとれた発展を実現するため、伸び悩む農村経済及び農民収入の改善、西部大開発や東北地域開発などを通じた地域間格差の是正、中央・地方政府における法に基づく行政の徹底及び行政事務の効率化等の方針を発表した。憲法改正を実施し、「三つの代表」思想(注35)、私有財産権の保護や人権の尊重と保障に関する規定等が新たに盛り込まれたほか、3月には人権分野に関する白書(「2003年中国人権事業の進展」)を発表した。
9月中旬に行われた中国共産党第16期中央委員会第4回全体会議(四中全会)では、江沢民(こうたくみん)党中央軍事委員会主席が辞任し、後任に胡錦濤総書記が就任した。これにより胡主席は、党(総書記)、国家(国家主席)に続き軍の最高位のポストを掌握することとなった。今次会議のコミュニケでは、中国共産党の執政能力の強化に関する記述が大半を占め、前回会議(昨年10月)のコミュニケが経済問題を中心に言及したのに比べ、政治に重点を置いた内容となった。
また、10月以降、中国各地における民衆による抗議行動の発生を報ずる報道が香港紙を中心として増加した。原因の多くは、税・費用負担をめぐる問題や、公務員の汚職・腐敗等とされている。2005年3月に開催された第10期全国人民代表大会第3回会議では、「調和のとれた社会」の実現を目指し、社会保障システムの整備、政府機能の強化及び公務員の資質向上に取り組むことなどが改めて強調された。また、江沢民国家中央軍事委員会主席が辞任し、後任に胡錦濤国家主席が就任した。
2004年12月末には、国防白書「2004年中国の国防」が発表された。中国の国防白書の発表は1995年以降通算5度目であり、1998年以降は2年毎に発表されている。2004年の国防予算は、前年度比(実績ベース)約12.6%増で引き続き高い水準で推移しているが、同白書は国防費増加の要因につき、人件費及び装備費等の増額であると説明している。
<経済>
2004年の中国経済は、一部産業を中心に経済の過熱が懸念され、中国政府は引き締め策(セメント等一部の分野の投資制限や法定金利の引き上げ等)を講じたが、GDPの成長率は、2003年と同水準の9.5%(2004年3月の全国人民代表大会で提起された目標は7%前後)を記録した。
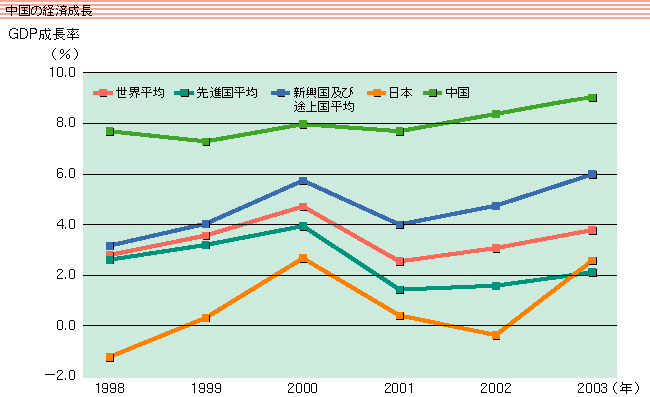
Excelファイルはこちら
中国の新指導部は、2020年までにGDPを2000年時の4倍増とする方針(注36)を掲げる一方で、経済成長のみを追求せず、社会全体の持続的な均衡発展を目指す「科学的発展観(注37)」を提唱し、経済格差の是正や産業構造の調整等に取り組んでいる。2005年3月に開催された全国人民代表大会は、2005年の主要課題として、8%前後の経済成長を目標に、科学的発展観を踏まえた、過剰投資抑制のためのマクロ・コントロール、三農問題(農業、農村、農民)対策、経済格差是正への取組を政策として掲げ、また、省エネや循環型経済といった概念を強調している。
<対外関係>
中国は、最優先課題である経済発展を確保するために安定した国際環境を必要としており、米国、ロシア、欧州諸国等の主要国との関係発展、近隣諸国との協力強化及び国際的な枠組みへの積極的な参加などの全方位外交を展開しており、そのような方針は、現指導部の下においても継続されている。北朝鮮の核問題については、中国は、朝鮮半島の非核化及び対話による平和的解決を望むとの立場から、引き続き関係諸国との調整を行い、2月及び6月に六者会合を開催するなど、問題解決のために積極的な役割を果たしてきている。
米中関係については、11月のAPEC首脳会議の際に米中首脳会談を行い、米中間の「建設的協力関係」を改めて確認するとともに、北朝鮮の核開発問題、イラク問題等につき議論したほか、首脳・外相間の電話会談や米国要人の訪中を通じて(注38)、台湾問題、北朝鮮問題、貿易通商問題、通貨問題等について議論が行われた。
中露関係は、5月に胡錦濤国家主席、9月に温家宝総理が訪露したほか、10月にはプーチン・ロシア大統領が訪中し、それぞれ中露間の戦略的協力パートナーシップの強化が確認され、また、北朝鮮、イラク問題等につき協議が行われた。なお、10月のプーチン・ロシア大統領の訪中の際には、一部未解決であった国境線上の河川に存在する三島の分割処理を含む東部国境画定に関する「追加合意文書」が調印され、約4,300キロに及ぶ中露国境がすべて画定した。
EUとの関係においては、温家宝総理が5月にドイツ、ベルギー、イタリア、英国等を訪問し、中・EU戦略的パートナーシップ及び広範な経済関係の強化を目指すことで合意したほか、12月に中・EUサミットが開催された。また、胡錦濤国家主席が1月の訪仏に続き、6月には2度目の欧州訪問を行うなど、EUにも力点を置いた多極化外交を推進している。
また、胡錦濤主席のアフリカ(2月)、中南米(11月)訪問等、要人往来の機会を通じて、中国は急速に向上する経済力を背景に、これら地域との関係も強化しつつある。
<香港>
2004年4月、中国全国人民代表大会常務委員会が2007年以降の行政長官の選出方法及び2008年以降の立法会議員の選挙方法を規定した香港基本法付属文書の解釈を発表した。2007年の行政長官の選挙から、普通選挙を行うことが法的に可能となった一方、選挙方法の改正の必要性については、全国人民代表大会が決定することとなった。また、返還7周年に当たる7月1日には、こうした事情に加え、反国家行為・組織を禁ずる基本法23条の扱いをめぐる問題、さらに2003年の経済不振、重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応の不十分さなどから来る現香港政府指導部への反発から、2003年に続き民主派を中心とした民衆の大規模なデモが発生した。
9月に行われた返還後3回目の立法会選挙では、民主派が大幅に躍進するとの予想に反し、現有議席をわずかに上回るにとどまり、回復基調にある経済を背景に親中派が引き続き過半数を確保する結果となった。
経済面では、2003年後半より引き続き顕著な改善を見せており、特に2004年に入ってからの経済成長率は非常に高く、2004年の実質経済成長率は7.5%となった。
なお、2005年3月、董建華行政長官が辞任し、曾蔭権(ドナルド・ツァン)政務長官が行政長官代理に就任した。
日本と香港の関係については、香港は総額で第5位の日本の貿易相手先となっている。また、2004年4月には、査証免除措置を実施しており、2004年の訪日者査免は約60万人以上に上っている。
(2)台湾
2004年の台湾では3月に総統選挙、12月に立法院選挙が実施された。3月の総統選挙では陳水扁総統が0.22%の僅差で再選されたが、立法院選挙では与党・民進党が第一党の座を確保したものの、野党連合が過半数を獲得し、陳総統は引き続き困難な政権運営を強いられることとなった。総統選挙と同日で実施された、対中ミサイル防衛能力の強化と対中協議メカニズム構築の是非を問う台湾で初めての公民投票は、有権者の過半数を超える投票が得られず不成立に終わった。
経済面では、民間投資の顕著な伸び、好調な輸出、失業率の改善(2003年の5.0%から4.4%)、2003年のSARSによるマイナス影響への反動等から、年間成長率は5.7%となった。
陳総統は5月20日の就任演説と10月10日の演説において中国に対話を呼びかけたが、2004年も両岸対話は再開されなかった。中国は2005年3月に全国人民代表大会で、台湾独立への反対及び牽制を目的とする「反国家分裂法」を可決したが、台湾は同法は台湾への武力行使を合法化するものとして強い反発を示している。その一方で、両岸間の経済交流は着実に拡大し、台湾の大陸委員会の統計によれば、中国は台湾にとって最大の貿易相手となるとともに、2005年1月には、旧正月期間中に初めて中台双方で直航便を相互乗入れさせることで合意に達した。
日本と台湾の関係については、1972年の日中共同声明に従って、非政府間の実務関係として維持されてきている。日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する重要な地域であり、台湾は、総額で米国、中国、韓国に次ぐ第4位の日本の貿易相手先となっている。また、2004年には台湾からの訪日者数が100万人を突破した。
両岸関係については、日本としては、当事者間の直接の話し合いを通じて平和的に解決されること、そのための両岸対話が早期に再開されることを強く希望している旨を中台双方に表明している。
(3)モンゴル国
モンゴルでは、2004年6月、第4回国家大会議総選挙が行われ、与党・人民革命党が大きく議席を減らす一方、野党の祖国・民主連合が大躍進した。しかし、いずれも過半数の議席数に至らず、その結果両者による大連立内閣が成立した。なお、首相には、祖国・民主連合から、エルベグドルジ(元首相)が、また国家大会議長には、人民革命党からエンフバヤル(前首相)がそれぞれ就任した。2005年夏には大統領選が行われる予定である。
経済面では、2004年の経済成長率は、2003年の5.5%から10.6%となり、大幅な伸びを示した。失業率は2003年の3.5%から3.6%となった。なお2003年末には、長年の懸案であった対ロシア債務問題が解決された。
外交面では、2004年7月にはバガバンディ大統領が中国、米国を訪問し、それぞれ胡錦濤国家主席、ブッシュ大統領らと会談を行ったほか、同年12月には北朝鮮を訪問するなど、活発な外交が見られた。またモンゴルは、イラク復興支援のため、昨年に引き続きイラクに国軍を派遣している。
モンゴルにおける民主化と市場経済化の成功は、北東アジア地域の平和と安定に寄与するとの認識の下、日本はモンゴルを積極的に支援している。8月には川口外務大臣(当時)が外相の単独訪問としては15年ぶりにモンゴルを訪問し、日本・モンゴル間の「総合的パートナーシップ」を今後とも一層強化させていくことを確認した。11月には、政府全体として一体性・一貫性をもって効率的・効果的なODAを実施していくため、対モンゴル国別援助計画が決定された。