第4章 > 第1節 外務省改革
【総論】
2001年初頭の外務省をめぐる不祥事の発覚以来、外務省では、改革に向けた取組を積極的に進めてきた。しかし、2002年1月以降も、アフガニスタン復興支援国際会議への非政府組織(NGO)出席拒否問題を始めとする政治家と官僚との関係のあり方をめぐり、外務大臣、事務次官の両名が辞任し、3月には北方四島の住民支援に関する特定議員の関与をめぐる問題が明らかになった。このような状況を受け、川口外務大臣の就任後、できることは直ちに実施するとの方針の下、外務本省・在外公館の幹部ポストへの民間などからの人材の起用、外務省タウンミーティングの実施、支援委員会の事業の見直しなどの措置を進めた。外部有識者からなる「変える会」や外務省内部の有志のグループ等の提言を踏まえ、外務省は、在瀋陽日本総領事館事件といったその後の出来事をも踏まえながら、更に省全体の改革を進め、国民の信頼を取り戻すための努力を続けている。
【川口外務大臣による外務省改革の一層の促進】
2001年、外務省は、同年初めより明らかになった一連の不祥事を深く反省し、報償費の支出手続を含め、公金の不正な使用・流用を許した従来の会計・予算手続を大きく改めた。また、再発防止を徹底し、内部のチェック機能を強化するとの観点から、同年9月以来、公認会計士などの外部専門家の参加を得ながら、在外公館への査察を強化する一方、外務本省への監察制度を新たに導入した。
外務省改革は、2002年2月に就任した川口外務大臣の下で更に強化された。川口外務大臣は、就任直後、透明性、スピード、実効性をキーワードとする「開かれた外務省のための10の改革」を発表し、「一連の不祥事により失われた国民の皆様の信頼を一刻も早く取り戻せるよう、改めるべき点は改め、国民全体の奉仕者としての意識を外務省員に徹底させ、国益を守る強靭〔きょうじん〕な外交ができる体制を整えていく」(「開かれた外務省のための10の改革」冒頭部分引用)方針を打ち出した。これに基づき、2002年3月、外部有識者からなる「変える会」(座長:宮内義彦・オリックス株式会社代表取締役会長)が発足し、5月9日、「開かれた外務省のための10の改革」に盛り込まれた10のテーマに関する検討結果を「中間報告」として発表した。同発表前日、5名の北朝鮮住民が在瀋陽日本総領事館に駆け込むという事件が発生したことを踏まえ、その後、「変える会」は、危機管理体制の整備と政策構想力の強化という二つのテーマについても議論を重ね、7月22日、これらを含む「最終報告書」を川口外務大臣に提出した。また、与野党からも外務省の組織の見直しを含めた外務省改革案が提示された。さらに、3月以来、外務省内で省員有志が自らの手で外務省改革を行うことを目的とした自主的なグループ「変えよう!変わろう!外務省」が活動を始め、7月12日、「報告と提言」をとりまとめ発表した。
このような動きを踏まえ、外務省は、「変える会」最終報告書の発表直後から外務省独自の改革案の策定作業に着手し、8月21日、外務省改革「行動計画」を発表した。同時に、川口外務大臣を本部長に、外務副大臣、外務大臣政務官及び各局(部)長などからなる外務省改革推進本部及び事務局を設置し、「行動計画」に基づく改革作業に着手した。
「行動計画」は、今日、日本を取り巻く国際環境が大きく変動する中で、アジア太平洋地域の平和と安定の確保や、テロ、軍縮、地球環境、貿易問題等の国際社会が抱える諸問題への取組において、日本は、国益に立脚した主体的な外交を展開する必要があり、このために、政策構想力を磨き外交イニシアティブを果敢に発揮しなくてはならないとの考えに基づき策定されたものである。政府開発援助(ODA)を含む幅広い分野での改革を内容としており、主要点は、以下の4点である。
 21世紀の新たな国際環境を見据えた日本外交を積極的に展開するため、組織として政策構想力と危機管理能力を強化すること。
21世紀の新たな国際環境を見据えた日本外交を積極的に展開するため、組織として政策構想力と危機管理能力を強化すること。
 省員の意識改革と徹底した競争原理の導入を図ること。
省員の意識改革と徹底した競争原理の導入を図ること。
 外交施策の透明性と効率性を確保すること。
外交施策の透明性と効率性を確保すること。
 国民への行政サービスの向上を目指し、領事業務を強化すること。
国民への行政サービスの向上を目指し、領事業務を強化すること。
外務省は、2月の「開かれた外務省のための10の改革」の発表以来、できることは直ちに実施するとの考え方に従って、競争原理に基づいて有能な人材を積極的に起用することに努めている。川口外務大臣の就任以来、省外より16名(2003年1月末現在)を外務本省の幹部及び在外公館の大使・総領事等に起用した。また、4月以来、国民との対話を目的に、川口外務大臣自らが参加して外務省タウンミーティングを全国各地で開催している。また、国際社会での重要性がますます高まるNGOと密接に連携しながら外交を行うとの観点から、常設ポストとしてNGO担当大使を任命したほか、7月9日に発表した「ODA改革・15の具体策について」では、透明性の確保、効率性の向上、国民参加を柱に、監査、評価、人材の発掘・育成・活用、情報公開・広報と並んでNGOとの連携を盛り込んでいる。
領事業務の強化については、 領事業務に関する省員の意識改革と研修、
領事業務に関する省員の意識改革と研修、 領事行政サービスの向上、
領事行政サービスの向上、 邦人安全対策・危機管理の強化、
邦人安全対策・危機管理の強化、 領事事務における情報通信技術(IT)の活用の4本柱の下で、具体的な施策が進められている。
領事事務における情報通信技術(IT)の活用の4本柱の下で、具体的な施策が進められている。
なお、2002年2月以降、北方四島住民支援等を実施してきた国際機関である支援委員会のあり方をめぐって種々の問題点が指摘された。これを受けて川口外務大臣の主導で設置された外部有識者からなる「支援委員会改革のための専門家会議」からの提言を重く受け止め、支援委員会を廃止するとの方針の下、支援委員会設置協定の締約国との協議を開始した。支援委員会廃止後の対露・対北方四島住民支援については、抜本的見直しを行うとともに、支援の実施にあたっては、透明性の向上等これまでに指摘された問題の再発防止策を講じた上で、新たな枠組みの下で実施していく予定である。
「変える会」は、9月以降も活動を続けており、「行動計画」の実施状況を確認するための会合を重ねている。外務省としては、このような会合を通じ「変える会」の助言を得ながら、外務省が自ら策定した「行動計画」を着実に実施することによって、一日も早く国民の信頼を取り戻せるよう、全省員が一丸となり外務省改革を推進していく考えである(注1)。
また、日本外交を強力に展開していくため、外務省は、12月20日、外交実施体制の強化を目的とした本省の機構改革に関する「中間報告」を発表した。引き続き、外務省が国民の期待にこたえる外交を推進するため、内部組織のあり方の検討を行い、2003年3月末までに機構改革に関する外務省としての「最終報告」を出す予定である。
宮内義彦「変える会」座長より、最終報告書を受け取る川口外務大臣(7月)
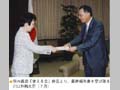
【ODA改革の推進】
2002年、外務省は、ODA改革の具体策を相次いで発表・実施してきた。具体的には、7月の「ODA改革・15の具体策について」及び8月の「行動計画」に従って、透明性の確保、効率性の向上、国民参加を柱とするODA改革を着実に進めている。また、12月には、「ODA大綱の見直し」、「無償資金協力実施適正会議の立ち上げ」及び「債務救済方式の見直し」からなる「ODA改革:三項目の実施について」を発表した。ODA改革の主な取組(注2)は、以下のとおりである。
〈ODA戦略の強化〉
ODA大綱(1992年6月閣議決定)について、策定後10年間に生じた国内・国際状況を踏まえ、2003年中ごろをめどに見直しを行っている。
〈透明性確保のための措置〉
 監査の拡充
監査の拡充
●外部専門家による監査を可能なものから導入している。
●2003年度より、「抜き打ち監査」を順次導入することとしている。
 評価の拡充
評価の拡充
●すべての事後評価に第三者の視点を導入している。
●外務省及び実施機関(国際協力事業団(JICA)及び国際協力銀行(JBIC))に、外部有識者による評価委員会を設置している。
 情報公開・広報
情報公開・広報
●ODAタウンミーティングを全国各地で定期開催している。
●ODAメールマガジンを原則月2回のペースで定期発刊している。
 無償資金協力の適正な実施と透明性の向上を図るため、「無償資金協力実施適正会議」を立ち上げ、2002年2月に第1回会議を開催した。
無償資金協力の適正な実施と透明性の向上を図るため、「無償資金協力実施適正会議」を立ち上げ、2002年2月に第1回会議を開催した。
〈効率的・効果的実施のための措置〉
 JICAの「環境配慮ガイドライン」を改定するために広く意見を聞きながら作業を行っている。
JICAの「環境配慮ガイドライン」を改定するために広く意見を聞きながら作業を行っている。
 食糧増産援助について、2002年12月、原則として農薬の供与は行わないなどの抜本的な見直しを行った。
食糧増産援助について、2002年12月、原則として農薬の供与は行わないなどの抜本的な見直しを行った。
 国際的な合意に基づく債務救済の実施方法として、2003年度より、従来の債務救済無償に代えて、JBICの円借款債権の放棄によることを決定した。
国際的な合意に基づく債務救済の実施方法として、2003年度より、従来の債務救済無償に代えて、JBICの円借款債権の放棄によることを決定した。
 外務省がODAに関する全体的な企画等について政府全体を通ずる調整の中核としての機能を担うため、ODA関係省庁連絡協議会、同幹事会、資金協力連絡会議、技術協力連絡会議、ODA評価連絡会議の主催を通じ、関係府省間の連携強化に努めている。
外務省がODAに関する全体的な企画等について政府全体を通ずる調整の中核としての機能を担うため、ODA関係省庁連絡協議会、同幹事会、資金協力連絡会議、技術協力連絡会議、ODA評価連絡会議の主催を通じ、関係府省間の連携強化に努めている。
〈国民参加促進のための措置〉
 NGOとの連携
NGOとの連携
●NGO支援策、ODA政策等を協議するNGO・外務省間委員会を設置し、それぞれ2002年11月11日、12月5日に開催した。
●在外公館とNGOとの定期協議会(ODA大使館)を、2002年末までに11か国で開催しており、引き続き開催していく予定である。
 人材の発掘・育成・活用
人材の発掘・育成・活用
●「国際協力人材開発センター(仮称)」を、2003年度、JICAに設置する予定である。
●すべてのJICA国内機関で、2002年度内に開発教育プログラムを実施する予定である。
【領事分野での改革】
外務省の業務の中でも、国民に直接接する機会が多く、国民生活との関係が深い領事業務は、一般の外交業務と並んで外務省の役割の重要な柱の一つである。特に、多くの日本人が海外に渡航し在住するようになるにつれ、きめ細かいサービスを求める期待や国内と同等の水準の福利や権利を享受したいとの要請も高まっている。さらに今日では、テロなどの重大な事件・事故に巻き込まれる可能性も高まっており、日本人が安心して海外で活動できる環境を整え、その活動について支援・協力することが重要となっている。こうした領事業務の重要性を踏まえ、外務省機能改革会議の提言を受けて、2001年6月に発表された外務省改革要綱の中では、領事業務についても抜本的改革の方向性が示された。
その後、「変える会」が2002年7月に発表した最終報告書を受けて、8月に「行動計画」を発表し、以下の4本柱の下で検討が重ねられ、現在までに次のような成果が得られている。
〈領事業務に関する省員の意識改革と研修〉
省員の意識改革と研修の強化については、2002年夏よりI種及び専門職の若手職員が在外研修後に領事業務に従事しているほか、本省・在外職員向けの研修を新設・拡充し、窓口対応が改善されたとの反応を得るなどの成果を上げている。
〈領事行政サービスの向上〉
領事行政サービスについては、利用者の便を向上させるため、領事関連窓口の業務時間の延長や休館時の電話対応サービスの充実、領事出張サービスの拡充が在外公館を中心に実施されている。
〈邦人安全対策・危機管理の強化〉
邦人安全対策・危機管理の強化としては、メンタルケアにおける官民協力や専門家の活用を通じて邦人保護業務の充実を図っているほか、衛星を使用した位置確認システム(GPS)を利用した邦人保護システムの配備を開始した。
〈領事事務における情報通信技術(IT)の活用〉
ITを活用し、インターネットを利用した旅券・在留届の申請・届出等を可能とすることによって、利用者にとっての利便性の向上と領事業務の効率化を図っていく方針である。また、テロリストを含む好ましくない外国人の入国を査証発給段階で、より綿密かつ効率的に精査する査証広域ネットワーク(査証WAN)システムの稼働が開始された。
外務省は、国の安全と繁栄を確保することと並んで、国民ひとりひとりの安全を確保し、利益を増進することが国益そのものであるとの認識に立って「国民と共に歩む外交」を遂行していく考えである。
外務省改革「行動計画」


 次頁
次頁 21世紀の新たな国際環境を見据えた日本外交を積極的に展開するため、組織として政策構想力と危機管理能力を強化すること。
21世紀の新たな国際環境を見据えた日本外交を積極的に展開するため、組織として政策構想力と危機管理能力を強化すること。 省員の意識改革と徹底した競争原理の導入を図ること。
省員の意識改革と徹底した競争原理の導入を図ること。 外交施策の透明性と効率性を確保すること。
外交施策の透明性と効率性を確保すること。 国民への行政サービスの向上を目指し、領事業務を強化すること。
国民への行政サービスの向上を目指し、領事業務を強化すること。 領事業務に関する省員の意識改革と研修、
領事業務に関する省員の意識改革と研修、 領事行政サービスの向上、
領事行政サービスの向上、 邦人安全対策・危機管理の強化、
邦人安全対策・危機管理の強化、 領事事務における情報通信技術(IT)の活用の4本柱の下で、具体的な施策が進められている。
領事事務における情報通信技術(IT)の活用の4本柱の下で、具体的な施策が進められている。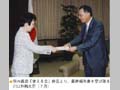
 監査の拡充
監査の拡充 評価の拡充
評価の拡充 情報公開・広報
情報公開・広報 無償資金協力の適正な実施と透明性の向上を図るため、「無償資金協力実施適正会議」を立ち上げ、2002年2月に第1回会議を開催した。
無償資金協力の適正な実施と透明性の向上を図るため、「無償資金協力実施適正会議」を立ち上げ、2002年2月に第1回会議を開催した。 JICAの「環境配慮ガイドライン」を改定するために広く意見を聞きながら作業を行っている。
JICAの「環境配慮ガイドライン」を改定するために広く意見を聞きながら作業を行っている。 食糧増産援助について、2002年12月、原則として農薬の供与は行わないなどの抜本的な見直しを行った。
食糧増産援助について、2002年12月、原則として農薬の供与は行わないなどの抜本的な見直しを行った。 国際的な合意に基づく債務救済の実施方法として、2003年度より、従来の債務救済無償に代えて、JBICの円借款債権の放棄によることを決定した。
国際的な合意に基づく債務救済の実施方法として、2003年度より、従来の債務救済無償に代えて、JBICの円借款債権の放棄によることを決定した。 外務省がODAに関する全体的な企画等について政府全体を通ずる調整の中核としての機能を担うため、ODA関係省庁連絡協議会、同幹事会、資金協力連絡会議、技術協力連絡会議、ODA評価連絡会議の主催を通じ、関係府省間の連携強化に努めている。
外務省がODAに関する全体的な企画等について政府全体を通ずる調整の中核としての機能を担うため、ODA関係省庁連絡協議会、同幹事会、資金協力連絡会議、技術協力連絡会議、ODA評価連絡会議の主催を通じ、関係府省間の連携強化に努めている。 NGOとの連携
NGOとの連携 人材の発掘・育成・活用
人材の発掘・育成・活用